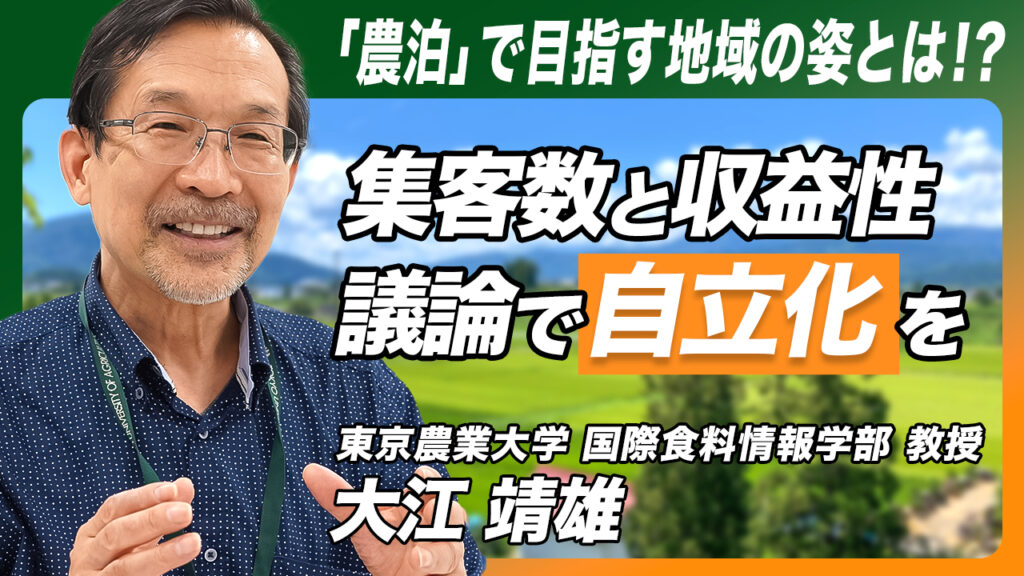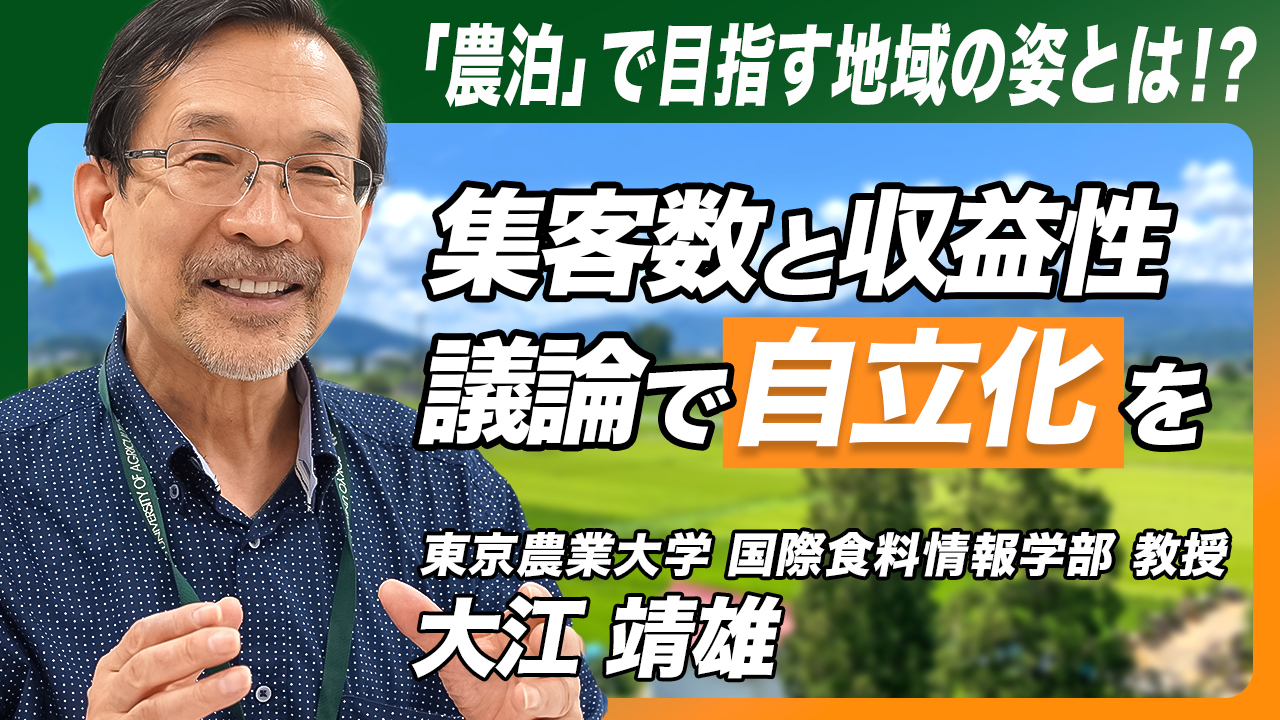――そもそも「農泊」とは。
農泊は、農山漁村に宿泊しながら、その地域の食材を味わったり、農林漁業や伝統工芸などの自然・文化を体験したり、さらには地域の人々との交流を楽しんだりする「農山漁村滞在型旅行」のこと。
農泊という言葉が使われる前は、日本ではグリーン・ツーリズムと言っていた。1990年代初め、農林水産省(農水省)で農村の活性化につながる活動を政策にして進めようという検討会があった。名前についても検討され、ヨーロッパの例などを見ながら、最終的にグリーン・ツーリズムとなった。これは、当時の報告書にも記載がある。海外では、グリーン・ツーリズムのほか、農村ツーリズムやルーラルツーリズムといった言葉が一般的である。
取り組みは、基本的に今の農泊と変わらないが、農村に都会の人が来て、農家に泊まるほか、食事、農作業体験をしながら、リフレッシュや交流が楽しめるというもの。これは、農家にとって新たな収入や仕事の機会になるほか、農村の活性化につながることが狙いだった。
――どこで農泊と言う言葉に変わったのか。
農水省では、2017年度から3年間の農泊という事業を始めた。背景だが、グリーン・ツーリズムという政策的なプログラムを、さまざまな角度から提案を変えながら取り組んできたが、目標としたレベルまで達しなかった。それは、集客数と収益性という2つの問題だ。私は、最初から収益性向上の必要姓についての意見を述べてきたが、当時の流れとしては、まず都市農村交流という形で、交流を促すことが優先され、経営問題が後ろに隠れてしまった。結果、収益性がなく、再生産ができないものとなった。
交流をするにも、その前提として、収益性があり、再生産可能な活動でなければ誰も続けない。交流疲れという言葉も使われるようになり、離脱者も増えた。このような状況が続き、収益性を上げることを眼目に据えて、名前も農泊に変更された。当時、農泊という言葉は、九州で使われていたようで、農水省が承諾を得たと聞いている。農泊という言葉を使い、活動の経済的自立性を高めることを主旨に、当初事業期間を3年間として実施された。
18年の終わりごろから、次期のポスト農泊の方向性を決めようと、農水省が農泊の検討会を設けた。私が座長を担い、外部の委員を中心に議論を行い、新型コロナ発生前の19年6月に中間取りまとめを発表した。20年度からその計画の実施を推進しようとしたが、世の中はコロナ禍になった。観光業界は壊滅的な打撃を受けたが、農泊は3割減程度に留まった。田舎では感染リスクが低く、ワーケーションやマイクロツーリズムという流れもあり、そのようなニーズを汲み取った結果といえる。
だが、コロナ禍でダメージを受けたことは事実であり、新しい農泊の方向性を再度検討しようということで、22年12月から検討会が再開され、議論を経て23年6月に「農泊推進実行計画」が取りまとめられた。内容は、最初の検討会で議論した主旨とはそれほど大きく変わっていない。ただ、前回と比べて需要面の目標値を明確にして、25年度に700万人泊を達成するという目標も掲げた。また、需要がおう盛になりつつあるインバウンドに関しても、10%を占めると想定され、潜在的なニーズがあることから、重点推進地域を設け、これをモデル地区にしていくという方向性が打ち出されている。
――目指す農泊の在り方について。
高齢化や人口減少が進み、22年度は日本の人口が約80万人減った。以前は、中小都市一つ分ぐらいの30万人ぐらいの減少が続いていたが、今は大都市が一つなくなる状況にまで陥っている。農村部に関しても、高齢化、人口減少が加速度的に進んでいる。
農村が自立しながら存続していくことは、日本の社会、バランスある経済の発展にとって非常に大事だ。農泊は、農村が頑張り、生き生きとして生活や仕事ができる場を作る手段の一つである。

――農泊で収益性を高めると言うが、具体的なイメージは。
私が抱くイメージとしては、若い人たちが経営者となり、農泊と農業を自立的に取り組むほか、地域で取れた食材をお客さんに提供することで、小規模でも自立ができ、家族を養っていけるレベルとなること。現在は、世帯で500~600万円ぐらいは稼げないと家族を養うことは難しい。次世代を育てることまで考えると、1,000万円ぐらい稼げるようになることが期待される。
農泊推進実行計画には収入に関する具体的な数字までは入っていないが、個人的な思いとして、次世代にバトンタッチできる農村ビジネスでなければならない。お金の話をすると、すごく汚い話をしていると捉えられることが多い。理想を追った趣味の世界では、当代は良いが次世代がついてこない。次世代もやりたいと思えるように、背中を見せなければならない。収益が上がらないということは、ビジネスモデルが成立していないということ。ただ都市農村交流と言っても続かない。これが基本的な現状認識で、私は持続性ある本物にしたいという思いをずっと抱いている。
――地域で整えるべき体制について。
うまくいっていない地域はけっこうある。グリーン・ツーリズム、農泊、もっと広い意味で言えば農業政策は、基本的に集落レベルで取り組まれてきた。これは、日本の農業政策の伝統となっており、農村政策も同様の形で組まれている。諸外国の言葉でいうと、コミュニティベースの活動だ。そうなると、コミュニティを運営する組織と個別の事業者が、うまく嚙み合わなければならない。今は噛み合わないことが多く、コミュニティベースの組織が作られてもその機能を発揮するまでには至っていない。組織と個別経営が両輪として回っていないことが大きな原因である。その部分については、いわゆるアントレプレナーシップ(起業家精神)を育成する必要があり、農泊推進実行計画にも農村のアントレプレナーシップという言葉が入っている。
農村のアントレプレナーシップは、企業版とは少し違う。地域の問題を常に頭に入れている人たちが、農村のアントレプレナー(起業家)であるからだ。地域と共存していく覚悟を持っているということ。アントレプレナーは土地に関わり、土地は個人のものだが地域の資源でもある。個人と地域の両方を満たしていく自立的な活動が出来る人が農村のアントレプレナーとなる。
――地域では行政の存在は外せない。地方自治体はどうすべきか。
私は以前、千葉県のグリーン・ツーリズムの担い手育成講座に携わっていた。同県ではグリーン・ブルーツーリズムと呼んでおり、人材育成のプログラムを十数年行っていた。ネットワークの中で人を作る方向性が一番良いが、ただネットワークを作れと言われてもなかなかできない。補助金が付くと一時的に人がやってくるが、補助金が終わると金の切れ目が縁の切れ目となる。補助金を付けて支援をしても自立できないことは繰り返されており、農泊に携わる人の自立については、農水省の評価委員会でも必ず論点になる。今後は、支援を通じて、デジタル化への対応のほか、プロモーションやメニューの開発、人材育成を行う組織を多く作らなければならない。正しく活動やサービスを提供することができて初めて、自分たちの収益を確保し、再生産が図れることにつながる。
コミュニティベースの組織としては、観光分野では観光地域づくり法人(DMO)があるが、農泊も基本的に必要なコミュニティベースの組織はDMOと同様である。また、各地域には組織を会社組織化し、最初から自立化を目指すDMC(Destination Management Company)が出てきており、その活動には期待している。すぐに、全ての組織が自立して、収益性が確保できるとは思わないが、試行錯誤しながら前に進めようとしている事実があり、そのような人たちの経験をできるだけシェアすれば、農泊は加速度的に進むはずだ。
――各地域では地域資源の洗い出し、ターゲットの設定、プログラムや食の開発などすべきことはたくさんある。どう考えるべきか。
地域の人たちが、自分たちの強みを、とことん議論しなければならない。例えば、私のゼミで行う卒論では、何をやるということから始めるが、何をやりたいかという問題意識をすごく大切にしている。考え方をシェアし、同じ方向を見ないと、いくら私がアドバイスしてもちぐはぐなものになってしまう。そこがうまくできるかどうかは、しっかりと議論をしているかどうかであり、避けてはならない。
農泊も全く同じであり、何かクリエイティブなことをしようとした時、大事なことは、どこを目指したいのかということで、それを互いにシェアできるかということ。目指すところが分かれば、どう取り組むかは皆が考えるようになる。今は、行政と現場の考えがずれているような気がする。そうなると、いくら旗を振っても誰も始めようとしないし、始めても続かない。自分が何をやりたいか、どう組み立てて自立的に運営するのか、そしてどういう農村の未来像を描いているのかを、しっかりと議論する必要がある。議論を重ねた結果、皆が腹落ちしたところで合意ができ、同じ方向が見られることとなる。これは、組織の力に直結してくる。最初に何をしたいかについての議論には、しっかりと時間を掛けてほしい。
――日本人は議論が苦手な傾向にある。一歩踏み込む勇気、嫌われる勇気が必要か。
ある程度必要だ。先日に農水省の評価事業で、秋田県仙北市に行っていたが、仙北市と岩手県釜石市、群馬県みなかみ町といった地域の運営組織のメンバーが、農村ツーリズムのDMOとして連合を作りながらイベントなどをしていた。現場を拝見したが、正面からぶつかり合いながら議論をしていた。仲が悪いということではなく、一緒の方向に進むために真剣な議論を交わしていた。意見を交わし、議論し尽くした後は、次にどういうステップを踏むかなどPDCAの回し方まで、しっかり話し合われるという有益な時間だった。
よく町村では集落ベースで物事を進めようとするが、やりたい人が出てこないほか、高齢化で担い手がいないという場合が良くある。全てを集落で完結する必要はない。やりたい人も、全部を引き受ける必要はなく、支援をもらう、連携をするなど、そういうところからスタートして良い。また、一つ進むとフィードバックが生まれ、良い評価を得た際には自身を含めて地域の自信につながる。ここがうまくいくと、次の新しい活動へとつながっていく。
――農泊の成功事例や、失敗事例について。
農水省では、これまでの多くの事例を持つ。一番成功している地域を到達点として見なくていい。到達点が高すぎると気後れする。成功事例を少し砕きながら、段階的にステップを踏むスモールスタートの形からでも取り組んでみてほしい。今、何もやらない選択をしては、町村がジリ貧になることは確かだ。
個別でできる人はいいが、コミュニティベースで取り組むとなると、地域のマネジメントをある程度行う組織があると心強い。農水省は、イタリアで始まった、分散型宿泊施設の考え方であるアルベルゴ・ディフーゾの日本モデルを作ろうとしていたが、アルベルゴ・ディフーゾの考え方は、集落ベースの活動と似ているものがある。やはり、分散型でできることをやるということは、エントリーモデルとしてもやりやすい。山梨県小菅村など、いくつかの先進事例がある。
行政においては、組織に優秀な人を送り込んでも、数年で異動となる。ある県では、出向で入った人が優秀だったが、皆がその人に頼りきりになり、後の人が育たないということがあった。立ち上げの際に人材で支援することは良いが、それをどこまでやるか、異動後の人材を作ることまで考えてほしい。
このほか、モデル地域となるも、高齢化で人が抜けて活動自体が衰退したという事例もある。人材のバトンタッチができなかったことが基本的な原因だが、こういうことはどこにでも起こりうること。一時は優良事例であっても、人間は生き物で老いていくものであり、活動で生まれたしがらみなども乗り越えて、次の世代にどうつなげていくかは考えなければならない。
――第三者の力について。
外の血を入れることも考えて良いが、根付かない場合がある。外から人を迎える地域は、外から来たいという人の定着までを視野に入れた活動も併せて必要だ。
――農泊を実施するに当たり、意識してほしいことは。
ニーズに合った受け入れ環境整備は大切だ。今の時代ではIT関連の整備は必須だ。田舎に来た数日ぐらいシャットアウトしても良いとも思うが、ネットにつながっていないと不安に感じる人が多い。また、風呂場やトイレが汚かったり、食事を提供するにしても、ごはんをてんこ盛り、冷凍のままの刺し身を提供しているところも過去には経験したことがある。ホスピタリティビジネスだという意識を持ってもらいたいし、無理をせず暖かい農村のホスピタリティの在り方についても真剣に議論する必要がある。
ターゲットについても、団体、インバウンド、家族、カップルなのかを考えなければならない。これからインバウンドが増えることを考えると、家族やカップルなど少人数グループが増えてくることが予想され、少人数に対応できるハード整備が必要になる。今までは、田舎の空き部屋で良かったかもしれないが、それを小さくする工事が必要で、プライバシーを尊重できるホスピタリティも考えた設計が求められる。
今は、自分がどういう人たちが交流するのか、したいのかを明確にしなければならない。
――今後、農泊はどう進んでいくのか。
難しい問題もあるが、目指すべきところは、若い人たちが自立して農泊のビジネスを行い、家族と生活ができること。そのためには、そのために必要な所得を上げることが大事になる。結局、農村ツーリズムは、ホスピタリティビジネスであるし、ライフスタイルビジネスとも言われる。経営者が、自分のライフスタイルをどう描いているかということがビジネスに表れる。農泊が、自分たちのライフスタイルをそこで実現してもらう活動になればいい。
そのような中、国が言うインバウンドの受け入れなども視野に入ってくるが、ただそれを絶対に行わなければならないとかではなく、自分がどれだけ関わりを持っていきたいのかという自分の気持ちが大事なので、日本人だけを対象にしてもいいし、欧米の人だと敷居が高そうだから、とりあえずアジアの人からでもいい。 日本の農村は美しい。私も海外の友人の研究者たちが日本に来た際に案内をしたときに彼らは異口同音に日本の農村が奇麗だと言ってくれる。最初はお世辞かなとも思ったが、実際に向こうに行くと、彼らが同僚や学生に同じことを言うので、本気だと思うようになった。やはり、日本の農村の魅力は伝わるものであるし、ポテンシャルは非常に高い。ポテンシャルを開花できるように、農泊事業を活用して皆が知恵を出しながら取り組んでほしい。
大江靖雄(おおえ・やすお)東京農業大学 国際食料情報学部 教授。北海道職員、農林水産省北海道農業試験場研究員および中国農業試験場農村システム研究室長、千葉大学大学院園芸学研究科教授を経て、2020年4月から東京農業大学国際食料情報学部国際バイオビジネス学科教授。研究テーマは、農業と農村の新たな役割を明らかにするため、農村ツーリズムを対象に国内およびイタリアをはじめ海外との比較研究をミクロ経済学と計量経済学で理論的・実証的研究を行っている。現在、日本観光学会会長, Asia Pacific Tourism Association 理事、Tourism Economics誌editorial board member。
聞き手 TMS編集部 長木利通