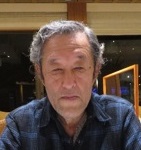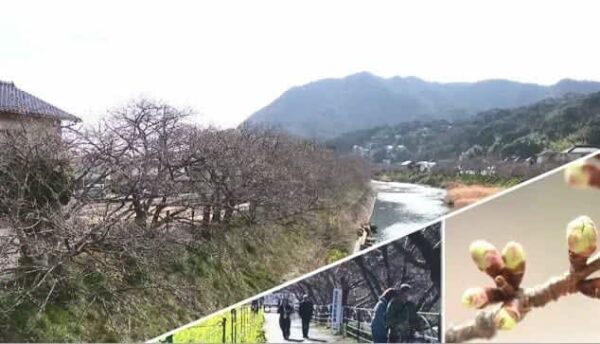京の町なかを歩きながら興味深い写真の新しい息吹に触れる。日本最大規模の写真展、KYOTOGRAPHIE(キョウトグラフィー)京都国際写真祭が4月12日から5月11日まで30日間、京都市内の町家や美術館など13会場で開かれる。東日本大震災2年後の2013年に始まって今年13回目。昨年まで延べ210 万人を超す来場があり、2024年の27万人の15%増の来場者を見込む。
今年は古都千年の伝統を守り続ける寺や町家などの歴史的な建築空間に先端文化を担う多数の写真作品群を展開する。建築家やグラフィックデザイナーが協力し、工芸職人や先進技術の企業を結び、建築と写真の調和と共存が興味を呼ぶ。
主な会場は昨年に続き京都文化博物館別館、京都市美術館別館、祇園南の建仁寺(けんにんじ)塔頭の両足院、烏丸御池周辺にある町家・八竹庵(はちくあん、旧川崎家住宅)、嶋臺(しまだい)ギャラリー、帯匠の誉田屋(こんだや)源兵衛竹院の間、くろちく万蔵(まくら)ビル、ギャラリー素形(すがた)などのほか、御所北側の出町枡形(ますがた)商店街、祇園のアートギャラリーASPHODEL(アスフォデル)、京都駅ビル北側通路壁面、京都新聞ビル地下1階の印刷工場跡など多彩だ。

第2回開催から毎年、写真祭全体のテーマを掲げてる。14年はOur Environments私たちを取り巻く環境。15年はTRIBE。直訳は部族、集団などだが、この写真祭は和文で「あなたはどこにいるのか」と興味深いテーマを掲げた。16年はCircle of Life、つまり「いのちの環」。17年はLOVE、次いでUP、VIBE、VISION、ECHO、ONE、BORDERと続き、昨年はSOURCE。そして今年のテーマはHUMANITYだ。写真祭は和訳を出していないが、LOVEから順に、愛、上へ、共振、意識、呼応、個、境界線、源、そして今年は人間性とでもイメージを構成できるだろうか。

公表されたプレス資料の冒頭で「私たちは個人として、世界の一員として、どう生きるのか」と基本的な問題を投げかけ、HUMANITYは「愛の力や共感力、危機を乗り越える力にまなざしを向けながら、日本と西洋という2つの異なる文化的視点を通じて人間の営みの複雑さを浮かび上がらせる」という。そして「写真の力を通じ、人間性とは何かをともに探し求めることが、他者への理解の一助となり、この混沌とした世界において自らがすべきことを共有するきっかけとなること」を掲げる。
参加アーティストは10か国から13組14名の予定。インドのプシュパマラ・N、フランス出身の作家JR、メキシコシティ生まれのグラシエラ・イトゥルビデ、ファッション・映画・文学の領域でも活動するアーティストのレティシア・キイ。さらにフランスの現代写真界を代表するエリック・ポワトヴァン、イギリスの写真家・映像作家・コレクターのマーティン・パー、アイルランドのアーティスト(音楽制作・写真家)イーモン・ドイル、パレスティナ系アメリカ人のアダム・ルハナ、ユニットとして出展するパリ在住映像作家のリー・シュルマンとセネガル出身写真家オマー・ヴィクター・ディオプ。
アジアは台湾から劉星佑(リュウ・セイユウ)。沖縄県大宜味村(おおぎみそん)生まれの石川真生(まお)は、1970年代後半に黒人兵が集まるバーで働きながら沖縄社会や男女の恋愛模様を収めた作品と離島で撮影中の最新作を誉田屋で展示。コマーシャル写真家としても活躍する𠮷田多麻希(たまき)は身近な自然や生き物と人の関係を問いかけるイメージを発表、写真専門学校出身で伊奈信男賞など受賞した甲斐啓二郎は、世界各地の格闘的な伝統の祭りに肉薄し人間の生を本質的に問う作品を、くろちく万蔵の空間に展開するという。=この項、敬称略=

KYOTOGRAPHIEは大きな美術館や企業が始めたのではない。2人のアーティストの発想と献身的な努力から生まれ育った。パートナーで共同代表の写真家ルシール・レイボーズさんと照明家・仲西祐介さんは東日本大震災を機に京都へ移住、2人でイベント実現を思い立った。
大震災と原発事故で一極集中の危うさを実感し、東京を経由しない発信に重きを置く。京都で暮らし始めたとき、まずは自転車で街を走り回り、毎日新しい優れものを発見し、国際的な魅力と人びとが生きる本質的な存在を共に持ち合わせる理想的な環境にいることを改めて感じ、時を超えたこの街に驚いた。日本の伝統を保ち、海外の人気も高い寺社や町家、茶屋、商店などのスペースを活かして国内外の写真家やアーティストたちの作品を並べてみたら、と具体的なプランを進めた。 従来型の大きな美術館で開く展覧会と趣を異にし、フランスのアルル国際写真フェスティバルのように、会場を巡ると街の歴史と新しい進化を同時に感じ取れる、そんな時間と空間の旅へ楽しみと興味を広げ誘う。日本と海外の写真、昔と現代の写真を集め、写真が多くの人びとの手に届き、生活の中に溶け込むフェスティバルに育てる思いで回を重ねて来た。
コロナ禍で大きな影響を受け、桜の季節の開催が2年間秋開催に余儀なくされたこともあった。会期や会場変更の出費増、スポンサーの撤退、縮小もあり、資金難に見舞われ、クラウドファンディング(ネット型資金調達)で目標を超す1千万円規模の寄付を得た。
また、学校閉鎖が続く中、「子ども写真コンクール」を企画して国内外へ発信し、未来の写真家の育成にも力を入れ、家族で写真を学ぶ参加型のイベントを育む。日本の撮影・印刷技術は世界的にハイレベルだが、独創的な日本の写真家は海外での評価が先行する傾向があり、それを克服して日本の表現レベルを世界に発信することも目標の一つだ。葵祭や祇園祭などと並ぶ年中行事になるよう京都発信の夢はふくらむ。

2013年の第1回からKYOTOGRAPHIEと同じ日程で同時開催している「KG+」は、活躍が期待される写真家やキュレーターを発掘し支援することを目的とした公募型アートフェスティバルだ。昨年は125の展覧会があった。会期中は写真集のブックフェアや関連ワークショップ、トークイベントなど市民参加型のプログラムが市内各所で実施される。応募の中から10組のアーティストが選ばれ展示制作補助金20万円が支給される。グランプリは補助が50万円となり次年度KYOTOGRAPHIEのメインプログラムとして展覧会が組み込まれる。今年メインに出展の劉星佑さんは昨年のグランプリだ。さらに関連するプログラムにKyOtOmAsOn MArAthOn!(京トマソン マラソン!)という凝ったタイトルの展示もある。前衛美術家の赤瀬川原平らが繰り広げた路上観察や街なかで発見した不思議な造作物などの写真展示だ。
写真祭の姉妹イベントとして国際音楽フェスティバルのKYOTOPHONIE(キョウトフォニー)も2年前の2023年から始まった。調和、多様性、交流、探求といったキーワードを核に、内外から多様な世界的アーティストを招き、今年もKYOTOGRAPHIE会期中にいくつもの公演を計画する。いまの時代、写真も音楽もデータ化されオンラインのやり取りが加速される世情の中で、素直に写真を見たり音楽を聴いたり「心を震わせる人間的な感覚が失われていくのではないかと危惧しています」「感覚的体験の機会を多くの人と共有したい」と共同代表の2人は切なる願いを語る。
KYOTOGRAPHIE本展の観賞入場料は、全13会場を会期中に1回ずつ観覧できるパスポートチケットが一般6,000円(前売り5,500円)、学生3,000円(前売りも同額)、会場ごとは一般600円~1,500円で、一部会場は無料。