〝地域間交流拡大〟を強力に推し進め、地域の活性化に向けた課題解決に取り組む地域連携研究所(濵田健一郎理事長)は11月22日、「第7回地域連携研究所大会 in 信州まつもと」を長野県松本市のホテルブエナビスタで開いた。全国から自治体、企業、金融機関、大学、文化団体など約290人が集い、人口減少下での持続可能な産業創出、歴史文化資源の観光活用、官民協働の地域戦略、広域連携、人材育成など、多岐にわたるテーマについて議論を深めた。北前船フォーラムと連動した松本開催により、〝海と山をつなぐ地域間連携〟という新たな視点が示され、地域の枠を越えた協働の可能性がいっそう明確になった。
大会では、企業経営者、政策担当者、文化・アニメーション分野の専門家、人材育成機関などが最新の取り組みや知見を共有し、今後の地域振興の方向性や広域連携の具体像を多角的に検討した。さらに、会員企業・団体によるふるさと納税の成果、伝統工芸の海外発信、地域イベントの再構築、交流人口拡大策などの報告から、地域振興の実践知を学んだ。
地域を越えて集う「学びと連携の場」
大会は冒頭、同大会が掲げる「地域間交流拡大」の理念が共有され、海・山・都市をつなぐ自治体、企業、金融機関、大学、文化団体など多様な参加者が松本に集う意義が示された。単に講演会ではなく、地域が抱える課題や強みを持ち寄り、互いの経験を照らし合わせながら新たな協働の形を探る〝実践の場〟として位置付けられており、そうした趣旨のもとで大会が幕を開けた。
続いて、主催者を代表して北前船交流拡大機構専務理事の浅見茂氏が登壇。浅見氏は全国からの多く参集した参加者を紹介しながら、この1年間の活動を振り返り、「地域課題は、もはや単独の自治体や企業だけでは解決できない。地域間の知見を交換し、民間・行政・市民が同じテーブルにつくことで、初めて解決の糸口が見える」と述べ、地域連携研究所の役割と使命を改めて示した。また、松本市を舞台に北前船フォーラムと連動して開催された今回の大会について、「歴史文化が重層する松本で議論する意義は大きい。地域が持つ原点を掘り起こし、未来につなぐ契機にしたい」と語った。

広域連携が地域の未来を拓く
歓迎あいさつにはまず、長野県副知事の関昇一郎氏が登壇。関氏は、地域連携研究所の立ち上げ以降の歩みに触れ、各地の首長が積極的に参画してきた歴史を紹介しながら、「市町村長が元気な地域は、地域全体も必ず元気になる」と語り、地域間連携の重要性を強調した。今回の大会が北前船フォーラムと連動し、初めて内陸の地・信州で開催されたことに触れ、「開催地の広がりそのものが、地域連携研究所が掲げる理念の具体化であり、地域が新たなステージへ歩み出している証し」と述べ、感慨を示した。
また、長野県が進める広域連携の取り組みとして、新潟・山梨・静岡と災害バックアップ体制を協議する枠組み、リニア中央新幹線沿線での協働など、地理的・産業的な結びつきを踏まえた連携事例を紹介。さらに、海と山という対照的な環境をもつ沖縄県との包括連携協定にも触れ、双方の文化や産業を補完し合う新しい形の交流が生まれつつあると語った。最後に、「人と人がつながり、知恵と力を持ち寄ることでローカル同士の関係は必ず深まる。そこから地域の未来が開けていく」と述べ、歓迎の辞を結んだ。

松本が示す「学びと連携の舞台」としての可能性
続いて登壇したのは、開催地を代表する松本市長の臥雲義尚氏。臥雲氏はまず、北海道から沖縄まで全国から多くの参加者が訪れ、3日間にわたりフォーラムとレセプションが行われたことに深い謝意を示し、「この大会は地域と地域をつなぎ、ローカルからローカル、そしてローカルから世界へとつながりを広げる場だ」と述べ、研究所大会の意義を改めて強調した。
今回、北前船フォーラムが初めて内陸都市である松本で開催されたことについては、「北前船の歴史に縛られない、より広い連携を探る舞台として松本が選ばれたことは象徴的」と語り、地域連携研究所の活動が進化しつつあることを示唆した。また、松本が持つ文化的背景にも触れ、「澄み切った青空や北アルプスを背にした松本城の姿など、この地ならではの風土を感じていただけたのではないか」と述べ、自然と歴史が育んできた松本の魅力を参加者へ紹介した。さらに、地域創生の議論に期待を寄せ、「今日の研究発表や意見交換を通じ、皆様が抱える課題の解決に向けたヒントを持ち帰ってほしい。松本での学びが各地域で新たな連携を生み、次の一歩につながり、大きな輪となることを願っている」と語り、歓迎のあいさつを締めくくった。

多様性こそ日本の力、地域連携が未来を拓く
主催者あいさつのトップとして登壇したのは、地域連携研究所自治体会員会長を務める衆議院議員の福原淳嗣氏。福原氏はまず、開催地である松本市に祝意を述べた上で、地域連携研究所の誕生がコロナ禍という困難な時期にあったことを振り返り、「地域を元気にする情熱と行動力が問われている」と語った。
さらに、地域多様性は日本の国力の源泉であり、その力を観光の側面から最大限引き出すことこそが政治の役割であると強調。国際観光旅客税の増額議論や、地方税源の見直しなど国の動きにも触れ、「地方の連携を進める自治体こそ、財源がきちんと行き渡るべきだ」と述べ、地域間連携の意義を国政の視点から提示した。「立場は変わっても、地方から日本を元気にする思いは変わらない」と語り、地域連携研究所のさらなる発展に期待を寄せた。

歴史と文化をつなぎ、新たな連携軸を紡ぐ
続いてあいさつしたのは、共同会長を務める岡山県岡山市の大森雅夫氏。大森氏は、北前船フォーラムが始まった当初は参加自治体も少なく、小さな会場でのレセプションからスタートしたことを思い返しながら、今日において北海道から沖縄まで全国の自治体が集結する姿を「まさに北前船が紡いだ連携の広がり」と表現した。
北前船フォーラムの講演で言及された古代史の話題に触れ、岡山の巨大古墳「造山古墳」や、古代吉備の文化が全国とつながりを持って発展した歴史を例示。「古代から連携は日本の営みの本質にあった。現代の地域連携は、その延長線上にある」と述べ、文化資源を軸にした広域連携の可能性を示した。「地域が手を取り合うことは、日本にとって必要不可欠。研究所活動をさらに大きな輪へと広げたい」と語り、今後の期待を込めてあいさつを締めくくった。

「地域連携の具体化」が動き始めている
観光庁元長官で特別顧問である田端浩氏は、研究所の発足時を振り返りながら、「コロナ禍の真っただ中で始まった取り組みが、7回目を迎え、今や具体的な広域連携として動き始めている」と感慨を述べた。
田端氏は、自治体同士の共同プロジェクトの可能性として、白神山地のような県境をまたぐ自然資源の活用、ふるさと納税ノウハウの共有、アニメツーリズムや伝統工芸の海外発信など、これまで自身が関わってきた連携事例を紹介。「文化・観光・産業を越境して結びつける広域リージョン連携は、まさに研究所が目指す方向性そのもの」と強調した。今後の会員拡大への意欲も示し、「地域連携研究所の活動がさらに力強く進むよう全力で支えていきたい」と述べ、あいさつを結んだ。

地方創生と北前船、伝統工芸をいかに世界へ届けるか
第1部のテーマは「地方創生と北前船について」。かつて日本海側の諸都市を結び、物資と人、そして文化を運んだ北前船は、いま再び「地域をつなぐネットワーク」の象徴として注目を集めている。人口減少や後継者不足が深刻化する中で、各地に残る伝統工芸やものづくりをどのように高付加価値化し、世界市場へと押し出していくのか。北前船ネットワークが持つ潜在力と、工芸を核とした地域振興の可能性について、国や民間の視点から語られた。

「土産物からアートへ」欧州富裕層市場を見据えた工芸戦略
最初に登壇したのは、伝統工芸品の海外展開を国会でも一貫して提起してきた参議院議員の横山信一氏である。 横山氏は、インバウンド増加により地方が世界から注目される一方で、和食やアニメに比べ、伝統工芸が十分に光を浴びてこなかった現状に言及した。経済産業省の伝統的工芸品指定制度や支援事業は整備されつつあるものの、「広域的な物語として発信する仕組みが弱く、個別産地の努力が世界市場へとつながりにくい」と課題を指摘した。特に、和食と器・盆・箸といった工芸品を「一体の文化」として扱う視点が不可欠だとし、北前船ネットワークが備前焼などの工芸産地と連携してきた例を挙げ、「面的な発信こそが次の突破口になる」と強調した。
横山氏が特に言及したのが、欧州富裕層の資産形成における「アート投資」の慣行である。富裕層が集まるアートフェアに伝統工芸を位置づけるためには、作品を扱うギャラリーとの接続が不可欠だが、「国の支援はプロモーションで終わり、フェアやギャラリーと結びつける最後の一手が不足している」と課題を語った。これを受け、横山氏は参院予算委員会で高市総理に対し、伝統工芸の高付加価値化と海外展開を政府の地域未来戦略本部で推進するよう求めた。総理からは欧州富裕層向け展示支援や販路開拓の強化が示され、「アートフェアへのアクセスを国の方針に明確に位置づけた意義は大きい」とした。
最後に横山氏は、「伝統工芸が世界で評価されれば地方創生に直結する。北前船が担った広域連携の精神を、現代の工芸・アートの文脈に読み替えていくことが重要だ」と述べ、国と民間の協働による継続的な支援の必要性を語った。

工芸の価値を「仕組み」で支える金融グループの挑戦
続いて登壇した三菱UFJファイナンシャル・グループ経営企画部ブランド戦略グループ部長の飾森亜樹子氏は、同グループが社会貢献活動の重点領域に「文化の保全と伝承」を掲げ、約2年半前から伝統工芸支援を進めてきた経緯を紹介した。「伝統と革新」「文化と産業」「ものづくりの根幹」を軸に、工芸を地域産業として捉え直す姿勢を示し、大阪・関西万博や愛知のアリーナ展示、来年名称を冠する「MUFGスタジアム」などを文化発信の拠点として活用する取り組みを説明した。また、パリの日仏フォーラムやニューヨークでのイベント、大相撲ロンドン場所での輪島塗提供など、海外での発信事例も紹介した。
若手支援では「KOGEI ARTISTS LEAGUE」を立ち上げ、一流作家による指導と日本橋三越での販売機会を組み合わせた仕組みを整備。初年度は約80名が応募し、ファイナリスト作品の多くが完売するなど成果があったという。素材・道具の供給難にも着目し、日経新聞連載で課題の可視化を進めるほか、SNSや「日経ウーマン」と連携し、生活者が工芸を日常に取り入れる提案にも取り組んでいる。
社内では全国の支店が地元工房を訪問し、選んだ工芸品を応接室で使用・展示する活動を展開。「社員が背景を語れることが文化支援の基盤」と飾森氏は述べた。今年からは、ものづくりを軸とした地域活性化プラットフォーム「工芸コモンズ」を始動し、福井県鯖江市のオープンファクトリー「RENEW」と連携して全国産地の学び合いの場を創出。「単発でなく継続的な仕組みに広げていくことが重要」と語り、北前船が象徴した地域連携の精神を現代の工芸支援に継承する姿勢を示した。

地方が東京を介さず「世界と直結する」ための現実的ルート
第1部の議論を受け、地方と世界の接続を阻む〝見えない壁〟について最も構造的な視点を提示したのが、財務省大臣官房企画官の二宮悦郎氏である。二宮氏は外務省EU日本政府代表部勤務時、北前船フォーラムのパリ大会で受けた衝撃を「問題意識が一変した瞬間」と振り返る。地方が誇る工芸が国の政策体系の中で十分に扱われず、所管省庁すら定まらないまま埋もれている現実に直面し、「食や酒に偏った地域施策では文化的価値を産業化しきれない」と捉えた。備前焼や大島紬をはじめ各地に残る高度な技術が、国内外で適切な評価に結び付いていない状況を目の当たりにし、「これは日本の産業構造そのものが抱える深層の課題だ」と位置付けた。
特に二宮氏が強調したのは、世界の富裕層が集まるアートフェアの存在である。欧州の人々の日本文化への関心が高いにもかかわらず、スイス・バーゼルやロンドンでの著名なアートフェアでは、日本の工芸の姿はほとんど見えてこないという。国内で日用品としての価格帯にとどまっている工芸品は、国際アート市場ではその低すぎる価格設定のために競争の俎上に載りにくい。だが一方で、ジャポニズム以降に続く〝供給の空白〟が希少性を高めており、適切な見せ方や市場への導線を整えれば、評価が立ち上がる余地は十分にある。北前船チームが備前焼作家をアートフェアへ橋渡しし、現地でトップページ扱い・完売につながった事例を挙げ、「日本側が市場構造を理解し、適切な回路に乗せれば必ず成果につながる」と述べた。
ただ、国内の行政・自治体などは依然として「やり方が分からない」状態に置かれ、企画会社への丸投げによって海外の実務プレーヤーと接続しない例が多いと指摘する。本来は、先に海外バイヤーやギャラリーを押さえ、そこから逆算して設計を行うべきであり、北前船のネットワークはその正しい順番を提示しつつあると評価した。また、京都で実施された〝食・工芸・アート〟を統合した富裕層向けイベントを例に挙げ、「日本の強みは総合芸術として提示したときに初めて国際価値が立ち上がる」と語る。最後に、地方案件が本社機能で埋もれがちな日本経済の構造にも触れつつ、「地方が主体となって世界と直接つながるモデルを北前船が具体化しつつある」と述べ、「第二のジャポニズムをともに創りたい」と締めくくった。

地方発の工芸を「世界市場で売れる形」に、独自展示で販路開拓に挑む
第1部の締めくくりとして登壇したのは、ANA総合研究所取締役副社長であり、北前船交流拡大機構の理事長代行を務める森健明氏である。森氏は、地域連携研究所が観光・産業・文化を軸に地域振興メニューを積み重ねてきた経緯を踏まえ、「観光から工芸ツーリズム、そして工芸そのものの海外展開へと事業領域は着実に広がっている」と指摘。今回採択された内閣府の実証事業もその延長線上にあり、「地域の手仕事を世界市場へつなぐ具体的な挑戦だ」と述べた。
森氏が紹介したのは、2026年1月下旬に予定するイタリア・ミラノにおけるADIデザインミュージアムでの独自展示の取り組みである。一般的なアートフェアへの出展とは異なり、あえて既存の入れ物に依存せず、同館のスペースを活用して単独展を組成する方針だ。秋田・角館の樺細工、新潟・佐渡の無名異焼、石川・輪島の輪島塗、岡山・備前の備前焼といった産地から、国内価格100〜200万円級、海外市場では1000万円規模に達する高級作品を選抜し、ミラノの富裕層をターゲットにピンポイントで招致する。森氏は「富裕層の視界に入らなければ価値は立ち上がらない」と述べ、茶筒16個を連作のアート作品として展示するなど、クラフトをアートへ昇華させる見せ方に重点を置く考えを示した。
さらに森氏は、震災後の輪島では多くの作品が「作家の押し入れに眠ったまま」になっている現実に触れ、「展示されなければ価値は生まれず、売れなければ復興につながらない」と指摘した。北前船ネットワークは、自治体が加盟する強みを生かして埋もれた作品・作家を発掘し、世界につなぐ独自の仕組みを持つという。また、海外実務に精通したパートナー企業や三菱UFJ、読売新聞の文化支援を挙げ、「民間の力を束ねてこそ販路が開ける」と強調。アルザス日本学研究所との欧州連携や2027年開館予定の漫画ミュージアムとの協働など、工芸からアニメまで射程に入れた展開も紹介し、「地域の財を次の市場へ運ぶ挑戦をともに広げたい」と呼びかけた。

アニメーション産業の現在地と地域社会への展開可能性
第2部では、国際展開が加速する日本のアニメーション産業をテーマに、政策・産業・教育の三つの視点から特別講演が行われた。国際的な需要の高まりとともに、地域社会とアニメ文化をどう接続し、持続的な産業基盤をつくるのか。アニメ政策を所管する国会議員、アニメ文化の発信を担う企業、そして新たなアニメ人材育成に挑む教育機関がそれぞれの立場から可能性を語った。
若者の挑戦と「攻めの農業」が地域を動かす新たな力に
第2部の冒頭では、衆議院議員の齋藤健氏が登壇し、地域活性化を考えるうえで「農業」と「若者」が鍵になると問題提起した。齋藤氏は、2011年に香港でおにぎり専門店を立ち上げ、現在150店舗超に成長させた日本人青年2人の事例を紹介。日本産米や海苔にこだわり、海外需要を自ら切り開いた姿勢を「日本農業が成長産業へ転じるモデルケース」と評価した。人口減少で国内市場が縮小するなか、「海外を見据えた攻めの農業こそが地域再生の突破口になる」と強調した。
講演では、日本のコンテンツ産業が海外で年間5.8兆円を稼ぐ一方、韓国や中国が急速に追い上げている現状にも触れ、「農業もコンテンツも、国内需要だけに依存していては未来は開けない。外へ出る主体が必要だ」と指摘。農産物の品質は世界トップであるにもかかわらず、売り込むためのマーケティングが不足しているとし、キッコーマンや自動車産業が海外で地道な“売り歩き”を行ってきた歴史を引き合いに「農業にも同じ発想が必要だ」と訴えた。
さらに齋藤氏は、若者の挑戦を抑えつける風土や英語力の壁が潜在力を阻んでいるとしつつ、生成AIの普及で海外挑戦が身近になると期待を示した。一方で、地方の書店が急速に消滅している現状を「文化インフラの危機」と位置づけ、全国市町村の約3割が書店ゼロである実態に強い危機感を示した。「本屋は視野を広げる装置であり、図書館やネットでは代替できない」と述べ、議員連盟として推進する「一村一書店運動」への理解を求めた。最後に「若者の挑戦を支え、外国市場を開拓する環境づくりこそが地域の未来を拓く」と語り、会場に新たな視点を提示した。

地域文化を「物語」として世界へ、アニメが拓く新たな地域戦略
続いて、角川文化振興財団の角川歴彦氏とアニメ制作会社Rocket Base LLCの水野寛氏が登壇し、日本のアニメ・マンガ産業が世界市場で果たす役割と、地域文化との接続可能性について議論が展開された。角川氏はまず、近年のアニメ市場の急拡大を俯瞰しながら、「世界に通用する作品の背後には、必ず固有の文化的背景がある」と指摘。単なる娯楽コンテンツではなく、地域に根づいてきた歴史や祭礼、工芸、食文化など、多層的な文化資源が物語の源泉として作品価値を高めていると述べた。そのうえで、「地域の文化をアニメが読み替え、再編集し、世界へ届ける。これは観光誘客以上の意味を持つ」と強調した。

水野氏は、制作現場から見た環境変化を示した。配信プラットフォームの国際展開が進んだことで、地方の小規模スタジオでも海外の視聴者へ直接コンテンツを届けられる時代になったという。さらに、自治体や地域企業が作品企画段階から参加する「地域協働型IP創出」の事例が増えている点を紹介し、作品そのものが地域の人材育成や産業育成につながると説明。「ロケーションを提供するだけの時代は終わった。地域が共に作品をつくり、著作権や収益にも関与するモデルを確立すべきだ」とし、持続可能な地域IP戦略の重要性を訴えた。
両氏は、アニメが地域に眠る文化資源を世界基準の表現へと昇華させる可能性について意見を一致させた。角川氏は「アニメは、地域文化を一つの世界観として再構築する力を持つ」と述べ、水野氏は「地域が主体的に関わり、作り手と一緒に物語を編むプロセスこそが、新しい地域産業を生む」と応じた。工芸・食・景観・祭礼といった要素を横断しながら文化価値を再定義し、世界へ届ける〝総合文化戦略〟としてアニメを位置付ける視点が提示され、会場には大きな関心が広がった。

八ヶ岳から始まる「稼げる農業」への転換
第2部の最後に登壇したのは、八ヶ岳農業大学校理事長であり、ビズリーチ創業者としても知られる南荘一郎氏が登壇し、再建に取り組む同大学校の現状と未来像を語った。冒頭、南氏は自身がカナダやインドで育った経験、そして新市場開拓を実践した父の背中を見て育ったことを紹介し、「価値あるものは国境を越えれば必ず評価される」という原体験が再建の基盤にあると説明。破綻状態にあった同校の実態に触れつつ、「日本の農業や自然資源は過小評価されている。仕組みを変えれば必ず再生できる」と語った。
再建の核として南氏が掲げたのは、「稼げる農業」への全面転換である。従来は教職員や学生の作りたい作物に依存していた生産計画を、マーケットからの逆算へと刷新。酪農・養鶏・野菜栽培に加え、長らく休止していた加工施設を再稼働し、チーズやソフトクリームの製造販売も再開した。さらに、直売所を地域と連携して立て直すなど、販売現場を教育に取り込む体制を整備。「いいものを作れば売れる時代は終わった。数字と市場を理解した農業人材を育てる」と強調した。また、富良野や浜松フラワーパークを参考に、サルビアを皮切りとした〝花による集客事業〟を始動。地域の文化資源を活かしつつ、八ヶ岳ブランドのファン形成を意識した新たな観光モデルづくりにも着手している。
教育機関としての再建も進む。学生数13人の小規模校ながら、年間1万人規模の小中学生が農業体験に訪れるまでに成長し、来年は1万2000人を見込む。さらに、南氏自身の原体験をもとに、森と湖の自然を舞台とした“アジア最大級の長期サマーキャンプ”を立ち上げ、200人規模の受け入れを実現した。「自然への没入体験が、次世代の価値観を育てる」と語り、農業・教育・観光を統合した新しい地域モデルの創出を掲げた。最後には、企業・個人が学校へ直接寄付できる新しいふるさと納税スキームを紹介し、「農業と地方には未来がある。八ヶ岳からそのロールモデルを示したい」と結んだ。

地域資源を結ぶ広域観光のこれから
第3部では、歴史ある街道や河川交通、そして果実菓子ブランドといった多様な地域資源を、広域観光や海外展開につなげる方策が語られた。国土交通省関東運輸局からは「江戸街道プロジェクト」を通じた広域ルート造成とインバウンド分散の戦略が示され、山形県中山町からは最上川舟運と北前船が育んだ芋煮文化を核としたまちづくりの歩みが紹介された。さらに老舗菓子メーカーは、果実栽培から国内外450店超の販売網まで一貫した取り組みと、新ブランドや乳業への挑戦を通じて地域発の価値創造を続ける姿を披露し、会場に「地域と世界をつなぐ仕組みづくり」のヒントを投げかけた。
広域連携で「江戸街道」を世界ブランドへ、新たなルート観光戦略
登壇した国土交通省関東運輸局長の藤田礼子氏は、五街道とその枝道を束ね、広域関東の観光振興を図る「江戸街道プロジェクト」の意義を改めて説明した。同プロジェクトは、江戸を起点とする街道文化を「関東一円の回遊ルート」という新たな文脈で再編集する行政主導の取組で、東京・神奈川・埼玉・栃木といった関東10都県に加え、長野・新潟・福島も連携対象に含む広域スキームが特徴だ。藤田氏は、自身がVISIT JAPANキャンペーンや震災復興観光を支えた経験に触れつつ、「街道は文化と移動をつなぐ物語の軸であり、多様な観光資源を一体的に束ねる最適なフレーム」と語り、宿場町の歴史情緒やアクセスの良さが国内外の旅行者にとって高い潜在価値を持つと指摘した。
プロジェクトは当初、認知向上や仲間づくりからスタートし、ロゴマーク開発、御宿場印プロジェクト、人材育成、文化体験プログラムの創出などを通じて、地域側の受け入れ基盤を段階的に整えてきた。藤田氏は「資源磨きの段階を越え、動く観光へと転換する時期に来た」と述べ、宮本亜門氏が演出した「OH!江戸東京まつり」をはじめ、江戸文化の発信と街道のイメージづくりを図る各種プロモーション事業を紹介。こうした取組によって街道沿いの魅力が可視化され、自治体・DMO・民間企業が連携する体制が整いつつあり、プロジェクトが本格的な誘客フェーズへ移行したと強調した。
さらに藤田氏は、来春から本格的に展開する海外向けプロモーションを「プロジェクトの飛躍フェーズ」と位置づけた。国外名称を「Edo Shogun Roads」に統一し、歴史文化を象徴するブランド力を強化。プロモーション動画やポータルサイト整備に加え、庭園・フラワー、酒蔵、温泉といったテーマ別モデルコースの発信、外国人インフルエンサーの招請、欧米・豪州での旅行博出展など、多層的な施策を展開する方針を示した。また、2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)を念頭に、庭園・花のルート造成を戦略的に強化している点にも触れ、「江戸文化とグリーンツーリズムの融合は、海外市場での新たな訴求軸になる」と説明。さらに、関東広域観光機構が職員・事業費ともに大幅に拡充され、活動体制が強化されていることを紹介し、「関東は世界市場で競争できる広域観光圏になり得る。自治体・DMOの積極的な参画が、街道ブランドを本物へと押し上げる」と呼び掛け、締めくくった。

最上川舟運と京文化を結ぶ「芋煮会発祥の地」としての歩み
登壇した地域連携研究所自治体会員代表で山形県中山町長の佐藤俊晴氏は、最上川舟運を通じて北前船文化が内陸へと波及した歴史に触れ、「中山町は寄港地ではないが、北前船との結節点として確かな文化交流の痕跡を持つ」と語り始めた。紅花交易、京都文化の流入、船頭たちの往来の記憶など、山形内陸に残る〝舟運文化圏〟としての独自性を紹介し、地理的には小規模な町でありながら、歴史資源の深さが地域文化を支えてきたと説明した。
象徴的な文化として、佐藤氏は「芋煮会発祥の地」とされる中山町のストーリーを詳述。船頭たちが到着時間を読めない舟運の待ち時間に、地元の里芋と航路で運ばれた大太郎を合わせて煮たことを起源とするという。当時の河原で鍋を吊った風景を動画で紹介し、「北前船が運んだ文化が、町の食文化として根付き、今や山形を代表する秋の風物詩へと発展した」と語った。昨年10月には“芋煮会の日”を記念日登録し、伝統を現代へ継承する取り組みも進む。
さらに佐藤氏は、紅花文化を伝える景観づくりや、歴史的建造物の保全、キャラクターを活用したPRなど、地域資源を活かす試みを紹介。「内陸の町にも北前船文化は確かに息づいている。こうした歴史を未来の力につなげていきたい」と述べ、会場に静かな共感を広げた。

源吉兆庵が挑むグローバル展開と多角化の経営モデル
最後に登壇した地域連携研究所企業会員代表で源吉兆庵ホールディングス執行役員の岡田圭子氏は、まずグループの全体像と事業基盤を紹介した。国内450店舗・海外41店舗(8カ国)を展開する同社は、和菓子製造から物流まで一貫体制を持つ稀有な企業であり、果実を中心とする菓子文化を軸に、京都・江戸・洋菓子など多様なブランドを育ててきた。「戦後の個人商店から始まった会社が、果実王国・岡山の強みを生かし、贈答文化を支える存在へと成長した」と述べ、創業から続く“果実を原点とする菓子づくり”へのこだわりを強調した。
続いて岡田氏は、1990年代から積極的に進めてきた海外戦略に言及した。シンガポール、ロンドン、台湾を皮切りに、現在はニューヨーク五番街に自社ビルを構え、店舗運営と文化発信の拠点として活用している。特に同ビルでは、日本クラブや商工会議所が入居し、日本文化の多目的ホールとしても機能。抹茶・和菓子・琴の演奏会、ひな祭り展示など、歳時記や工芸菓子を通じて“文化としての和菓子”を世界へ伝えている点を紹介した。また、原材料供給の不安定化に対応し、自社農園でマスカットや桃の栽培を進めるなど、サプライチェーン強化の取り組みも明らかにした。
さらに岡田氏は、需要変化への敏感な対応がグループ成長の鍵だと語った。コロナ期には贈答需要が急減したことで、日常消費を見据えた乳製品(ヨーグルト)事業を立ち上げ、2024年にはファミリー層向けの新ブランド「J.Sweets Harmony」を創設。価格帯・嗜好・購買動機の多様化に合わせ、和菓子だけに依存しない多角化を進めている点を示した。「失敗も挑戦もすべて次への資産。食文化を守りながら、新しい市場を切り拓く」と締めくくり、老舗でありながら変化に挑む企業姿勢を会場に印象付けた。

持続可能な連携モデル、北前船ネットワークを支える「会員制度」について
諸連絡の時間では、まず「北前船ネットワークの会員募集について」が取り上げられ、地方創生支援官の出口岳人氏が、制度の背景と意義を説明した。出口氏は、北前船が全国の自治体・企業を結ぶ稀有なプラットフォームになりつつあるとした上で、「地域の文化資源を国内外へ流通させる“動脈”として機能させるには、継続的な仲間づくりが不可欠」と強調。行政としても、文化・食・工芸を軸にした地域の海外展開は重要政策テーマであり、「会員制度は、地方創生の実装を支える持続的なエコシステムになる」と述べた。

続いて、日本航空(JAL)ソリューション営業本部担当部長の伊東芳隆氏が、民間企業の立場からネットワーク参加の価値を語った。伊東氏は、航空会社が持つ国際線ネットワーク、富裕層マーケットへの接点、海外PRのノウハウを挙げ、「地域が生み出す文化・工芸・食の価値を、実際に世界の顧客へ届けるフェーズを共に担いたい」と説明。イタリア・ミラノでの展示など北前船の取り組みは日本の地域資源の国際化を後押しする具体的事例であり、「民間の実務力が加わることで、地域の挑戦は一段階上の市場へ届く」と述べた。

両氏は最後に、会員制度を「単なる名簿づくりではなく、各主体が役割を持ち寄る〝協働モデル〟」と位置付けた。行政は制度と政策で下支えし、民間は販路やデザイン・国際発信を担い、自治体は地域資源の磨き上げを進める。こうした三位一体の連携こそが北前船ネットワークの最大の強みであり、「新しい地域価値を世界につなげる基盤になる」と会場に呼び掛けた。
地域連携研究所が地域をつなぐ「新しい航路」をつくる
閉会にあたり、日本航空(JAL)副会長の清水新一郎氏が登壇し、大会を振り返った。会場に入った瞬間に感じたという参加者の表情の違いをユーモアを交えて紹介しつつ、「この2日間がどれほど濃密で、有意義な時間だったかがよく分かった」と語り、登壇者一人ひとりの強い個性と実践知に満ちた講演が印象的だったと謝意を述べた。
地域連携研究所の役割についても言及。「研究所」という名称が誤解されがちな点に触れつつも、その本質は〝仲間をつくり、領域を越えてつながる場〟にあると強調。北前船がかつて海を介して地域をつないだように、現代は鉄道・自動車・航空がその役割を担う時代であり、「地域同士が東京を経由せずに直接つながることこそ、連携研究所の価値だ」と指摘した。自治体同士、企業同士、そして自治体と企業が交差し、新たなアクションに転じる場としての重要性を丁寧に示した。
さらに清水氏は、当日紹介された多数の事例に触れ、「ここで語られた挑戦はあくまで入口にすぎない。大切なのは継続し、次の動きへと変えていくこと」と述べた。来年の舞台が新潟となる予定であることにも触れ、「この流れを一過性で終わらせず、広域での連携をさらに進化させたい」と期待を寄せた。最後に、運営スタッフ、長野県・松本市の関係者に深い謝意を伝えた。
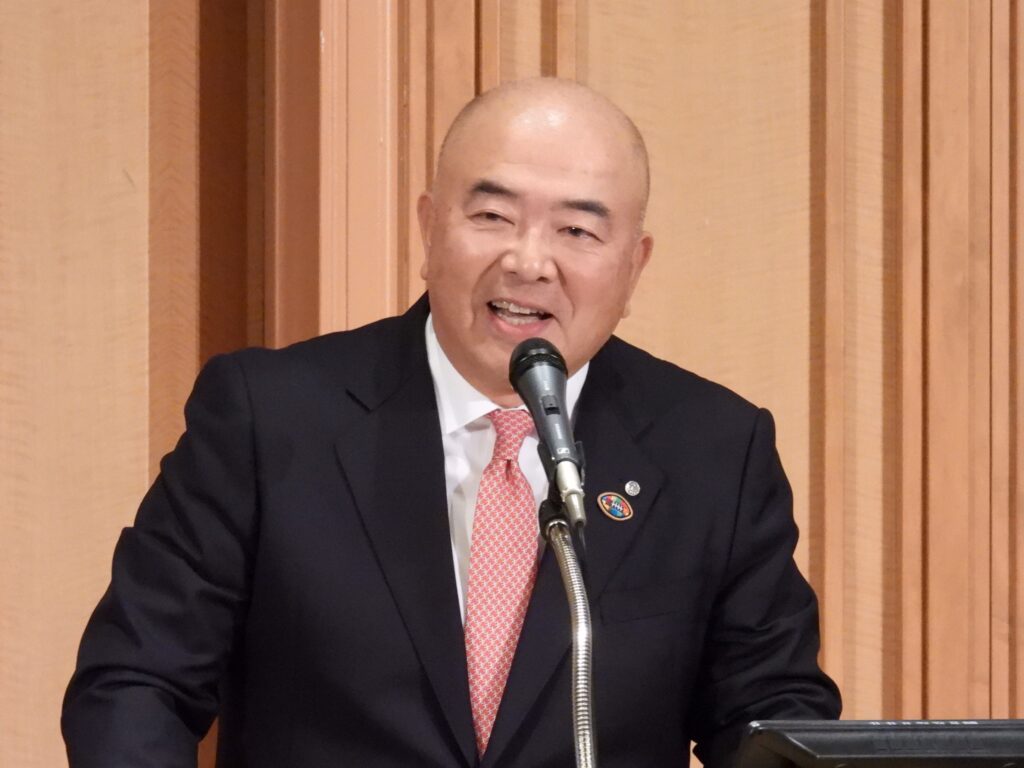
取材 ツーリズムメディアサービス編集部











