江戸から明治にかけて海運を担っていた北前船をテーマに、寄港地連携、地域間交流での活性化を図る「第35回北前船寄港地フォーラムin 加賀・福井(加賀会場)」が11月22日、石川県加賀市山代温泉のみやびの宿加賀百万石で開かれた。会場には、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長や小泉進次郎衆議院議員が駆け付けるなど、全国から自治体や観光関係者、EU各国の大使館関係者ら約380人が出席。北前船文化を生かした観光まちづくりやインバウンドの推進を考えるほか、北陸復興に向けた観光の取り組みを考える議論などが行われた。日本旅行の小谷野悦光社長は「北前船経済圏を提唱するなど、石川好先生が唱えられた『北前船コリドール構想』がまさに動いている。今後は、われわれがいかに工夫できるかが問われる。能登の復興はもちろん、世界に向けても皆さんの力を結集しながら課題を解決し、進んでまいりたい」と総括した。


「北前船コリドール構想」を動かしながら、北陸復興への道筋つくる
同フォーラムでは冒頭、北前船日本遺産推進協議会会長で石川県加賀市の宮元陸市長が「大変大勢の方々にお集まりいただいた。日本人の惻隠の情の表れと言える。加盟自治体が全て参加し、約30人の組長が集うなど、かつてない質と規模を誇っている。われわれの仲間である能登をどう支援するかのその一心だ。大会では地元から北前船に関連する人による話もあり、その取り組みも聞いていただきたい」とあいさつした。

北前船交流拡大機構副会長、元観光庁長官で東武トップツアーズの久保成人会長は、「フォーラムは、北陸復興に向けてが大目的だ。そして、もう一つは北前船の文化を世界に発信すること。北前船はいにしえから世界に開かれた窓口であり、日本海側である内日本の中心地である加賀でフォーラムが行われることは非常に意味深い。多くの地域がこの地で連携することは、今年8月に亡くなられた石川好先生による『北前船コリドール構想』を実現していると言える。北陸新幹線の開業を機に太平洋側にも大動脈ができた。フォーラムを通じて、北陸復興への道筋を作りたい」と述べた。

来賓からは、観光庁の祓川直也長官が「コロナ禍が明けて観光全体は良いトレンドとなっているが、皆さまの尽力によるもの。本日の午前には九谷焼の工房を見学したが、江戸の後期から素晴らしい技術が受け継がれていることを目の当たりにした。一時は長い休眠期間があったが、それを復旧して今につながっていることに感銘を受けた。また、橋立地区は船頭・船員が集う大きな集積地で日本一豊かな場所だったと聞いている。そのような歴史・文化がある土地でフォーラムが開かれることは素晴らしい。多くの人たちと有意義な時間としたい」と話した。

秋田県の猿田和三副知事は「元旦には能登半島地震、9月には豪雨災害があったが、被災した皆さまにお見舞いを申し上げる。秋田県からは石川県に3人の職員を派遣し、復興の手伝いをしているが、1日も早い復旧、復興を心から祈っている」と能登での震災など災害の被災者を見舞った。フォーラムに向けては、「北前船に関しては、北陸と秋田は長く交流を続けてきた。男鹿のナマハゲと能登のアマメハギは、共にユネスコ無形文化遺産に登録されている。また、秋田県の伝統的工芸品である曲げわっぱを北陸の皆さんと一緒に海外に売り出して伝統文化を引き継いでいきたい」とさらなる連携を呼び掛けた。

北前船日本遺産推進協議会からは4人が代表してあいさつ。北海道函館市の大泉潤市長は「回を重ねるごとに土地ならではの特色が全国に発信され、民間の開催としては今や国内最大級のフォーラムとなっている。私はフォーラムの黎明期に市役所内の観光のセクションにいたが、今ではどんどん進化していることに驚きを隠せない。また、復興の機運を高めなければならない時期に、北陸で開かれることに大きな意義を感じている。函館の街は、高田屋嘉兵衛翁がいなければ、小さな漁村、寒村であったかもしれい。そのポテンシャルを見抜いたことが、200年たった今の函館につながっている。日本の誇るべき文化遺産である北前船を礎に交流をつづけていく」と北前船を契機とした新たな交流に期待を寄せた。

秋田県由利本荘市の湊貴信市長は「フォーラムは、能登の復興に向けて力を尽くすことが一つの目的である。一方、7月には秋田や山形でも大雨の被害があり、由利本荘市が200億を超える被害額となるなど、県内で一番被害を被った。いまだ50本を超える道路がまだ通行止めとなっているが、復旧復興に向けて進んでいく。能登の復興は創造的復興であると伺った。われわれもかつてと同じでなく創造的にハードもソフトも次につながるようにしていく」と災害の復旧復興に向けて前を向いた。また、観光面では、鳥海山を核として、秋田県のにかほ市、酒田市、遊佐町の4市町と連携しながらキラーコンテンツづくりを行っていくことを紹介した。
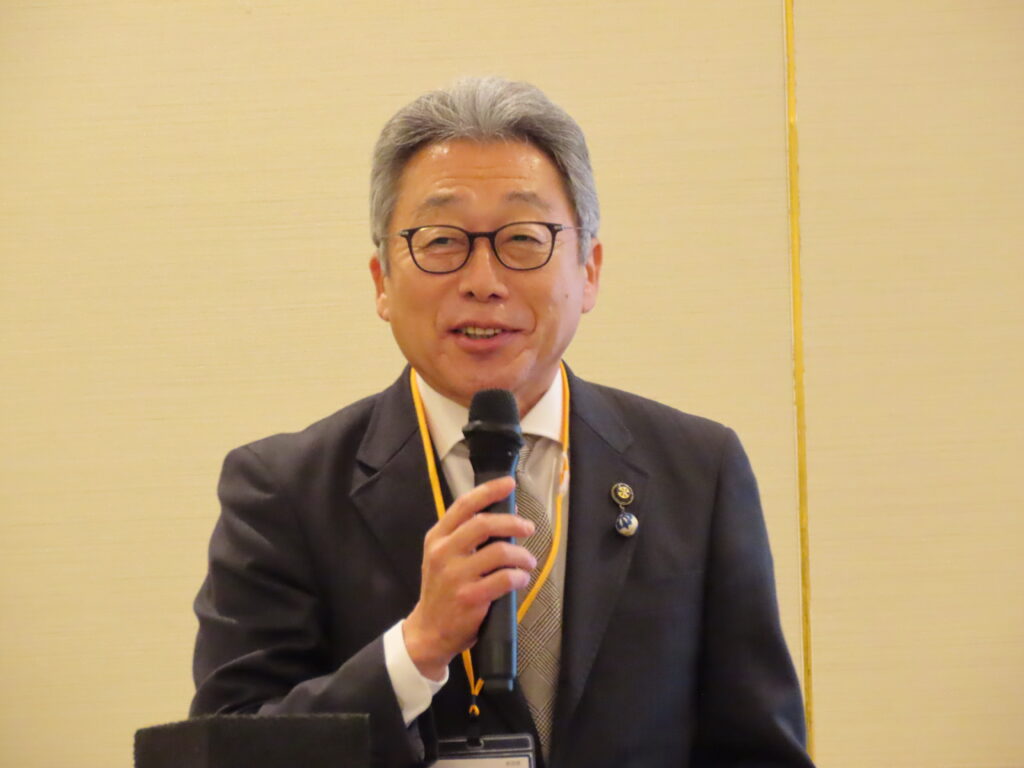
酒田市の矢口明子市長は「酒田市は、第1回の北前船寄港地フォーラムが開催された地である。石川好先生には酒田市美術館の館長も務めていただいた。由利本荘市と同様に号災害で大変な被害を受けた。今も土日では災害ボランティアセンターを開設し、泥かきなどをしていただいている」と7月の豪雨災害を振り返った。フォーラムに向けては、「寄港地フォーラムの存在が災害復旧支援の大きな力になっている。加賀にもそれぞれの分野で活躍している人が集っており、今後の大きな力となるはずだ。皆さまと力を合わせて盛り上げていきたい」と復旧復興への協力を呼び掛けた。

鳥取県鳥取市の深澤義彦市長は「フォーラムのテーマの一つに震災からの復興に向けてがある。1日も早い復興復旧を願ってやまない」と被災者を見舞った。深澤市長は、2015年に初めてフォーラムに参加したことを振り返りながら「当時、加賀市で開かれたフォーラムに参加させていただいた。とても素晴らしいフォーラムであり、2年後に鳥取で開かせていただいた。先人たちは現代以上に盛んに連携、交流をしていたが、われわれも歴史の光を見ながら、連携、交流、活性化を地方自治体がこれからとしっかりと取り組んでいかねばならない」と連携による発展を見据えた。

①北前船文化②石川県復興支援③特別講演―の3部構成
フォーラムは3部制で実施され、第1部では、全国北前船研究会副会長で江沼地方史研究会の見附裕史会長が「橋立北前船主と近江商人との繋がり」、加賀橋立北前船ツーリズム実行委員会の木村茂樹事務局長と小樽商科大学の高野宏康客員研究員は「『北前船の里』加賀橋立~日本遺産を活かした観光まちづくり」を題に講演。見附会長は、北陸3県に北前船主、船乗りが出てきたことに注目。特に加賀の橋立や輪島の黒島を挙げながら、大正5年に発行された「生活」という雑誌の掲載記録を示しながら、橋立が約100軒の地さな村でありながら「日本一富豪の村」として資産家が多くいた地であったことを紹介した。また、日本全国を行脚した近江商人が北海道松前藩で場所請負制を用いながら北前船を使い、石川・福井と交易していたことなどを説示した。

木村事務局長と高野研究員は、北前船の里である加賀橋立を舞台に「保存から活用」を目指した北前船ツーリズムのあゆみを紹介した。同地域では、加賀橋立北前船ツーリズムを観光庁の事業を活用しながら展開。事業では、107棟が伝統的建造物として指定されているなど橋立地区を案内する北前船主のまちなみまち歩きマップが作成されるほか、肌で体感して感じる観光の実現として台湾から観光のプロを招いたモニターツアーの実施、船主邸で浴衣体験や橋立まちの浦安の舞巫女を囲んだ交流などが行われている。台湾からは7月28日、11月18日に「ウェルネスツアー」を迎えて抹茶の作法、生け花、琴の体験、伝統芸能などを提供したことや、北陸新幹線延伸を機にJR東日本、JR西日本、JR東海の3社と関連業者を招きエクスカーションを行ったことなども報告された。高野研究員は、一方で同ツーリズムを取り巻く課題として、空き家問題、自然災害、高齢化などを挙げ、今後は地元参加など「ひと」、伝統体験など「もの」、お土産物販など「かね」に注目しながらど、住民主体の観光まちづくりを展開していくことを説明した。

官民関係者が一丸となり新たな観光地づくりを
第2部は、「石川県の復興支援に向けた取り組み」をテーマに、北前船文化の高付加価値化や、北陸復興に向けた観光の取り組みを考えるパネルディスカッションなどが行われた。基調講演では、元観光庁長官の和田浩一氏がインバウンドが急成長する中での高付加価値な観光地づくりについて説いた。和田氏は、コロナによる変化として世界の旅行者が「持続可能な観光」への関心が高まり、自然、アクティビティに対する需要が高まっていることを紹介。高付加価値なインバウンド観光地づくりに向けては、14地域を選定し、高付加価値旅行者の地方への誘客に向けて、「ウリ・ヤド・ヒト・コネ・アシ」の5つの観点で集中的に実施されていることを述べた。能登半島地震と豪雨災害への支援としては、北陸応援割「いしかわ応援旅行割」が再開されたことを案内しながら、交流人口拡大(観光)による地域の持続可能性向上に向けては、復興から地域における観光収益の拡大、観光収益の地域内還流、地域課題の解決を「官民関係者が一丸となって取り組むべき」と訴えた。

「北前船文化観光」の拡張、「北前船ストーリー」の確立へ
続いて、「北前船文化と高付加価値インバウンドの推進」を題に、北前船交流拡大機構顧問で石川県観光連盟の上口昌徳副理事長、石川県観光大使の福原義明氏、石川県北前船文化観光上口塾コンソーシアムチームが登壇。福原氏は石川県におけるインバウンドの現状を紹介。延べ宿泊者数は2019年の約2倍に増加する一方、課題としてインバウンドの金沢一極集中、1.5日という滞在時間の少なさ、能登半島地震の影響などを挙げた。改善に向けては、日本遺産となる北前船寄港地をストーリーとしてプロモーションしたり、横断的な機能を持つ新たな組織の設置などをしながら、北前船に関心を持った海外ハイエンド層の取り込み、教育性の高い旅行所品の開発などに取り組み、北陸全体としての「北前船文化観光」の拡張、北陸新幹線延伸を契機とした新しいインバウンド観光ルート「北前船ストーリー」の確立を目指すことを宣言した。

上口副理事長は、北前船の歴史と文化、観光への理念と哲学を「日本の表と裏」をテーマに講演。92歳となる上口副理事長は船問屋を営んでいた母方の先祖を振り返りながら、母親が北海道の民謡「江刺追分」を歌っていたことを紹介した。日本海側が裏日本と言われていたことに対して、「汚い、暗いものを隠しているのではなく、本当の日本を残している」と話し、北前船が文化を運んでいたことを語った。フォーラムについては、「本来の日本人は何かということを原点にかえり、皆で考え直す大事な機会だ。大和民族と言われるもっと前から、日本人は世界に例のない何か大事なものを持っている。日本海側の文化を向上させた北前船の精神もある中で、われわれは世界の中で役割を果たし、歴史・文化を含めて今ある大切なものを後世に残していかなければならない」と語った。
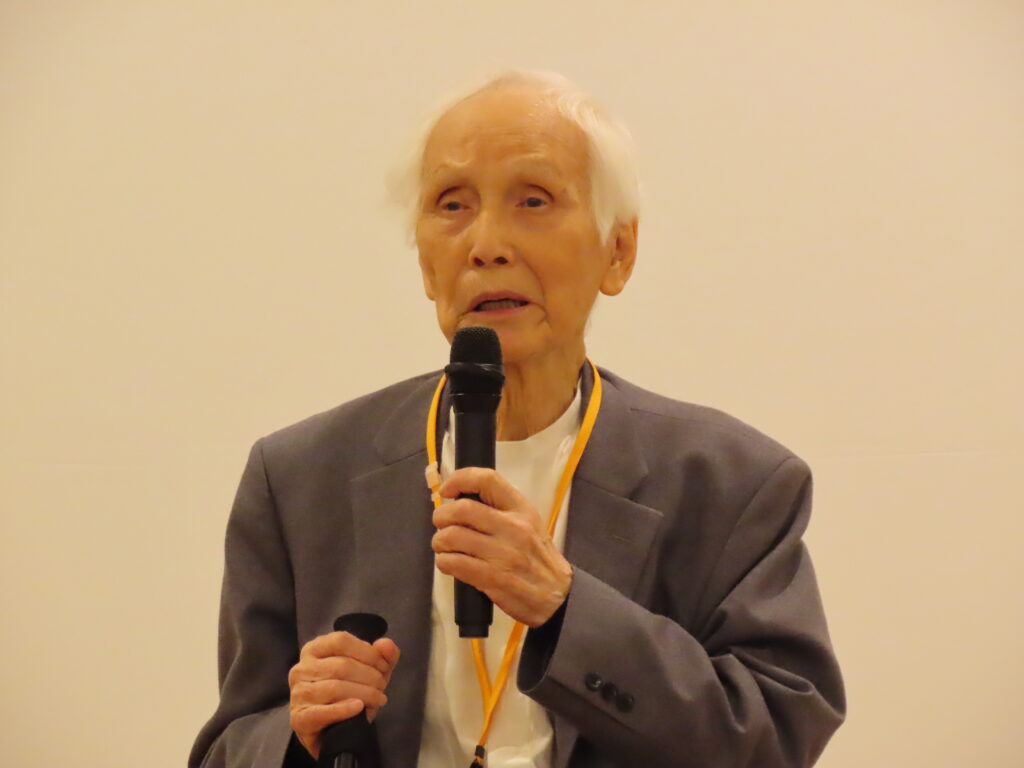

能登をフォーカスし、震災前よりも魅力的な地域に
パネルディスカッションでは、「北陸復興に向けた観光の取り組みを考える」を題に議論。ファシリテーターとして観光庁の長﨑敏志観光地域振興部長を迎えながら、パネリストとして日本航空中部支社の岩見麻里支社長、全日本空輸石井智二取締役執行役員、西日本旅客鉄道の岡田学理事・マーケティング本部鉄道マーケティング部長、日本旅行の吉田圭吾常務取締役ソリューション事業本部長の4人が登壇した。
長﨑部長は、今後の北陸に向けて「お悔み、お見舞いの後に、われわれとして何ができるかを考えなければならない」と呼び掛けた。石川の観光については、「石川県全体の宿泊はコロナ前よりも良く、インバウンドについてはさらに良い状況だ。だが、金沢や加賀でなく、能登にフォーカスを当てなければ議論にならない。能登の旅館・ホテルは300強あるが、事業を再開しているのは1割にも満たず、和倉では22の旅館のうち復旧しているのは3軒で、従業員は困り、観光客が戻っている状況にはない」と能登の状況を踏まえながら議論することの大切さを訴えた。

日本航空の岩見支社長は、能登震災復興支援として、マイルやふるさと納税を通じた義援金・寄付、応援割や応援クーポンの発行など「JAL復興応援キャンペーン」の実施、ドローンによる調査協力、社員ボランティアの派遣などを行ってきたことを紹介。今後に向けては、「北陸の自然や歴史、食といった観光コンテンツを掘り起こしていく」と観光需要を掘り起こすことや、首都圏など都市部からの2地域居住を促すプロジェクトを通じた支援を継続しておこなっていくことを宣言した。

全日本空輸の石井取締役は、ANAグループの北陸支援として行ってきた取り組みとして、義援金・マイル寄付や能登臨時便の就航、能登復旧支援割といった復旧支援、被災4件観光需要喚起策、北陸応援割旅行商品の販売、能登復旧支援ツアー、能登便複便など復興支援などを行ってきたことを紹介した。「正月明けにすぐに経営トップ全員が集まり、北陸にできることは全部やると意志固めをして、この1年間進んできた。12月以降も12月25日からは能登線を朝と夕方の2便に増便する」と、観光の受け入れ整備や観光人材の育成などを通じ、交流人口の拡大に寄与しながらの継続した復興支援を約束した。

西日本旅客鉄道の岡田理事は、地震発生直後からの復旧に向けた取り組みとして、七尾線やのと鉄道といった鉄道の早期復旧や、被災者・被災地支援として、義援金やポイント付与などを紹介。北陸全体に足を運んでもらう取り組みとして、北陸新幹線金沢~敦賀間開業と告知、「北陸おでかけtabiwaバス」特別価格の販売など地域の状況を踏まえた送客・地域消費拡大の施策を展開したことを発表した。今後に向けては、全国から集中送客を図る取り組みとして10~12月で実施している北陸デスティネーションキャンペーン(DC)の展開、アンテナショップでの北陸のPRなどを実施する。「北陸新幹線開業効果の最大化、持続に向けて、JR西日本グループを上げた観光利用促進の取り組みを通じ、北陸復興へとつなげる」と力を込めた。

日本旅行の吉田圭吾常務は、震災発生直後からの支援として、工事事業者や他自治体からの派遣といった被災地域への支援者の宿泊斡旋や、被災者の宿泊・入浴支援として自衛隊借り上げ船舶2隻の運営管理、被災宅地の相談、公費解体の申請など被災者の支援窓口の運営を行ってきたことを紹介。「能登笑顔プロジェクト」として、被害を受けた学校・生徒に支援を届けるとの思い出、関西と北陸の学校と話し合いの上でボランティアツアーや現地クラブ生交通費支援、大阪ツアー無料招待といった取り組みも披露した。「観光誘客に向けて、旅行代金の一部を義援金として寄付する商品も開発している」と復興商品の造成・販売を通じた支援もしていることを伝えた。1人500円で約2万人から集まった1000万円を寄付している。

最後に、長﨑部長は復興プロジェクト参画から観光まで、関係人口を創出で復興を加速させる「のと100プロジェクト」が11月から本格始動していることを説明。プロジェクトでは「#いま能登で出来る100のこと」を発信し、いま能登でできる100のこと いま行ける、いまできる能登の魅力を100の視点で紹介されている。「運送事業者や旅行会社の思いを受け止めた。今後も北前船関係者が思いを一つに、力を合わせて地元を支援していかなければならない」と参加者へさらなる協力、支援を呼び掛けた。また、パネルディスカッションでの話を受けて石川県輪島市の坂口茂市長は「多くの観光客を受け入れて十分なもてなしはできないが、今しか見られない景観、今しかできない体験がある。フェーズによって中身は変わるが、観光業は輪島市にとって非常に大きな産業であり、100のことの1つでも拾っていただきながら、現実を知っていただきたいし、震災前よりももっと魅力的な輪島としたい」と答えた。

新しいマーケットの開拓、持続可能へ地域一体での仕組みづくりを
日本政策投資銀行企業投資第3部の西村俊輔地域投資担当課長は、同行が取り組む輪島塗の復興に向けた活動を紹介した。活動事例として、海外展開支援として行ったイタリア・ミラノで4月に開かれたミラノ・サローネの視察や8月10日にベルギーにある諏訪田製作所ブリュッセル店で実施した諏訪田製作所と輪島塗職人のマッチングについて説明した。西村課長は、「輪島塗は3人の人間国宝を有する国を代表する伝統工芸の一つだが、産業としての規模は震災前から長期的な縮小傾向にあった。バブルの1991年には180億円あった生産規模が、9分の1に縮小し、従業員は3分の1、所得も600万円から3分の1に縮小している」と危機的状況が続いていることを訴えながら、持続可能な産業とするためには、マーケットを50億円まで再拡大しなければならない必要性を訴えた。再拡大には、新しいマーケットの開拓、持続可能となるための地域一体での仕組みづくりの二つの方向性が大事だと説いた。

楽天・三木谷会長、インテックス・植村社長、小泉衆議院議員が登壇
第3部では特別講演を行い、3人が登壇した。楽天グループの三木谷浩史会長兼社長は、災害時における情報ネットワークの重要性を話した。楽天では、能登半島地震において、移動基地局車を累計40台、可搬型発電機を累計48台稼働していた。被災エリアの応急復旧については、1月15日までに、進入困難地域を除き、いち早く応急復旧が完了していたことを明らかにした。また、輪島市在住者の投稿から、「最速で駆け付けたのは楽天モバイルで、地元銀行が使えない中でスムーズに利用できたのが楽天銀行だった」というエピソードを披露した。また、被災地への活動して、避難所などにおける無料充電や、Wi-Fiルーターの無償提供などの支援を行ったほか、支援募金が楽天ふるさと納税では18億7864万4000円、楽天クラッチ募金では3億5858万2243円が集まったことを報告した。このほか、災害時もつながる日本全域エリアカバーの実現に向けて、AST SpaceMobile社との戦略的パートナーシップの締結、商用衛星「Block 1 BlueBird」5機の打ち上げおよび全5機のアンテナ展開の成功といった取り組みを披露し、「日本の携帯キャリア面積カバー率は70%程度だが、2026年内には100%カバーを目指したい」と話すとともに、今後における北陸の応援についても約束した。

インテックスの植村公一社長は社会・公共インフラのPPP(Public Private Partnership)による地方創生などを国内外で展開するプロジェクトマネジメントの第一人者として、「PPPを活用した地方創生」について話した。植村社長は、まずPPPのメリットとして「官民連携のメリットは公共の資産を活用して、民間事業者がインフラビジネスを展開すること」と伝えながら、官民連携において必要とするテーマとして①気候変動への対応②共生社会の実現③地方におけるスタートアップの支援―の3つを挙げた。また、気仙広域環境未来都市推進共同事業体による東日本復興に関する取り組み、環境・超高齢化対応等に向けた環境未来都市構想の基本的な考え方、大船渡駅周辺地区震災・津波復興プロジェクトの概要、エリアマネジメントの仕組み構築支援といった取り組みなど、国内外の取り組みについて説明した。参加者に向けては、「制度設計を含めて難しいことがあるが、間違わなければ、これから増えるであろう地方創生の公的資金をミックスして組み合わせることで、地方創生の非常に大きな力になる」と述べた。

小泉進次郎衆議院議員は、同日に自民党で水産総合調査会長に就任したことを伝えながら、「地方創生に切っても切れない話として、食、第一次産業である農業・漁業である」と話し、地域の経済を良くするためには地域の総点検が必要であることを訴えた。地元である横須賀市では、小学校で海外産である小麦でなく国内産の米粉を利用し、小麦アレルギーの子どもへの配慮をもしていることを紹介した。「米粉への置き換えが進むと共に、小麦粉との価格の差がないこと、グルテンフリーであり、食べ残したカレーが皿にこびりつかずに労力が減った」と事例を紹介しながら、今まで当たり前だったことの振り返りを呼び掛けた。また、エネルギー問題にも切り込み、廃棄物の資源化、再生可能エネルギーの活用などを挙げながら、「CO2をただ減らすのではなく、出るものが出るから使うといった発想も含めて、これからは地域の中で他の地域にはないような攻めのまちづくり、差別化ができれば、まだまだ地方の中で、より活性化をして豊かになる地域が必ず出てくる」と来場する多くの地域に呼び掛けた。













