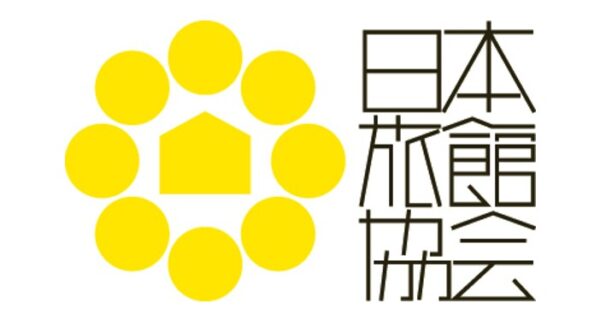江戸から明治にかけて日本各地の港町を結び、物資と文化を運んだ北前船。その歴史を軸に、寄港地連携と地域間交流による地域活性化を議論する「第36回北前船フォーラム in 信州まつもと」が11月21日、長野県松本市のホテルブエナビスタで開かれた。今回は北前船ゆかりの沿岸部から遠く離れた“内陸の地”での初開催で、テーマは「令和に呼び覚ませ、塩の道~海洋と内陸の経世済民~」。全国から自治体首長、観光関係者、伝統工芸・食の事業者、学識者、企業関係者ら約370人が参加し、海と山、沿岸と内陸という二つの文化圏を架橋し、北前船が築いた歴史的ネットワークを令和の地域政策・観光戦略へどう生かすかについて、活発な議論が交わされた。
総括を行った観光庁元長官で東武タワースカイツリー会長の久保成人氏は、「歴史を未来へつなぐために欠かせないのは、中央からの一方向の発信ではなく、地域が本来備えている内発的な力を見つめ直し、互いに結び合うネットワークだ」と指摘。さらに「かつて北前船が海と内陸を直接つなぎ、多様な文化や産業を育んだように、地域が地域と対等につながる構造を取り戻すことが重要だ。内陸の松本で本フォーラムを開いた意義は大きく、海と山、沿岸と内陸が新しい形で結び直される象徴的な契機となった」と述べ、北前船文化を基盤とした地域連携の広がりに大きな期待を示した。

内陸初開催、「塩の道」で海と信州を結ぶ
開会における主催者あいさつでは、長野県副知事の関昇一郎氏が長野県知事の阿部守一氏に代わり登壇し、「全国各地からこれほど多くの皆さまにお越しいただき、心より感謝申し上げる」と述べた。その上で、これまで海沿いの地で開催されてきたフォーラムが初めて内陸で開かれた意義に触れ、「瀬戸内から北前船が運んだ塩が『塩の道』として信州へ届き、暮らしを支えてきた歴史がある。海と内陸は本来、緊密につながっていた」と強調した。また、今回のフォーラムが生む地域間交流について、「人と人、地域と地域が出会い、つながることが新しい発展の土台になる」と述べ、人口減少や社会情勢が厳しさを増す中で「地域のネットワークこそが日本の原動力になる」と期待を寄せた。

続いて長野県松本市長の臥雲義尚氏は、全国からの参加者に感謝を示しつつ、信州と北前船をつないできた歴史的背景に言及した。「信州の名産である味噌や酒、漆器、絹といった産業は、日本海側の港から運ばれた塩や海産物との交易によって大きく発展してきた」と述べ、海と内陸の間に古くから存在した経済・文化の交流の深さを強調。さらに、松本を中心とした広域の自治体首長が実行委員会として参画していることを紹介し、「沿岸と内陸、地方都市同士があらためてつながり直す場として、このフォーラムが未来への一歩となることを期待したい」と語った。また、「山高く水清くして風光る」という言葉を引用し、北アルプスを望む松本の風景に触れながら、「この地での開催は、海と山、歴史と現代をつなぐ象徴的な機会になる」と歓迎の意を示した。

開会あいさつに立ったANA総合研究所副社長で北前船交流拡大機構理事長代行の森健明氏は、「ようこそ信州へ、そして私のふるさと松本へ」と述べ、全国からの参加者に謝意を示した。森氏は、これまで北前船寄港地の港町で開催されてきたフォーラムが初めて内陸で開かれた意義に触れ、「北前船の広域ネットワークは本来、海だけでなく内陸とも深く結びついていた」と強調した。さらに、松本開催の背景には地域連携研究所の立ち上げなど、寄港地以外の自治体も含めた広域的な連携の取り組みがあることを紹介し、「今回の開催は、北前船ネットワークの新たな広がりを象徴するものだ」と述べた。

日本航空(JAL)執行役員で北前船交流拡大機構副会長の西原口香織氏は、全国からの参加者に感謝を述べた上で、「2007年に酒田市で始まった北前船フォーラムが36回を迎え、ここまで発展してきたのは、各地が培ってきた文化の力と関係者の尽力のおかげだ」と振り返った。今回の松本開催については、「海に面していない信州で北前船を語ること自体が象徴的であり、“塩の道”を通じて海と内陸が結ばれてきた歴史を考える機会になる」と指摘。また、JALとしても「国内外への発信に積極的に取り組む北前船交流拡大機構とともに、文化を軸とした地域創生を支えていきたい」と述べた。

海から内陸へ、寄港地文化が示す「地域間交流の再構築」
北前船日本遺産推進協議会からは4人が代表してあいさつ。秋田県男鹿市長の菅原広二氏は、ユネスコ無形文化遺産に登録されたナマハゲ文化に触れ、「ナマハゲは秋田県全域にある文化ではなく、男鹿が独自に守り継いできた精神文化だ」と紹介。誰の目があるかに関わらず続けられてきた行事であることを示し、「地域の覚悟と誇りが文化を支えてきた」と強調した。さらに男鹿と北前船の関係について、「古来、日本海交易を通じて文化や技術が流入し、地域の生活・価値観にも深い影響を与えてきた」と述べたうえで、「北前船の精神は『互いに補い合う地域間連携』にある。今後も寄港地ネットワークの一員として、新しい交流の形をつくっていきたい」と語った。

続いて登壇した石川県輪島市長の坂口茂氏は、能登半島地震後の復興の現状を踏まえ、「輪島塗という文化は、単なる工芸の枠を超え、北前船文化圏で磨かれ受け継がれてきた『精神の結晶』である」と述べた。震災で工房や生産基盤は大きな被害を受けたが、「技術を失ったわけではなく、むしろ文化への誇りが次の復興の力になる」と力を込めた。また、「北前船の交流史は、沿岸のまちが互いに助け合い発展してきた歴史そのもの。全国の皆さんと連携しながら、輪島から新しい文化再生のモデルを発信したい」と語り、文化を軸とした復興への強い決意を示した。

新潟県佐渡市長の渡辺竜五氏は、佐渡が持つ圧倒的な文化層の厚さに触れた。「金銀山、能、酒づくり、漁業、鬼太鼓、自然景観と佐渡ほど多様な文化資源が凝縮している地域は珍しい」と述べ、これらは北前船寄港地としての歴史が培った『文化の蓄積』であると説明した。さらに、「北前船は物資だけでなく、人・技・文化を運んだ。その交流の軸を寄港地同士で再構築し、海から内陸へ広がる文化ネットワークを取り戻すことが、日本全体の活力にもつながる」と述べ、佐渡としても連携の中心的役割を担う意欲を示した。

北海道函館市長の大泉潤氏は、「瀬戸内から運ばれた塩が千国街道を通り松本へ届き、内陸へ広がっていった塩の道の歴史は、沿岸と内陸が互いに補完し合っていた証拠だ」と述べ、北前船文化が海だけでなく内陸にも深く根付いていることを強調した。また、「北前船ネットワークの価値は、地方同士が直接結びつく『水平連携』の構造にある。東京を介さず、地域と地域が対等に挑戦できる環境こそ日本の未来を形づくる」と語った。最後に、「このフォーラムをきっかけに沿岸と内陸の連携がさらに広がり、全国の自治体が自立的に支え合うネットワークを築いていきたい」と締めくくった。

交通・観光から見た「新たな広域連携」
来賓として登壇した日本旅行社長の吉田圭吾氏は、同社の創業120年に及ぶ歴史を紹介し、1905年に長野向けの貸切列車旅行を日本で初めて実施したことに触れた。「鉄道は、地域と地域をつなぐ『陸の北前船』としての役割を果たしてきた」と述べ、北前船フォーラムの意義と近代交通の精神が続いていることを示した。また、「北前船フォーラムが、鉄道・航空・海運を含めた広域的な交流モデルへ発展していくことに期待している」と語り、観光産業から見た地域連携の未来像を提示した。

開会式では最後に、北前船交流拡大機構専務理事の浅見茂氏が登壇して全国から参加した自治体・企業を紹介。沖縄からの参加者にも触れながら、「北前船ネットワークは、地方同士が結びつき、さらに世界へ広がる潜在力を持つ」と述べた。また、「地域の文化や産業を互いに補い合いながら、広域連携を進めることこそ北前船の精神であり、現代でも活かすべき日本の強みだ」と締めくくった。

寄港地から内陸へ、北前船文化が描く広域交流の原点
第1部の基調講演では3氏が登壇し、寄港地から内陸への交流、古代史に見る地域ネットワークの連続性、そして移動がもたらす新しい価値の創出という、それぞれの切り口からフォーラム全体の問題意識を立体的に描き出した。

寄港地と信州をつないだ「塩の道」、海・川・陸路が支えた物流網
基調講演の冒頭を飾ったのは、松本出身で現在は東京在住の近畿大学名誉教授・胡桃沢勘司氏である。氏は「寄港地から内陸へ」をテーマに、信州へ塩を運んだ六つの主要ルートを体系的に解説した。今回の全国大会が“港町以外”では初めて松本で開催された背景については、「海のない信州こそ、海上物流と陸路の結節構造を示す象徴的な地域だ」と述べ、講演を始めた。
胡桃沢氏がまず強調したのは、信州へ運ばれた最重要物資が〝生命維持の基礎〟である塩だったという点である。江戸期、瀬戸内海沿岸の入浜塩田で大量生産された塩は、糸魚川・直江津・清水・三河湾など各地に陸揚げされ、そこから内陸へ流通した。なかでも象徴的なのが糸魚川—松本ルートで、瀬戸内塩や能登塩が糸魚川に届き、大町までは川船、大町から松本までは馬で運ばれた。戦国期の「謙信が信玄に塩を送った」逸話も、この道筋に重なると言われる。また直江津から高田へは荒川の川運が担い、その後は北国街道や山間ルートを経て長野へと届けられた。一方、江戸から佐久・上田方面へは江戸川・利根川を遡る川運が中心で、倉賀野から中山道の陸路へ接続。さらに駿河湾・三河湾からは富士川や矢作川の川船が活躍し、諏訪・伊那・飯田・木曽谷など信州南部へ塩を送り込んだ。「海のない信州には四方から多様な塩が入り、地域ごとの味噌文化の違いにもつながった」と氏は述べた。
講演の中心に据えられたのは、海運と川運がどのように連結されていたかという点。六つの主要ルートのうち、暴れ川・姫川を抱える千国街道だけが川船を使わず、他はすべて海船、川船、牛馬という三段階で物資を運んだ。胡桃澤氏は「小型の川船でも約2トンを積み、馬15頭分に相当する。最初に川運を確保できるかどうかが内陸輸送の成否を決めた」と述べ、北前船の背後で川船が果たした役割の大きさを強調した。さらに山形・最上川の事例にも触れ、「佐渡に上陸した荷が150キロ超の川筋をさかのぼり、山形・米沢へと届いたように、海上物流は川運なしには内陸へ展開できなかった」と指摘。海と陸をつなぐ物流の接続点の重要性を示した。結びに胡桃澤氏は、「北前船の物語は海の上だけで終わらない。川を遡り、峠を越えて、ようやく信州の暮らしへ届いていった。その多層的な接続こそ、日本の物流文化の深みである」と語り、会場に歴史像を提示した。

古代史が示す「地域間ネットワーク」の必然性
続いて登壇したANA総合研究所会長の功刀秀記氏は、近年静かな広がりを見せる古代史ブームに着目し、各地域同市が歴史資源を共有することで生まれる新たな連携の可能性を示した。東京国立博物館等のはにわ展及び古代史関係の作品を含む国宝展が相次ぎ、新聞各紙でも特集が組まれるなど、古代史関連の動きが活発化していると紹介。「こうした潮流を、地域同士が互いの歴史を紹介し合う交流の契機にできる」と述べた。次回大会が新潟で開催されることに触れ、古津八幡山古墳や糸魚川・姫川のヒスイを例示した。
功刀氏は、古代史が観光施策との親和性も高いとし、FDA(フジドリームエアラインズ)が路線プロモーションで神社など古代要素を扱った事例や、自身が北海道勤務時代にオホーツク人文化を観光誘致に活用した取り組みを紹介。「歴史的素材が観光回遊を促す具体例は各地に豊富に存在している」と語った。一方で、古代史の価値は観光振興だけではないと強調。各地の資料館を取材するなかで、学芸員が「最初は遠慮がちながら、語り始めると目を輝かせ、自地域の歴史を誇りとして語る」姿に触れ、古代史研究が地域に精神的な力も与えると述べた。全国の古代遺跡を比較し物語化することで、「欧米の旅行者が重視する歴史性を、持続的な観光資源として提示できる」と述べた。講演では、瀬戸内海の明石海峡を望む五色塚古墳(兵庫県明石市)を例に、古墳が地方豪族の政治的影響力を象徴するランドマークであることにも触れ、「地政学的な意味を今に伝える」と説明。自身が同地で景観を眺め「古墳の主の視点を体験した」と語るなど、古代遺跡の象徴性を強調した。
最後に功刀氏は、「古代史は地域の物語を再編集し、広域連携を生む媒介となり得る」と述べ、資料館や埋蔵文化財センターに眠る郷土史を相互につなぐ意義を強調。「一時的なブームに留まらず、地域の誇りと歴史を未来へ橋渡しする取り組みにしたい」と述べ、講演を結んだ。

古代から続く包摂性と信濃国の戦略的位置
基調講演の最後には、国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課長の星明彦氏が登壇し、「しなのの国から~懐かしくて新しい世界をつくる~」と題して講演した。縄文から近代に至る歴史を踏まえて「信濃国が日本列島の要地として担ってきた役割」をについて星氏はまず、山陰で発掘された遠洋型木造船の例を挙げ、「古代から外との交流があり、多様性を受け入れる包摂的文化が形成されていた」と説明。今日で言われる〝ウェルビーイング〟が、縄文文化の段階で実践されていたとの見方を示した。
続いて信濃国の歴史的地位に触れ、古代には東山道の原型となる交通路が存在し、大和政権が国家基盤を整備する際に「最初に戦略的に押さえた場所が松本周辺だった」と紹介。東山道は北東北まで延びる官道へ発展し、人・物の移動を支えたと述べた。その交通基盤は中世・近世にも継承され、京都への貢物輸送や武士の行軍、江戸期には参勤交代路として使われたほか、近江商人が瀬戸内・九州・日本海の産品を運び込み、地域の産物と融合させて新たな価値を生む役割を担ったと説明。「江戸期の日本には、地方にも高付加価値を生む都市が存在していた」と指摘した。また〝人づくり〟の面でも信濃国が先進的だったと述べ、寺院・武家主導が一般的だった寺子屋と異なり、「農民が自発的に教育を始め、多様な学びを育てた」点を強調。これが近代教育につながり、開智学校の成立にも結びついたとした。
さらに星氏は、自身が関わった「GW(ゲートウェイ)2050 PROJECTS」に触れ、スイスの都市戦略との比較から「人材育成、民間主導、混ざり合いによるイノベーション」といった要素が、古代から信濃に育まれてきた文化と重なると説明。「地方発の自律成長は十分に実現可能だ」と述べた。終盤では県民歌「信濃の国」に示される地域の多様性と豊かさに触れ、「信濃は歴史的にも文化的にも日本の中心的な土地であり、その誇りを再認識してほしい」と語った。最後に、地域交通政策の視点から「人の往来こそが共同体の信頼と幸福を育てる」と述べ、北前船ネットワークが地方同士、さらに地方と世界をつなぐ可能性を強調して言葉を締めた。

地方が描く「高付加価値インバウンド」の戦略と実践
第2部では、「地方における高付加価値インバウンド観光の推進」をテーマに、研究者、行政経験者、宿泊・観光事業者が多角的な視点から議論した。モデレーターを務めたのは清泉女子大学学長の山本達也氏。パネリストには、観光庁元長官で運輸総合研究所理事長業務執行理事の和田浩一氏、自遊人代表取締役の岩佐十良氏、扉ホールディングス代表取締役の齊藤忠政氏の3名が登壇した。

冒頭、山本氏は自身が二拠点居住という形で松本と東京を往復している経験を紹介し、「自然と都市文化が近接する松本は、今後の日本を象徴するような都市モデルになりうる」と指摘した。基調講演で語られた「海と山」「沿岸と内陸」という対比軸を踏まえながら、「地方都市の価値は、歴史・文化・自然環境をいかに高付加価値として束ねるかにかかっている」とし、このパネルが第1部の議論を実践レベルに落とし込む機会であると強調した。

国の視点から見る「地方インバウンド戦略」の課題と転換点
和田氏は、国のインバウンド政策の流れを踏まえながら、近年の訪日外国人の動向が「東京・京都・大阪といった従来の黄金ルートから、地方都市へ確実に広がっている」と指摘した。そのうえで、「高付加価値層の取り込みには、単なる「観光地の魅力競争」ではなく、地域が一体となった価値創造が不可欠」と述べた。また、「知識層・富裕層は『自分の興味関心が深い領域』には積極的に支出する。地方側はそのための受け皿づくりが重要だ」とし、モデル観光地として松本・高山エリアが国の伴走支援を受けていることを紹介。「5年間の長期支援がつくのは、観光庁としても『地方が主役の観光』を進める本気度の表れ」と語り、制度面から松本の取り組みを後押しする姿勢を示した。

新しい旅の価値を生み出す仕組みづくり
齊藤氏は、松本で立ち上げた「松本における持続可能な観光地づくりの産業研究会」を紹介し、「観光はすでに地域の主幹産業になりつつあるが、旅館・飲食だけでは地域全体の価値をデザインしきれない」と述べた。研究会には、信州大学や不動産デベロッパー、木工職人、農業者など21団体が参加しており、「観光の枠を超え、地域の未来をどうつくるかを議論する場としている」と説明。さらに、近年顕在化したオーバーツーリズムの課題を挙げ、「観光地の魅力が生活環境の悪化につながらないよう、地域内で適切なバランスをとる必要がある」と警鐘を鳴らした。「高付加価値観光とは、単価の高い客を呼ぶことだけではなく、地域に文化・技術・暮らしを再循環させる仕組みを作ることだ」と述べ、観光と地域経済を結びつける視点の重要性を示した。

地域文化を世界基準の体験に昇華する
最後に発言した岩佐氏は、自身が手掛ける浅間温泉「松本十帖」を例に、地域文化をいかに世界へ伝えるかを語った。岩佐氏は、「水や火山、温泉、伝統工芸など、日本文化の核心は『自然と生活の関係性』にある」と指摘し、それを宿泊体験として編集することで、海外の上質旅客に強く訴求できると説明した。また、世界の富裕層の旅の傾向として、「移動距離より『体験の深さ』を求める傾向にシフトしている」と述べ、「松本のように“具体的な文化層”が厚い地域は、深さで勝負できる」と評価した。さらに、地域内の複数施設を回遊させる「文化回廊」的な仕組みの可能性にも触れ、「日常と地続きの文化を、高品質な体験に転換することが地方の競争力になる」と語った。

パネルディスカッションの最後に山本氏は、第1部からの議論を踏まえ、「海と内陸、沿岸と地方都市という縦のつながりが、観光における広域連携モデルとしてそのまま活かせる」と総括した。高付加価値インバウンドは、単なる経済施策ではなく、①地域文化の再編集②生活者と観光者の共存③地方同士の水平連携―という「北前船的発想」の延長線にあると結んだ。
世界市場を見据える「地域文化」の挑戦
フォーラム後半となる第3部では、「伝統工芸品と食の海外展開」をテーマに、北前船が築いた広域ネットワークを活かして地域文化をいかに国際市場へ橋渡しするかが議論された。松本という内陸都市での開催にふさわしく、海と山、都市と海外をつなぐ多層的な視点から、登壇者が未来への道筋を語った。
最初に登壇した新潟県村上市長の高橋邦芳氏は、日本海沿岸に息づく文化が「海の交流そのものによって磨かれてきた」点を強調し、村上の鮭文化や茶の湯文化も北前船の往来がもたらした結節点にあったと紹介した。さらに氏は、北前船の寄港地52都市を示す地図を掲げながら、「これは歴史がつくった物流網であると同時に、日本文化を支えた見えない『交流インフラ』だ」と指摘した。そのうえで、北前船寄港地のうち経済産業省が認定する伝統的工芸品を持つ自治体が21市町にのぼる事実に言及し、「これら一つひとつが日本の宝であり、地域の誇りである」と述べた。午前中には、これらをつなぐ新組織として「北前船伝統的工芸品ネットワーク」を立ち上げることを発表。輪島市や佐渡市をはじめ、各地の首長が登壇した開会式の議論を踏まえ、「個々の自治体だけでは越えられない課題がある。ネットワークを組むことで初めて海外展開の扉が開く」と語った。
さらに高橋氏は、イタリア・ミラノのフォーリサローネで備前焼や大館曲げわっぱが高く評価された事例を紹介し、「欧州での評価はすでに確かな手応えがある。しかし、生産者・作家が持続的に市場へアクセスする仕組みは整っていない」と課題を提示。そこでこそ、北前船のネットワークを活用した広域連携の意義が生まれるとし、「宝を宝のまま埋もれさせず、世界に届ける道筋を皆でつくりたい」と述べた。
最後に、「伝統的工芸品を持つ21自治体は今は点となっているが、これらが確実に線となり、面となっていけば、日本文化の新たな地図が描ける」と語り、今後のフォーラムで成果を共有していく考えを示した。「今日はキックオフにすぎない。多くの仲間とともに、この北前船フォーラムから新しい挑戦を進めていきたい」と結び、会場に大きな期待を残した。

日本の工芸を「世界の富裕層」へ、アートフェアが開く新たな可能性
今年夏までEU日本政府代表部参事官としてブリュッセルに勤務していた財務省大臣官房企画官の二宮悦郎氏は、日本の工芸が抱える構造的課題と、世界市場における展開可能性について多角的に論じた。二宮氏が北前船関係者と初めて関わったのは3年前のパリ大会で、地方自治体から「食や酒は政府の支援が進む一方、工芸には推進力が乏しい」という切実な声を受けたという。
そこで二宮氏が直感したのは、日本の行政システムが依然として大企業中心に設計されているため、小規模事業者が多い伝統工芸は制度の外側に置かれ、結果として販路支援や政策的後押しが届きにくい構造にあるという点だった。加えて、国内市場の縮小によって従来の支え手が減り、海外に売り出そうとしても仲介機能が決定的に不足しているという現状も大きな課題として指摘した。工芸品が〝価値としてのポテンシャル〟を備えていながら、市場にアクセスする回路が整備されていないというのが氏の問題意識である。
一方で二宮氏は、欧州での経験を通じて、世界的にもユニークな伝統工芸こそが日本が世界の富裕層へ直接アクセスできる数少ない分野であると強調した。世界の超富裕層は資産の約5%をアートで保有するが、日本の存在感は国際アートフェアではほとんど見られず、「巨大なビジネスチャンスが未だ手付かずのまま残されている」と警鐘を鳴らした。工芸品は彫刻的表現や大型作品とも相性が良く、アートとして提示すれば価格は国内基準ではなく〝国際市場の基準〟で評価され得ると述べた。
実際の取り組みとして、イタリア・ミラノで開かれたミラノ・フォーリーサローネでは備前焼、大館曲げわっぱ、越前和紙などをアート文脈で発信し、欧州の富裕層コレクターにつながった結果、実際の買い付けが生まれた事例を紹介。こうした「やり方を示す」取り組みが、国の政策面で地方創生2.0に結び付き、北前船交流拡大機構の活動も広域的な文化戦略の担い手として位置付けられつつあると述べた。
最後に二宮氏は、海外展開には地方から東京、海外へという従来型ルートではなく、地方と海外が直接つながる構造が必要と強調した。その際、歴史的な航路で地域を結んできた北前船のネットワークは、現代における広域ブランド戦略や市場アクセスのモデルになり得るとし、「有識者として今後も工芸分野の挑戦を支えたい」と締めくくった。

昆布が示す「日本のテロワール」、物語としての和食文化
続いて、老舗昆布問屋「奥井海生堂」三代目である奥井隆氏が登壇。奥井氏は、昆布が世界で注目される理由を「テロワール(風土)」と「クリマ(気候)」という概念から解説した。長野には昆布の流通経路こそなかったが、「海藻を高度に使いこなす和食文化自体が世界的に稀で、そこに外国人は強い興味を示す」と述べた。昆布はワインと同様に産地による格付けが存在し、北海道の浜ごとに品質が異なるという。「グランクリュに相当する一級品が実際にある」と語り、自社が最高級昆布を京都の料亭へ届けている取り組みを紹介した。また、昆布は海中で2年間育つため気候の影響を強く受け、「ヴィンテージ」と呼べる品質差が年ごとに生まれると説明した。こうした話を海外ですると、「ワインの文化として理解されやすく、関心を持ってもらえる」と強調した。
さらに、蔵で1〜2年寝かせる「熟成」によって風味が高まり、世界では「ヴィンテージ昆布」として評価が高まっていると述べた。平成元年産の古い昆布には著名シェフも関心を示し、「熟成という物語が海外で価値付けになる」と指摘した。奥井氏は、海外発信に欠かせないのは「理由づけと物語」であり、単に〝良い昆布〟と伝えるだけでは理解されないと説明。「自然環境、職人、地域性といった背景を語って初めて品質が伝わる。工芸も同じで、物語を付与しなければ海外市場に届かない」と述べた。自身のスペイン講演では、10年もののヴィンテージ昆布を試飲してもらい、来場者から高い反応を得た経験を紹介。JETROや農水省の協力を受け、世界のトップシェフとも交流が生まれたという。
最後に奥井氏は、「味噌・醤油・酒など『塩の道』に根ざした日本の食文化もワインに負けない深みを持つ。これを育てたのは北前船の交流圏だ」と述べ、歴史を踏まえた発信の重要性を強調した。

生活文化を基軸とした地域価値創出の必要性
内閣府地域活性化伝道師や総務省地域力創造アドバイザーなどを務める跡見学園女子大学准教授の篠原靖氏は、北前船交流拡大機構および地域連携研究所の活動に数年前から関わり始めて以来、「地域連携の取り組みが自分自身の課題として捉えられるようになった」と述べ、フォーラムの発展性を強調した。第36回北前船フォーラム、第7回となる地域連携研究所大会を振り返り、「規模と質の双方が着実に向上している」と評価。昨年の北陸大会で文化庁長官を招いた取り組みや、日本遺産・寄港地に認定された自治体で観光資源活用が進展している点を紹介した。
続けて篠原氏は、同機構が近年重点化している「伝統工芸品と食」の推進方針について触れ、「伝統工芸はどの市町村にも存在するわけではないが、地域の生活文化に根差した固有の『色』を高付加価値化する視点が欠かせない」と指摘。二宮氏の講演にもあったミラノ・サローネでの備前焼、大館曲げわっぱ、さらに本年の輪島塗の紹介事例を挙げながら、「日本の生活文化を国際市場へ橋渡しする動きは確実に広がっている」と述べた。さらに篠原氏は、こうした取り組みが政策面でも新段階に入りつつあると説明。参議院議員の横山信一氏(元財務副大臣)が今月14日の国会で伝統工芸品の販路拡大や事業継承支援を政府に求めたことに対し、高市総理が「地域未来戦略本部のもとで工芸など地場産業の付加価値向上と海外市場の開拓を強力に進める」と明確に答弁した点を紹介した。「これまで積み重ねてきた取り組みが、国全体の方針として可視化され始めた」と評価した。
その一方で、観光庁の「地域観光魅力向上事業」で工芸ツーリズムや食の高度化を支援対象として明記した昨年度補正予算に関し、「申請自治体が極めて限定的だった」と課題を示し、情報発信の不足も反省材料として挙げた。こうした背景から、寄港地間では新組織「北前船伝統工芸品ネットワーク」を立ち上げ、実践ノウハウの共有と横連携を強化する方針を明らかにした。
最後に篠原氏は、「伝統工芸や食を含む生活文化を、地域産業と観光の双方で再編し直す視点が不可欠だ」と述べ、北前船伝統的工芸品ネットワークがその推進力になるとの認識を示した。そして、「本日の議論を次の展開につなぐため、引き続き皆さまと共に歩みを進めたい」と、今後の取り組みへの意欲を語った。

地域の創意と広域連携が、観光の未来を決める
最後に、観光庁観光地域振興部長の長﨑敏志氏が来賓としてあいさつ。長崎氏は、「北前船は地域間交流そのものであり、現代の観光政策が目指す広域連携の根源的モデルだ」と述べた。また、観光庁が進める地域の稼ぐ力強化、観光DX、文化資源の活用などの政策を紹介しつつ、「地域が持つ創意と個性が結び合ったとき、日本の観光は世界で確固たる地位を築く」と強調した。松本開催の意義については、「海ではなく内陸で北前船を語ること自体が、連携の未来を象徴している」と述べ、地域文化の多様性を生かした観光戦略の深化に期待を寄せた。

交流が新たな地域の動きを生み出す
閉会のあいさつで登壇した東日本旅客鉄道(JR東日本)長野支社長の下大薗浩氏は、松本開催の意義に触れながら、「海と内陸という異なる文化圏が交わることで、新しい交流の可能性が生まれる」と語った。下大薗氏は、JR東日本が進める広域観光連携の取り組みに言及し、「鉄道は地域と地域、人と人をつなぐ現代の航路であり、北前船が果たした役割をいまの時代に引き継ぐインフラでもある」と述べた。特に松本エリアについては、「観光、文化、工芸など多様な魅力が凝縮されており、全国、そして海外との交流拠点としてさらに発展する可能性がある」と評価した。
さらに同氏は、今回のフォーラムで示された地域間連携の方向性に触れ、「沿岸の寄港地と内陸都市が互いの強みを共有し、ともに未来を描く姿勢こそが、地方創生における最も重要な要素である」と強調。「本日の議論が、地域を越えて広がる新たな協働の第一歩となることを期待したい」と述べ、閉会の言葉とした。

会場では参加者から大きな拍手が送られ、海から山へ、過去から未来へとつながる北前船ネットワークの可能性を確認しながら、フォーラムは幕を閉じた。

取材 ツーリズムメディアサービス編集部