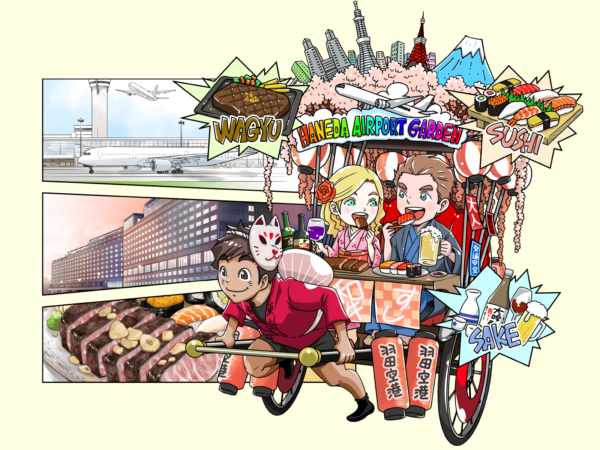観光は、人と人とのつながりが成功に導くと言われる。

そのため、すそ野が広く正解がない産業だ。地域には、そのような観光振興、観光に従事されている方々が数多い。
そのひとり一人をご紹介するシリーズ『人と人がつなぐ観光』の第4回目。東京都中央区で料亭を営む「つきぢ田村」の四代目、依田裕治(よりたゆうじ)さんだ。コロナ禍の最中に急逝した三代目の田村隆さんの跡を継ぎ、館の建て替えを経て、令和の田村を発展させるべく、その腕前を磨いている。
その味が歴史を紡ぐ
つきぢ田村は、初代・田村平治氏が戦後間もない1946年11月に築地本願寺の斜め向かいの地に開業したことに始まる。大手財界人たちが「この場所で美味しいものが食べたい」と発し、その言葉が後押しとなった。
その料理は、技術ばかりではなく、心を提供するものという教えが受け継がれている。そして、これらを凝縮した言葉が「五味調和」である。五味とは、「甘い」「酸っぱい」「苦い」「塩辛い」「香辛料の辛み」の五つの味を指す。『料理は五つの味がうまく調和し、食べるお客様はうまいと感じる』ものだ。また、『最高の素材のすべてを余すことなく使い切る』『熱いものは熱く、冷たいものは冷たく』という三つを大切にしてきた。それが、「西の吉兆、東の田村」と言われる由縁である。

二代・暉昭氏、三代・隆氏と代を重ねてきた。特に隆氏は、調理場に立つ傍ら、テレビ番組や料理学校の講師、料理本出版などを手掛け、一般に向けた食の普及活動も推進した。
しかし、コロナ禍の2020年12月、急性心不全で急逝。この大過によって、飲食業界は大打撃を受けている時期に、主を亡くし店を閉じるという選択肢もあったという。
また、老朽化した店舗も建て直さねばならず、大きな岐路、決断を迫られた。
裕治さんは、隆さんの長女と結婚した娘婿だ。幾度も家族会議が開かれ、大きな判断の末、跡を継ぐこととなった。一方、幸いにも世の中のすべてが底を打ったコロナ禍は、大きな転機となり、チャンスを与えてくれた。そして、2024年3月に新たな設えの建物、令和のつきぢ田村は完成し、再出発を迎えることとなる。
二代目が事務所にやってきた
さて、筆者は前職時代に初めて二代目・暉昭さんにお会いする機会を得た。その時にいただいた名刺には肩書がなく「田村暉昭」とだけ書かれていた。じっくりとお顔を拝見すると、よくテレビに出ている方だと興奮した覚えがある。
かつて、旅行会社と宿泊施設や食事施設の契約は、実際のお客様があって成立する。それ故、正式な契約がなくとも問題なく進められていた。しかし、この頃から不測の事態に対応するため、コンプライアンスが重視されるようになってきた。まずは契約ありきだ。その後、お客様をお送りするといったルールが必然となってきた。
一方、営業現場では、信用金庫友の会や募集型バスツアーなどで、既に多くのお客様がつきぢ田村の料理に魅了されていた。
「俺は、お宅の看板が欲しい」とおっしゃった暉昭さんの言葉は、今でも脳裏に蘇ってくる。
絵巻物のような招待状
旅行会社との契約は、その書類の多さも面倒なものである。しかし、お客様をご紹介することは、食事を提供いただくお店とお客様への責任でもある。そのため、最終的に現地を視察し、特にその味を吟味せねばならない。また、暉昭さんからは、「勉強のため、一度うちの料理を食べてみなさい」とおっしゃり、お帰りになった。
数日後、披露宴の招待状のような、かなり厚い封書が届いた。開けてみると、絵巻物のような手書きのものであった。これまで、数多くの契約を進めてきた。しかし、このようなお手紙を頂戴したのは初めてである。早速、お電話を差し上げ、訪問する日を決めた。なかなか出向く機会がない料亭への視察である。
少しばかり緊張しつつ、当日を迎えた。通常営業にご迷惑をかけないため、朝一番の訪問であった。当然、玄関は閉まっている。ぐるぐると周囲を回り、勝手口のインターフォンを押した。厨房の横を通り抜け、バックヤードからお客様がくぐる玄関に通された。これも初めての体験であった。
残念ながら、家宝にしようと思った招待状は、当日回収されてしまったので手元にはない。
昆布は、つきぢ田村の命
「困ったことに、昆布が取れなくなってきているんです」と、裕治さんは口を開いた。昆布は、つきぢ田村の生命線である。出汁を取るのに、昆布と鰹節、めじ節(キハダマグロ)を使い、独特の味わいを作り出しているという。その中でも昆布は、口に含むとその味わいに余韻を残すものである。

特に函館周辺で取れる真昆布を田村は使い、料理を作り出す。まさしく、伝統を守るための不可欠なものだ。田村らしさを語るこの出汁は、これから先も大切なものであり、入手できなくなると店の営業・料理に大きな影響を与える。
一方、日本人の舌の感覚も変化している。そのため、伝統的な出汁だけでは勝負できなくなってきているという。
3年前に先代を継ぎ、新たな館をオープンした時は、全力で取り組んでいた。昔を再現することに注力してきた。忠実にこれまでの出汁を再現することに努力した。しかし、一年経つと「我」が出てきた。昔を守りつつ、新しさを取り入れる。美味しい料理だけでなく、楽しい料理を提供することが大切だと思うようになってきた。周りからは賛否両論も多数、厳しい言葉に勇み立つ毎日であった。
会社勤めから「食」の世界へ
さて、裕治さんは現在42歳だ。大学を卒業し某コンビニエンスストアの営業職として活躍していた。就職活動の時に田村の娘さんと知り合い、交際を続けていた。「食」の世界は縁もゆかりもない世界だった。
紆余曲折もあった会社勤めのある日、結婚を決めた裕治さんは、初めて義父・隆さんに会うこととなった。まず、「継ぐ気があるのか」と問われたという。お父さんと呼んだのは、この時ともう一度と述懐する。娘婿である前に「師匠と弟子」という形が生まれた。

その後の会社勤め3年間で優秀な成績を残し、29歳の時に料理の道へ入る。そして、9年間、隆さんの下で修行し、その技を学んできた。
会社時代に「分析」することの重要性を学んできた裕治さんは、「食」にも分析を取り入れるようになった。まさしく「理系脳」と形容できる。
フランス料理は化学的なレシピによって作られる。また、料理は因数分解で方程式が確立すると開花する。このような斬新的な手法を採用した。今では、伝統的な和食に中華や洋食を取り入れた料理が提供されている。
ちなみに、和食でナタデココを初めてデザートに取り入れたのは、田村の先代たちである。
お前が美味しいというものを出しなさい
2019年のコロナ禍が、親子の関係をより緊密にすることとなった。ある時、隆さんが「本気で継ぐ気があるのか」と聞いたという。裕治さんは、すぐに「はい」と答えたものの、この言葉は、田村の看板を背負う重圧から逃れても良いという親心であることを後から知った。
コロナ禍の最中にあっても隆さんは、通常の仕入を行なっていた。「お客さんもいないのに、魚を仕入れる必要はない」などと揶揄された。しかし、これは魚屋をはじめとする仕入先を守るためのこと。そして、田村自身を守るためであった。

~奥は三代目愛用の包丁が祀られている
また、当時、和食の世界でもオープンキッチンが主流となってきた。そのため、あらゆるお店を視察した。しかし、その時の違和感は、お客様の眼前で料理の神髄を見せるだけで、おもてなしに欠けていることだった。
「お父さんと、田村でカウンター割烹をやりたい」と伝えたのは、この頃である。そして、隆さんはその場で建設会社に電話をかけ、娘婿の想いに応えてくれた。
隆さんは、良く落語を聞きに行くことが多かったという。まさしく、お客様の前に料理を提供し、楽しく食べていただくために「間」を学ぶためであった。そして、新しくなったらカウンターで「お前が美味しいというものを出しなさい」と教えてくれた。隆さんこそ、カウンターキッチンをやりたかったのだと感じた。
四代目の誕生
一方、コロナ禍は多くの仲間たちを失う結果にもなった。とある料亭が閉めることを受けて、東京の料理人たち(芽生会)が集まる機会があった。その宴は、重鎮たちの部屋と若手の部屋が分かれていた。師匠である隆さんは、その若手の部屋で赴き、ひとり一人にお酒を注ぎながら、「うちの四代目です。これからもご指導くださいますよう、お願いいたします」と頭を下げていた。
お酒を注がれる若手料理人たちは、恐縮しつつも裕治さんを認める結果となっていた。それまで、仲間の中では裕治と名前を呼ばれていた。しかし、それは隆さんが裕治さんが高慢な気持ちにならないように、あえてお願いしていたことだった。師匠であると同時に親であることの想いといえる逸話だ。この日、この瞬間に「つきぢ田村」の四代目は誕生した。
これからの飲食業界、つきぢ田村が目指すもの

団体も受け入れることができた大箱の料亭つきぢ田村は、現在、上層階をマンションに変え、その2階部分に個室とカウンターを有する店舗となっている。この形に変えるために、多くの諸先輩方にご指導や助言をいただいた。
しかし、選ぶのはたった1つである。不義理を感じつつも、あの時、父と話をした「カウンター料理」に固執した。
カウンター割烹を成就させるためには、話術もしかりだが、料理の説明などを主人自ら語ることが一番重要である。そのため、その成功している事例を学ぶために修行に出た。この修行には、田村ゆかりの料亭や名だたる割烹で学ぶべきとの意見もあった。
しかし、裕治さんが選んだのは、青森県八戸市の「銀波」という割烹料亭である。ご主人の城前孝史(じょうまえたかし)さんは、隆さんが懇意にしていた後輩である。そして、その話術から「城前劇場」と称えられている。
割烹 銀波(https://www.ginpa.jp/)
カウンターで料理を提供するには、話術や知識、料理の技が卓越していることが必要となる。そのために、現地では魚市場や野菜などの農家へも足を向けた。たった一年の経験ではあるが、今では、そこからも食材を仕入れさせてもらっている。
四代目は、「先付は、料理人からのメッセージ」と語る。お客様は、「この料理人は、どのような食事を提供してくれるのか」と興味津々でお店を訪れる。そして、和食でありながらフレンチの先付が出てくる。一方、次に八寸は古典的なもの。出汁は田村の伝統を守ったものを使う。五味調和の伝統と新たなチャレンジを融合させる料理こそ、令和の田村の姿を作り上げている。
次につながる和食料理人の養成

今や和食料理人の成り手が少なくなってきているという。また、教える側も高齢化し、伝統継承に赤信号が灯るようになっている。これまで、つきぢ田村は全国に卒業生を擁し、「田村会」なる組織も構築してきた。卒業生たちが年に一度顔を合わせ、その技を磨き上げることも行なってきた。
そのため、和食の世界を未来につなぐ養成学校の復活を望む方々も少なくない。斯界のリーダーたる「つきぢ田村」の再出発には、四代目自らが継続した「学び」を実践せねばならない。
楽しい料理を提供し、料理に夢中になっていると24時間寝る暇がないと語る。10年後の田村は、どのような形になっているか想像もできない。しかし、どのようになっていても、それが正解だと、四代目は目を輝かせながら語っていた。
何もわからない世界の飛び込み、多くの軋轢もあったという。自分の弱さを知っている者は、人に優しくなれる。そのようなつきぢ田村の四代目のご活躍を、引き続き応援していきたい。
つきぢ田村
東京都中央区築地2-12-11
(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8
取材 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長(2026年2月9日)





.jpg)