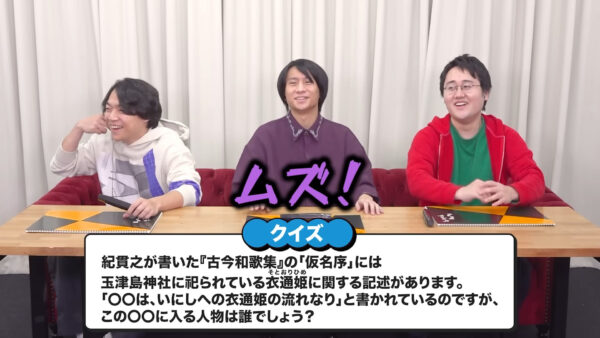鏡のように穏やかな瀬戸内海が終わりを告げる場所。黒い半島の間に輝く海峡、一本の筋が見えてきます。海峡に架かる関門橋です。
関門海峡は下関と門司との間、本州と九州を結ぶ海峡です。源平合戦でも名高い壇之浦と和布刈(めかり)間の幅600m、国内でも有数の早瀬です。最深部は47m、大潮の時には最大10ノットという速さで海が動きます。
海峡が時代を変えてきた
古くから「ここを制する」ものは、世の中を支配するとも言われました。源頼朝は戦勝によって、鎌倉幕府を建てました。また、明治維新には下関戦争など、海外列強との戦争となった場所でもあります。
第二次世界大戦下の1942年に関門鉄道トンネルは開通しました。その後、関門国道トンネル(1958年)や高速道路の関門橋(1973年)が供用開始されます。そして、新幹線の新関門トンネル(1975年)と交通の利便性が図られてきました。

地上に降り立ってみると、赤間神宮や春帆楼、火の山公園などの史跡があります。目を凝らすと機上からも手に取るように見えてくるのが不思議です。しかし、その当時の人々は、地形を俯瞰することはできません。もし、俯瞰することができれば、もっと素晴らしい戦略戦術を繰り出していたかもしれません。
隠された歴史を目の当りに
さて、火の山公園は、山麓の壇之浦からロープウェイで標高268.2メートルの頂上に赴くことができます。1890年に砲台が設置された下関要塞。そのため、終戦まで民間人は踏み入ることができなかった場所です。山頂のこの公園は1956年に一般開放。また、展望台が1973年も開園しています。残念なことに展望台は、現在リニューアル工事で閉ざされています。

そして、関門橋越しに見る門司港の夜景と遠方の彦島の姿は、1000万ドルの夜景と称されています。
海上交通の要衝、下関と対岸の門司は、日本近代化における重要な拠点でした。当然、さまざまな産業が集約されました。「ノスタルジック海峡」と呼ばれる関門海峡は、双方を連携させた観光コンテンツ化を進めています。
ただ、広島や博多という大消費地から離れていることはマイナスポイント。これを打破するには、より効率的な仕掛けが必要な場所とも言えます。
歴史にフグが刻まれた旬感

例えば、唐戸市場に揚げられる「ふく」に代表される海産物を活用した「食」のコンテンツ作り。
(下関では、フグを「福」にかけ、「ふく」と呼びます)
また、毛利家ゆかりの「長府」の町並みや近代化を推進した建造物などに触れる歴史的観光。
それは、ここでしか体感できないコンテンツと言えます。そして、コンテンツを充実させることによって、地域への滞在時間を増やす取り組みが必須と考えます。

現在、唐戸地区は、門司港までの航路の桟橋や下関水族館「海響館」などが一体となっています。カモンワーフと商業施設が中心となり、賑わいを拡げています。
また、かつての貿易の中心地でもあり、レトロな建物の代表格、旧秋田商会ビルも観光情報センターとして再生しています。町歩きのコンテンツも徐々に充実し、回遊性を高めているところです。
そして、関門連絡船に乗船し、関門海峡の潮流の速さを体感することも楽しいものです。また、関門人道トンネルでは、自らの足で歩いて門司に渡ることもできます。
-683x1024.jpg)
(現・下関観光情報センター)
海上交通の重要さを学び、トンネル建設の技術力に触れる。まさしく、下関は、唯一無二の観光コンテンツを保有する素敵な町なのです。
さあ、少しばかり足を延ばして、下関の歴史に触れてみるのはいかがでしょうか。
寄稿者 観光情報総合研究所 夢雨/代表
(これまでの寄稿は、こちらから)





円形.jpg)