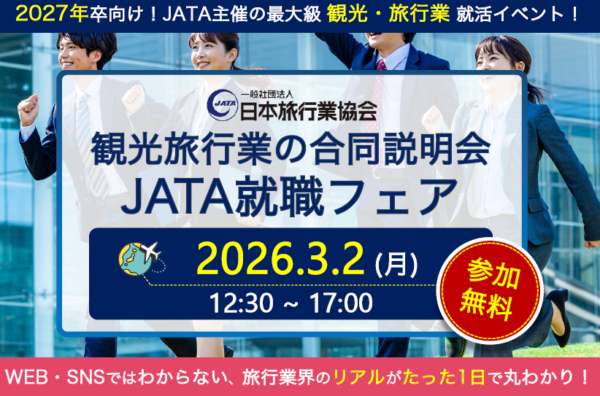前編(https://tms-media.jp/posts/57458/)は、宿泊施設の国際的なエコラベルであるグリーンキー(Green Key)の基準や仕組み、取得の現状を説明したほか、持続可能な開発という概念の成り立ちについて紹介した。後半では、持続可能な観光に向けて環境の重要性などを伝えていく。
なぜ環境が観光にとって重要か
まず、現在の持続可能な観光の定義をみてみよう。

図表にあるように、訪問客、業界、環境および地域社会のニーズに対応しつつ、現在および将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮に入れた観光(出典:UNWTO)とある。この経済、社会・文化、環境が三位一体で示されているが、これはそれぞれの国・地域、観光形態によっても重要度や優先度が変わってくる。前編で紹介する東京女子大学教授・藤稿 亜矢子氏も指摘されているが、砂漠化などで水資源の枯渇に苦しむ地域や地球温暖化で海水面が上昇し国土の保全の危機に直面しているような島嶼(とうしょ)国と、限界集落化しコミュニティの維持の危機に瀕している地域では重点分野も当然変わってくる。わが国の観光立国推進基本計画(2024年)においても、 (以下引用)
観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針
世界的に「持続可能な観光」への関心が高まっている。自然、アクティビティに対する需要も高まりを見せ(中略)この世界的潮流を捉える必要がある。世界的にも関心の高まっている「持続可能な観光」とは、単に環境にやさしい旅行形態ではなく、いわば「観光 SDGs」であり、「住んでよし、訪れてよし」の観光 地域づくりに重要な、経済・社会・環境の正の循環の仕組みにつながる観光の基本的なあり方である。地球環境に配慮した旅行を推進していくことに加え、地域において、自然、文化の保全と観光とが両立し、観光地・観光産業が付加価値を上げ収益力を高め、観光振興が地域経済への裨益と地域住民の誇りや愛着の醸成を通じて 地域社会に好循環を生む仕組みにより、地域と観光旅行者の双方が観光のメリット を実感できる観光地を持続可能な形で実現していくことが、従前にも増して重要と なっている。(中略) インバウンド回復と国内交流拡大の双方を支える持続可能な観光地域づくりを推進する。(引用終わり)
とある。この巻頭で環境に触れてはいるが、中身を見ていくと、どちらかといえば持続可能な観光地域づくりにフォーカスしたうえで経済、社会・文化的側面に主軸を置いておりこの後に出てくる具体的施策には環境的側面を見出すことはできない。しかしながら環境的側面は無視でできないリスクを抱えていることを筆者はあえて強調しておきたい。
顕在化した環境リスク
自然環境が与える恩恵は、前述の藤稿教授がわかりやすくまとめてくれている。
(下記参照 筆者にて同氏著書図表を編集・PPT化)

世界銀行の試算によると世界のGDP44兆ドルの半分は天然資源に依存している。
今やこうした恩恵が脅かされており生態系の破壊が環境に与える影響は図り知れず、少し遡るが2020年(これが最新版)の世界経済フォーラムのレポートでは、

人間の活動がいかに生態系を脅かしているかを示している。
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/new-nature-economy-nature-risk-rising.html (日本語版)


その上で、同レポートでは「自然への依存度は産業やセクターによって大きく異なる。自然消失が第一産業にもたらすリスクは分りやすい一方、第二次産業や第三次産業への影響もまた重大なものとなり得る。例えば化学品、素材、航空・旅行・観光、不動産、鉱業・金属、サプライチェーン・輸送、生活消費財、ライフスタイルの6つの産業に関しては直接的なGVA(粗付加価値)のうち自然に強く依存しているものは15%に満たないものの、サプライチェーンを通じた『隠れた依存性』が存在し、これら6つの産業のサプライチェーン由来のGVAの50%超は自然に中~高程度に依存している」としている。

また、今年発表された世界経済フォーラムの「The Global Risks Report 2025」においても、向こう10年のリスクの上位は環境起因のリスク(図表の緑色)が独占した。
https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/

こうした結果が何をもたらすかは自明であろう。わが国に置き換えてみよう。
もうおわかりだろう。異常気象のみならず、観光を支える自然景観や、訪日旅行客の最大の楽しみの一つでもある日本食を支える農林水産業、里山といった生態系などに計り知れない打撃を被る可能性を十二分に秘めているのだ。われわれ観光産業に関与する人間は改めて環境保全への視点をもつべきであろう。また食を支える農業においても農業従事者の問題もあるが、化学肥料や農薬による土壌汚染から昆虫や鳥など生態系を保全する取り組みもまた重要であろう。わが国の有機農業の耕地面積は農水省の資料によるとわずか0.2%、中国の半分といったあり様だ。

https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2019/attach/pdf/190726_01.pdf
農業における循環的生態系を破壊する遺伝子組み換え品種といった問題も生じてきた。最後になったがこの遺伝子組み換え種子の問題については超セレブリティに登場してもらおう。英国のチャールズ国王である。国王は皇太子時代から農園を所有し自ら土をいじり有機農業や牧畜を推進してきた。国王の農園で加工されたジャムやクッキーなどは英国の高級スーパーで販売されている。

国王は皇太子(Prince of Wales)であった1998年に英紙 デイリーテレグラフに自らの経験を踏まえて寄稿をしている。タイトルは「The Seeds of Disaster」(種子の災禍)だ。原文は英文だが一読をお勧めしたい。
https://www.royal.uk/clarencehouse/speech/article-prince-wales-titled-seeds-disaster-daily-telegraph
未来の国王(当時)による未来への警鐘はまさに地球が持続可能であることを願ってだろう。以下日本語(抄訳)を付記しておく。
従来の植物品種改良と遺伝子組み換え植物品種改良の根本的な違いは、後者では、ある種の植物、バクテリア、ウイルス、動物、魚の遺伝物質が、自然には交配できない別の種に文字通り挿入されることである。このような技術の使用は、倫理的にも実際的にも極めて重要な問題を提起している。
私は常々、農業は自然と調和しながら進むべきだと考えてきた。だからこそ私は12年前、人工的な農薬や肥料を使わない有機農法に踏み切ったのだ。私自身の経験から、有機農法が経済的に実行可能であること、環境的・社会的に幅広い恩恵をもたらすこと、そして最も重要なことは、消費者が自分たちの食べる食品を選択できるようになることだと確信している。
しかし、オーガニック食品の売り上げが急増している今、集約農業の発展は、私たちが口にする食品に関する基本的な選択肢を奪い、私たちの食と環境の将来について、まだ答えの出ていない重大な問題を提起している。遺伝子組み換え(GM)作物は、伝統的な植物育種法の延長線上にある技術によって収量を増加させるという、本質的に単純な開発として紹介されている。残念ながら、私はこれを受け入れることはできない。
伝統的な植物育種と遺伝子組換え植物育種の根本的な違いは、後者では、ある種の植物、バクテリア、ウイルス、動物、魚の遺伝物質が、自然には繁殖し得ない別の種に文字通り挿入されるという点である。このような技術の使用は、倫理的、実際的に極めて重要な問題を提起している。
私は、この種の遺伝子組み換えは、人類を神の領域、そして神のみに属する領域へと導くものだと信じている。非常に有益で特殊な医療用途を別にすれば、私たちは生命の構成要素を実験し、商業化する権利を持っているのだろうか? 私たちは権利の時代に生きている。私たちの創造主にも権利があってもいいのではないだろうか。
私たちは、このようにして育種された植物を放出することが、人間の健康やより広い環境に対して長期的にどのような結果をもたらすかを知らない。私たちは、これらの新しい植物が精力的に試験され、規制されていることを保証されているが、その評価手順は、遺伝子組み換え作物が安全でないことが示されない限り、その使用を停止する理由がないことを前提としているようだ。BSEをはじめとする、「安価な食品」のために人為的に引き起こされた災害の教訓は、予期せぬ結果こそが最大の懸念材料であるということだ。
遺伝子組み換え作物は、農薬の使用を減らすことができると言われている。たとえそれが本当だとしても、それがすべてではない。それが考慮されていないのは、農業システムが生態系や社会に与える影響である。例えば、これまでに販売された遺伝子組み換え作物のほとんどは、同じメーカーから販売されている広範な除草剤に耐性を持つバクテリアの遺伝子を含んでいる。
この除草剤を散布すると、畑の他のすべての植物が枯死する。その結果、基本的に無菌の畑となり、野生生物に食料も生息地も提供しない。これらの遺伝子組み換え作物は、野生の近縁種と交雑し、除草剤に耐性を持つ新しい雑草を作り出し、他の作物を汚染する可能性がある。
遺伝子組換えナタネの遺伝子組換え作物が、1マイル以上離れた在来作物に混入していたことが判明した。その結果、慣行栽培作物も有機栽培作物も脅威にさらされ、その脅威は一方通行となっている。
遺伝子組み換え作物はまた、独自の農薬を生産するように開発されている。このため、抵抗性の昆虫が急速に出現すると予測されている。さらに悪いことに、そのような農薬生産植物は、害虫だけでなく有益な捕食昆虫も殺すことがすでに示されている。ひとつの例を挙げると、スノードロップの遺伝子をジャガイモに挿入すると、そのジャガイモはミドリムシに耐性を持つようになったが、ミドリムシを捕食するテントウムシも死んでしまった。また、コーンボーラーを捕食する天敵であり、農地の鳥の餌でもあるヒメシロヒトリは、遺伝子組み換えトウモロコシで育てた害虫を食べると死んでしまった。
莫大な面積があるにもかかわらず、遺伝子組み換えの商業用作物を監視し、何が起こっているかを正確に把握することは、公式には義務づけられていない。単一品種の作物への過度の依存から生じた過去の農業災害を考えてみてほしい。10年以内に、大豆、トウモロコシ、小麦、米などの主食用作物の世界生産の事実上すべてが、消費者の圧力がない限り、数種類の遺伝子組み換え作物でまかなわれるようになる可能性は十分にある。
イングリッシュ・ネイチャーをはじめとする公的機関は、遺伝子組み換え作物を広範囲に導入することが環境に悪影響を及ぼす可能性について警告を発している。そして、これらの作物のうち少なくとも一つの使用を一時停止するよう求めている。
一度環境中に放出された遺伝物質は回収できない。大きな問題が発生する可能性は、一部の人々が指摘するようにわずかかもしれないが、もし何か悪いことが起きれば、私たちは自己増殖する一種の公害を一掃しなければならないという問題に直面することになる。この問題をどのように解決するのか、また誰がその費用を負担するのか、そのアイデアをもっている人がいるとは思えない。
私たちはまた、遺伝子組み換え技術が『世界を養う』のに役立つとも言われている。これは私たち全員にとって基本的な関心事である。しかし、この技術を管理する企業は、世界の最貧困層に製品を販売することで十分な見返りを得ることができるのだろうか? また、基本的な問題が常にそれほど単純であるとは思わない。
食糧不足が問題なのであって、食糧を買うお金がないことが問題なのではない。たとえば、労働力と経営技術を最大限に活用しながら天然資源を節約する技術を用いれば、伝統的な農業システムの収量を2倍、さらには3倍に増やすことができることが、最近の研究で明らかになっている。
遺伝子組み換え技術を使う必要はあるのだろうか?テクノロジーは人類に多大な恩恵をもたらしたが、特に食料、健康、環境の長期的な未来といったデリケートな分野においては、技術的に可能なことを確立することに全力を注ぐあまり、それが私たちのなすべきことなのかどうか、まず立ち止まることなく考えることは危険である。
私は、科学や規制だけでは効果的に対処できない原則的な問題について、広く国民が議論することを通して、立ち止まってその問いを立てるべきだと考えている。食料供給と安全保障、農村の雇用、環境保護、景観といった観点から、私たちが農業に実際に何を求めているのかをまず検証してから、その目的を達成するために遺伝子組み換えが果たせるかもしれない役割を検討したほうがいいのではないだろうか。
もちろん、これらの重要な問題については、私たち全員が自分自身の考えを決めなければならない。私自身は、遺伝子組換えによって生産されたものを食べたいとは思わないし、そのような農産物を家族やゲストに故意に提供することもない。多くの人々が同じように感じていることを示す証拠も増えている。しかし、このような考えが広く浸透しつつあるのであれば、食物連鎖の進展に基づく包括的な表示制度に裏打ちされた、遺伝子組み換え製品の効果的な分別がなされない限り、私たちの原則を実践することはできない。
これが不可能であるとか、無関係であるという議論は、単に信用できないだけである。消費者が遺伝子組換え原料を含む製品を食べるかどうかについて、十分な情報を得た上で選択できるようになれば、消費者は自分の嗜好について直接的で紛れもないメッセージを送ることができるようになる。製造業者、小売業者、規制当局が、このようなことが実現できるよう、責任を負う用意ができていることを願っている。
おわり。
※メインビジュアルは、砧公園 東京都世田谷区の桜(筆者撮影)
寄稿者 中村慎一(なかむら・しんいち)㈱ANA総合研究所主席研究員