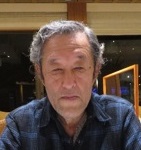横浜みなとみらいにある横浜美術館(横美=写真)が2025年2月リニューアルし、オープン記念の「おかえり、ヨコハマ」展を6月2日まで開いている。港都・横浜にふさわしい歴史と発展の息吹を表現し、収蔵品を中心に展示する。横浜市歴史博物館などの協力も得て展開する第1章「みなとが、ひらく前」は縄文、弥生時代に遡り土偶や土器などを展示。次いで「みなとを、ひらけ」は開港時代、鉄道開通の光景などを繰り広げ、「ひらけた、みなと」で輸出向け産業の曙を示す陶磁器など。
第4章は美術界発展のさなか襲った関東大震災の惨状を示す「こわれた、みなと」。さらに、戦争の足音を「また、こわれたみなと」で表現。「あぶない、みなと」で戦後占領が長引き混乱する横浜を振り返る。横美紹介の「美術館が、ひらく」と続き、最後の第8章「いよいよ、みなとがひらく」で未来へ希望を探るという。収集する1万4千点を超すコレクションは「みんなの宝物」として常時200~300点を展示し若手作家の支援や教育普及にも努める。
みなとみらいの高層ビル街に石造りの豪壮な外観が目を引く
1989年11月3日に開館した横美は2021年からの大規模補修を昨年終え全館で4年ぶり再開となり、賑わいを取り戻して「お帰り横美」の思いを込める。開館から30年以上経過した施設や設備の老朽化に対し長寿命化を図る。電気、空調など設備を更新し、外壁などの経年変化による劣化の改修、エレベーターの増設、エスカレーターの更新、多目的トイレの増設などバリアフリーの工事を進め、美術品や資料の収蔵庫を増設、美術図書室の移設で利便を図った。みなとみらいの高層ビルが立ち並ぶ中、憩いを求めて人びとが集い、緑に囲まれた横美は、石造りの豪壮で左右対称の外観が目を引く。
ガラス張りの大天井から降り注ぐ自然光

館内に入るとガラス張りの大天井で自然光が降り注ぎ、吹き抜けの開放的なエントランスホールが広がる。リニューアル整備で特に力を入れた無料スペース「じゆうエリア」はオリジナルの淡いピンク色の丸い机や椅子が並びカフェの飲み物もいただきながら寛ぎの空間となっている。多種多様な人びとが集い、共に過ごすための「広場」だ。
最大の見せ場である大階段で展開するバリアフリーのアートは圧巻だ。入口の最下段から階上の展示室まで車椅子で移動できるスロープを新設し、所どころに車椅子アートを配置した檜皮(ひわ)一彦「walkingpractice」の作品。自ら車椅子利用の檜皮さんは「大変苦心苦労してデザインしスタッフと作った。さらに改善したい」と意欲を見せる。アート表現として作ったスロープだが実用にもなり「おかえり、」展後も残せたら、と思わせるほどの大作だ。

みる(展覧会)、つくる(アトリエ)、まなぶ(美術図書室)の3本柱
ミュージアムショップはMYNATE(みなと)と名付け「地域の文化と本のある店」として市内の作家や企業、クリエーターの作品、文化を楽しむグッズ、横浜の出版社発行の情報誌「濱手帖(はまてちょう)」などを販売する。カフェも新装した。美術図書室は24万冊を超す国内外の展覧会カタログや専門書、雑誌、映像資料を所蔵し、だれでもいつでも無料で気軽に閲覧できる。みる(展覧会)、つくる(アトリエ)、まなぶ(美術図書室)の3本柱を掲げて子どもたちの来館を歓迎し「ゆっくりあるこう」「さわらないでみよう」「ちいさなこえではなそう」「おきにいりのさくひんをみつけよう」などと分かりやすく示した案内冊子「こどもミッションシート」を配りマナーも啓蒙する。

蔵屋美香館長は「アートを通して新しいものに出会う」「みんなが生きる力を得る」そんな場所にしたいと願う。長い休館中に、これからの美術館の姿について検討プロジェクトを立ち上げ、いまやどの美術館も博物館も求められる多様性という課題に「横浜らしいやり方で応える」と言う。

世界に開かれた貿易港の横浜に様々な人が訪れ、新しい文化や情報がもたらされ、そうした中で、新しいものに出会う不安や驚きに対し、異なる声にも柔軟に耳を傾けると自分の世界が大きく広がり、異なる空間の相手もこちらに向かって「共にいるための空間が生まれる」と考える。そもそもアート作品は、異なる時代や地域に生きる人びとが「いろいろな考えに基づいて」作り、一つの作品の中にも「多種多様なメッセージが込められ」、多様なものの見方に触れる手掛かりに「アート作品ほどふさわしいものはない」と強調する。こうした思いを実現するため、多様な人びとが気軽に美術館へ足を運び、思い思いにくつろげるよう、ベビーカーや車いすでいっそう快適に館内移動できるよう、ハード面の整備とともにソフト面でも収集する作品や書籍、展覧会の企画、ワークショップやトークイベントなど理想を求めていく。期待してほしいと。
(写真・文 林 莊祐)