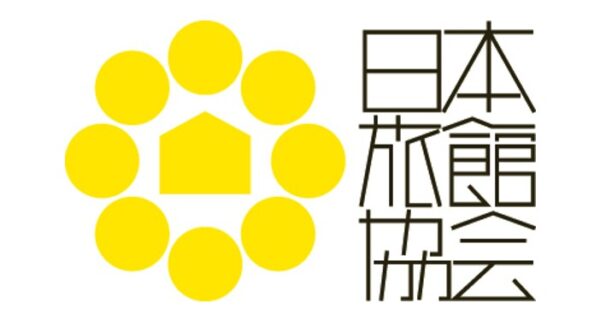京都駅の南側は、一部の例外を除き、有名観光地が少ない。特に近鉄と京阪電車が走っていない場所は、完全に観光空白地域となっている。その中でも、ここ城南宮は、正月が終わると一気に観光客が増えるお宮だ。そして、その歴史は、白河天皇が鳥羽離宮を造営し、その一角に御宮を建てたことから始まる。御所の裏鬼門に位置する場所ゆえ、方違(かたたがえ)の御社と呼ばれた。そのため、当時の貴族たちの方位除けの神社としても繁栄した。
しかし、天皇家や貴族たちの住居から離れたこの場所は、何度となく主戦場となってきた。その代表例が、応仁の乱や江戸末期の鳥羽・伏見の戦いである。戦いの度に荒廃した土地であったが、終戦後、徐々に復興を果たし、現在の姿に復元された。
幽玄さを目の当たりに
さて、春にはまだ早い時期、神苑には梅や椿の花々が咲き誇る。雨の降る日は、地面に落ちた椿の花びらが儚さを映し出す。また、晴れた日は、枝垂れ梅がキラキラと光を透かす。昨今、SNSでつぶやかれ、これまで以上の観光客が訪れるようになった。「落ち椿の向こうに枝垂れ梅」という定番の撮影スポットは、長蛇の撮影待ちが起きる。
一方、ゴールデンウィーク中には、平安時代の宮中イベントが行われる。庭園に流れる一筋の鑓水に、歌を流す宮中行事「曲水の宴」が開催される。雅やかな行事、京都市内には、まだまだ知られていないモノ・コトがたくさん溢れている。やはり、悠久の都、奥が深い。
(2021.02.27.撮影)
(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8
取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長





.jpg)