■消え去る景色が語ること
冒頭の写真は、「大洲川まつり花火大会肱南(こうなん)河原編/2019年8月4日撮影」
■わが町を語るとき
それは、自らの生い立ちや家族との思い出、学友たちとの交流。そして、社会人としての活動など、さまざまな成長の記憶や環境が絡み合って形成されるそれぞれの「ふるさと感」が醸し出すのだろう。
だが、記憶の片隅にしまわれた「名場面」があるとしたら、その「ふるさと感」はとても大切な宝物になるのかもしれない。
私は、「地域創生撮影」などと訳の分からんことを唱えて、自らの育った町を徹底的に取材撮影している田舎の写真家だ。しかし、自らが撮影した「写真」で、愛媛県大洲市を観光まちづくりの表舞台へと20年の歳月をかけて押し上げた経験値は、写真で地域を表現し情報として拡散させるだけの「視点」と「独創的表現力」のエネルギーになっている。それ故、国内では私くらいのもんだと思っている。
■2019年8月4日に撮影した一枚の写真
話は随分遡るが、現役時代の私は地域の観光まちづくりの事業基盤形成の責任者&プロデューサーとして「大洲川まつり花火大会」の打上プロデュースを12年にわたって担当していた時期があった。しかし、この川まつり花火大会は、大洲市が藩政時代から引きずっている歴史的事情の象徴でもあったのだ。
明治維新を迎え、「廃藩置県」の際に妙なことになってしまう。城下を分断する「肱川(ひじかわ)」南側を肱南(こうなん)地域と言い、北側を肱北(こうほく)地域と称する。そして、大洲城があり城下町を形成している肱南地域を「大洲町」とし、肱北地域が「大洲村」とされた。そのことが後に双方合併して大洲町になって以降、色々な催し物を開催する際に、水面下で起こる地域住民による綱引きがさまざまな影響をもたらすこととなってしまった。このことは、時代も令和に変わった今日でも潜在的に存在している。それ故、大洲における街づくりにおいては、しっかり認識しておかなければならない重要な地域事情でもある。
■大洲の花火大会
毎年8月3日は肱北河原で、8月4日は肱南河原で開催されていた。これは、この地域が抱える歴史的事情の象徴のようなものだ。そのため、私の現職時代にも毎年のように花火大会の一本化が叫ばれては消えていた。
2019年8月4日に撮影したこの花火大会の写真は、後に訪れる国家の危機とまで言われた「コロナ禍」によって肱南河原で開催された最後の花火大会となった。
今日では、花火代金の高騰とスポンサー料が減少していることから行われなくなった「名物仕掛け花火」だ。そして、この場面は「鵜飼い」の屋形船がシルエットのように写り込むことから、大洲城とセットで撮影できる8月3日開催の肱北河原とは、また違った人気を誇る花火大会の象徴的場面だったのだ。
■これからのこと・・・
さて、燃料費の高騰、令和の米騒動、人口減少が招く地域力の低下・・・などと挙げればキリはない。しかし、大切にすべき日本古来の伝統文化や独特の仕組みを「デジタル化」の名の下に、軽んじてきたツケがいよいよのしかかる時代となってきている。
一枚の写真が語る「消え去った風景」は、この町にとってかけがえのない歴史と刻まれた軌跡でもある。そのような場面を特に力を入れて撮影に臨んでいるが、「あの時、ボクが観た景色」は百年先の皆さんに遺し伝えたい私の「ふるさと感」でもある。
コロナ禍終息以降、「夏の陣」と「冬の陣」の2回に分けて打ち上げられていた大会も、今年からは「冬の陣」は取りやめとなってしまった。致し方ない諸般の事情ではあるが、せめてあの時はこうだったといずれ語り合うことができるよう、カメラを持てる間は撮り続けていくのが、地域における写真家としての私の役割だと考えている。

(これまでの寄稿は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=14
寄稿者 河野達郎(こうの・たつろう) 街づくり写真家 日本風景写真家協会会員










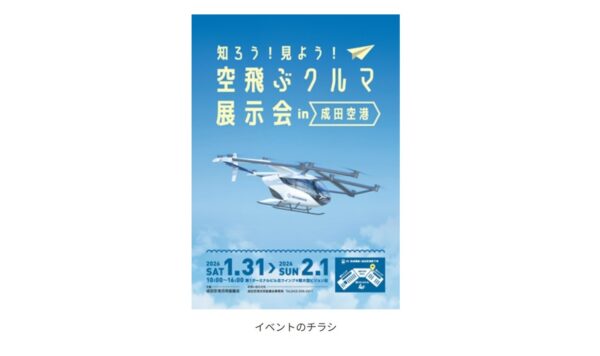

記事を拝読し、改めて素晴らしいご活動だと感じました! 河野さんの思いを知ると一枚のお写真から様々なメッセージが感じられ、一層心に響きます。 これからもご活躍を陰ながら応援しております!