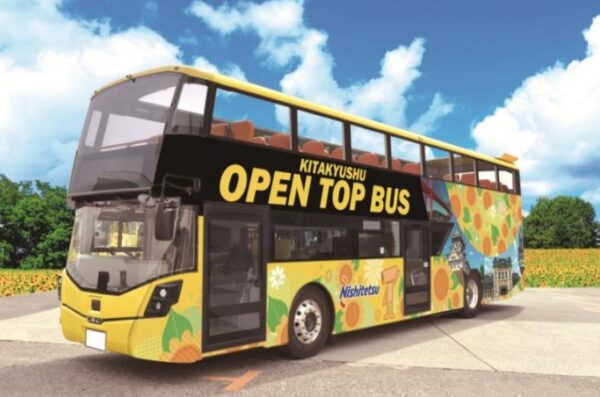子ども時代、物心ついた頃には自宅前をSLが汽笛を鳴らし黒い煙を吐いて走っていた。今から60年以上も前の話ではあるが、どこへ行くにもこのSLに乗って連れて行かれたものだ。そして、夏休みともなれば、朝一番の機関車の汽笛で目が覚める。もたもたしていたらお袋にケツを叩かれラジオ体操へと追い出されるのだ。
残念だが、その当時のSLの写真等はおやじがまめに整理して残してくれているアルバムをめくってみても残っていない。私の脳裏に思い出の名場面として記録されているだけだ。

■底辺に息づく思い
本格的に写真を仕事として撮り始めた2000年頃。まだ撮影の力量もままならず、とてもそれで生活が成り立つなんてレベルではなかった。しかし、私が流行り始めたパソコン操作に興味があり、嫌いではなかったことが功を奏した。
撮った写真を作品化して多くの方々にご覧いただくということとよりも、地域情報として全国へ世界へ発信して、隣町の内子町に追いつきたいという仕事の方向性を私は大切にした。そして、撮影の基本に置いたのがこの町を走る汽車だった。
大洲盆地のド真ん中へ流れ込む肱川は、南側に位置する西予市宇和町との境界付近を源として約103kmかけて伊予灘へと向かう。河口から約18km付近には予讃線の肱川橋梁が肱北(こうほく)から肱南(こうなん)へと渡っており、これが城下町大洲を演じるドラマの重要な舞台となっているのだ。
鉄道が走る城下町の風景、汽車が音をたてて鉄橋を渡る景色等々と色々な表現がある中で、静止画である写真でこの町を感じ脳裏にふるさとを思い浮かべ、喧噪の世界から逃れて「帰りたい」と想いを寄せていただくことを、私の写真撮影では大切にしている。
■汽車が運んだ時代の軌跡

2015年5月6日に撮影したこの写真は、翌年春のダイヤ改正で予讃線松山~宇和島間からは姿を消してしまった「アンパンマン列車」の8両連結フル編成だ。お正月前後、GW期間中、お盆期間中にはこの編成だった。写真撮影をされている方々も今ほど多くはなく、当時はこの鉄橋と大洲城をセットにして撮影しているのは私くらいのものだった。
よくぞこのシーンを撮っていたものだと自分でも感心しているが、二度と戻ってこないシーンであるだけに永久保存版ものだ。

伊予灘ものがたりの誕生
2014年7月5日に撮影した初代伊予灘ものがたり初撮影のシーンは、今思い起こしてみても私以外に撮影しているカメラマン諸氏はいなかった。この撮影データを大洲市やJR四国を含む関係機関等と共有し、インターネットを通して配信していった。そして、この後、このことが大洲の観光街づくりに大きな変化をもたらすきっかけとなった。その一つが、2015年初め頃から始まった大洲城からの旗振りだった。

2015年12月13日撮影の「新阿蔵踏切」の写真は、今や全国に広まっている撮影ポジションだ。当時、鉄橋と大洲城だけではなく、他に大洲城が列車と絡む場所はないものかと走り回って気がついたのがこの場所だった。
このときの撮影は、運転士もここで撮影するとは思っていなかったようで、望遠構えている私を見つけて思わずにっこりしてくれたというとても嬉しい思い出のシーンだ。
「写真は語る」地域振興のはじめ
これらの写真は、大洲市で進めていた観光街づくりの資料やパンフレットなどに積極的に活用し、併せて、進化を遂げるSNSを介してこの写真を発信した結果、今日のような状況を生み出している。

2019年7月28日に迎えた伊予灘ものがたり就航5周年では、当時の大洲城支配人が5周年に合わせて500人の旗振りを企画し、紆余曲折はあったものの見事に大願成就。その名場面の写真がこれである。
現在は、列車も2代目となり昨年無事に10周年を迎えて今も元気よく走っている伊予灘ものがたり。以前ほど多くはないが、撮影のホットスポットではカメラを構えて撮影を楽しむ方々のお姿を見かけることは、その人気ぶりが落ちていないことを物語っているようだ。
■観光まちづくりとキャリア連携

掲示板(BBS)からBlogへ、Facebookから派生したInstagramへ、そして、今静かに広がりを見せている「note」。「X」は少し別格としても、これらは今や仕事にも日常生活にも不可欠のものとなっている。併せて、多くの利用者がスマホやデジタルカメラで撮影を楽しむ時代。そこには、地方を訪れる観光客の皆様方を「広告媒体」として上手く活用する取組が当然ながら不可欠である。地域間競争の勝負どころでもあり、町に汽車が走っていることに感謝しなければならない。

松山以南の予讃線では電車は走っていない。「汽車」なのだ。古いし遅れていると思われるかもしれないが、だからこそ「アナログ的価値」がある。その価値を上手く写真で画にして表現し、多くの皆様方にお伝えして感じていただくことが、この町の第一期観光街づくりにとっては不可欠なことであったと言える。
その一翼を担わせていただいた写真家として、今後もできるだけ長くこうした地域創生撮影活動を続けていくつもりでいる。
(これまでの寄稿は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=14
寄稿者 河野達郎(こうの・たつろう) 街づくり写真家 日本風景写真家協会会員