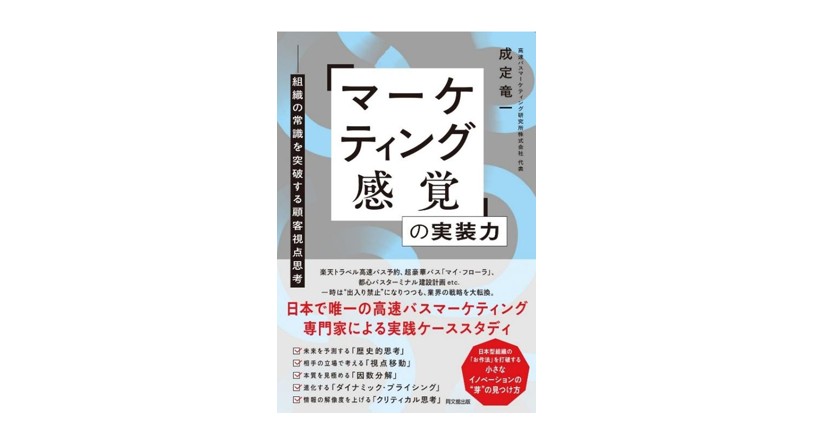高速バス業界を対象にコンサルティング事業を行っている高速バスマーケティング研究所(横浜市港北区)の成定竜一代表は8月8日、新著「『マーケティング感覚」の実装力」を刊行する。5月発売の「高速バスビジネス」に続いて上梓。日本型組織や成熟産業に変革を起こすヒントを伝える。
8月発売『「マーケティング感覚」の実装力 --組織の常識を突破する顧客視点思考』
高速バスは本来、後発の挑戦者で、鉄道などからシェアを奪うべき収益事業。しかし、それを運行するのは、地域独占的な事業免許制度の下で地域の路線バスを運行してきた、内向きで保守的な社風のバス会社たちだった。ほんの少し「常に消費者の視点に立って考える」ことができれば高速バスはまだまだ成長できる――バスターミナルでの学生アルバイト時代の直感が、筆者の原点。もっとも、高度なマーケティング理論や最新の手法までは不要。もっと手前の「消費者の立場で考えるコツ」を「マーケティング感覚」と名付けました。バス業界のみならず、内向きになりがちな日本型組織において、すべてのビジネスパーソンに必須の思考だと考えている。
同著では、高速バス業界に「競争」と「多様化」の概念を持ち込み、国の有識者会議委員として制度改正に関
わりながらも、横並び志向の業界から一時は“出入り禁止”になった経験などを踏まえ、日本型組織や成熟産業に変革を起こすヒントをまとめている。
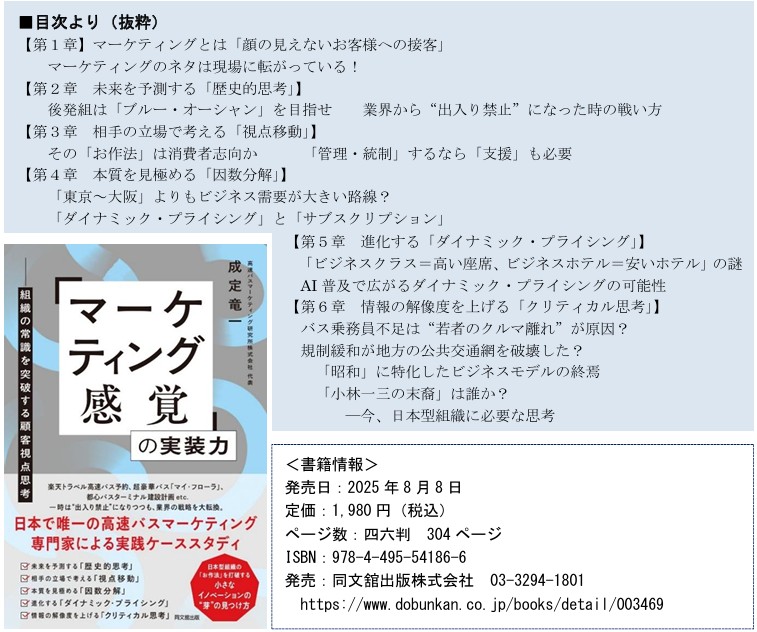
5月発売『高速バスのビジネス-業界の変遷・現状と今後の戦略- 交通ブックス131』
昨今、通勤通学の多い短距離・昼行路線から長距離・夜行路線まで、年間輸送人員が約1億人と、実は航空国内線に匹敵する高速バス事業。2冊の著書では、高速バスの誕生(1964年)から80年代の急成長期、2000年以降の「高速ツアーバス」の興隆(「超豪華バス」登場などの多様化)といった業界の歴史を、主に「高速バス参入の権利(営業権)」と「マーケット開拓」の2つの面で振り返っている。それを踏まえ、高速バスの市場を大きく3つに分類し、それぞれのマーケットが今日直面する課題と各事業者が採るべき戦略を解説している。