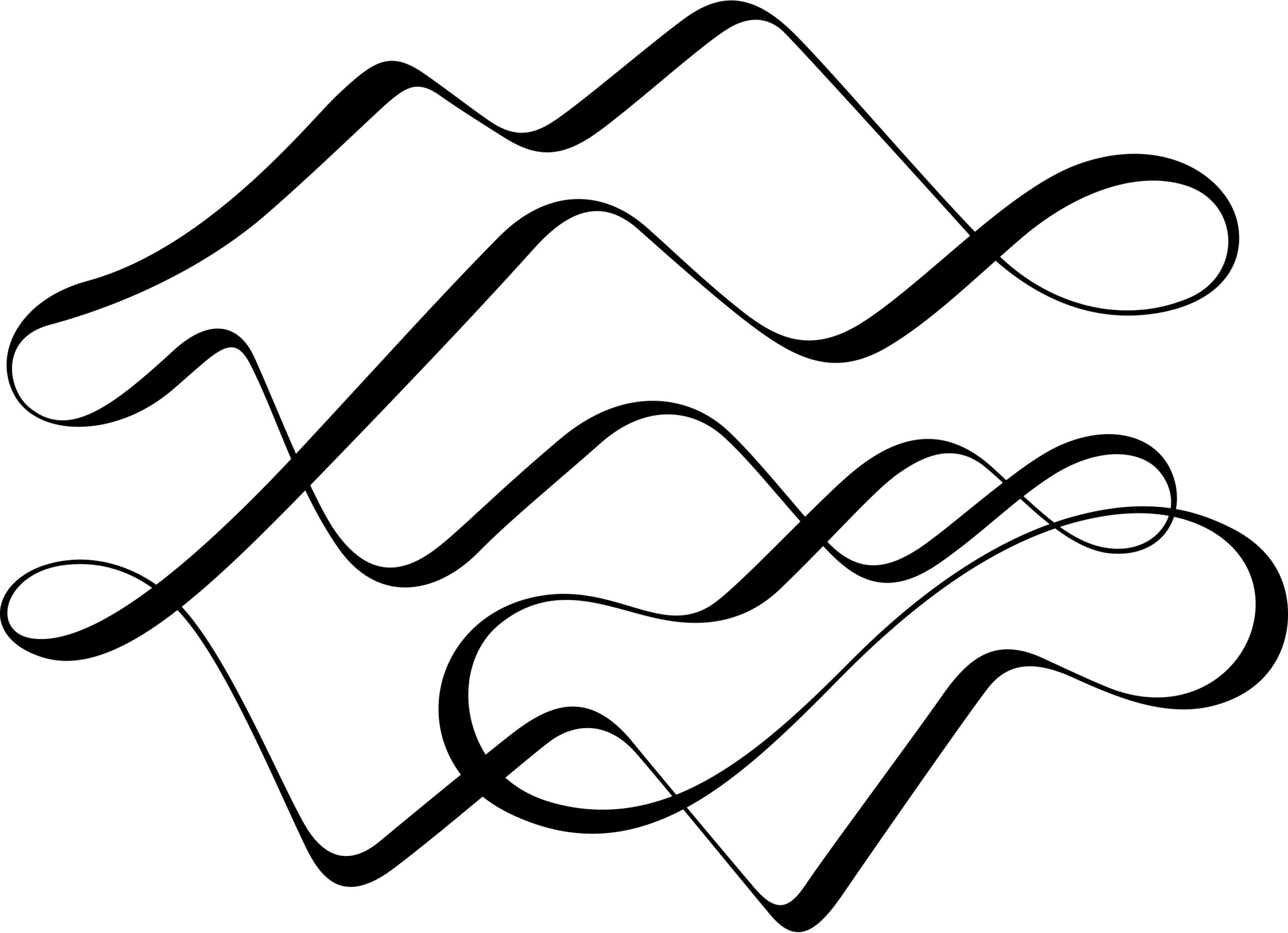強固な防潮堤(ハード)だけでは命を守れない――。その事実を突きつけられた私たちが、陸前高田の旅の最後に訪れたのは、静かに佇む旧・気仙中学校の校舎でした。当時の市内死亡率が7.2%に達する中、この学校の生徒87名と教職員は、誰一人欠けることなく津波から生還しました。それは単なる偶然の「奇跡」ではありません。防災の核心である「ひとづくり(ソフト)」がいかに重要かを、静かに、しかし雄弁に物語る、必然の軌跡でした。

◼️奇跡を必然に変えた、3つの「人の力」
では、なぜ彼らだけが助かったのか。その背景には、3つの決定的な要素がありました。
- 一人のリーダーの「想定外」を乗り越える行動
内陸出身だった校長先生は、海の近くにある学校の避難計画に強い危機感を抱き、自ら山を歩いて、マニュアルにはない、より安全な避難場所を探し出しました。行政や前例に頼るのではなく、主体的に「最悪」を想定し行動した一人のリーダーシップが、すべての始まりでした。 - 体に染み込んだ「生きた教訓」
気仙中学校では、地域の津波経験者である高齢者を学校に招き、体験談を聞く防災学習を続けていました。そこで語られた「屋上へ避難しては絶対にダメだ」という生々しい教訓が、生徒たちの命を救います。2011年の津波は、校舎の屋上を遥かに超える高さに達したからです。マニュアルには書かれていない「地域の知恵」が、生死を分けたのです。 - 思考停止を許さない「訓練の賜物」
震度5強の揺れで大人がパニックに陥る中、生徒たちは、「地面がぐにゃぐにゃに揺れている最中に、全員が全力で走って逃げた」といいます。避難完了まで、わずか10分。それは、日頃から体に染み込ませていた反復訓練の賜物以外の何物でもありませんでした。
◼️生還の先にある現実と、ツアーの終わりに

しかし、この物語には胸が張り裂けるような続きがあります。高台に避難した生徒たちの目の前で、生まれ育った町が津波に飲み込まれていきました。「お母さんが家にいる」「おばあちゃんが…」と泣き叫ぶ子どもたち。結果的に、生還した生徒の8割が、家族を失う「遺族」となってしまったのです。個人の避難の成功と、地域全体の防災との間にある、あまりにも大きな溝を、この事実は浮き彫りにします。
それでも人々は、バラバラになった心をつなぎとめるため、祭りを再開しました。賛否両論の中、開催された祭りは、人々が再び前を向くための活力を生み出したといいます。それは、地域に根ざした文化が持つ「結束の力」が、コミュニティの再生に不可欠であることを示していました。
この3日間の旅で私たちが陸前高田から学んだのは、ハード(まち)とソフト(ひと)の両輪で、過去の教訓を未来の希望へと繋ぐ、壮大な挑戦の姿でした。津波の色が、海底のヘドロを巻き上げた「黒」だったという話は、災害が自然と人間の関係性を映し出す鏡であることも教えてくれます。
このツアーは、私たち一人ひとりに問いを投げかけて終わりました。 あなたの町の災害リスクは何ですか? あなたは、あなたの大切な人を、どう守りますか? 陸前高田の学びを、自分たちの町へ持ち帰ること。それこそが、この旅の本当のゴールなのかもしれません。
寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-14-1024x576.png)