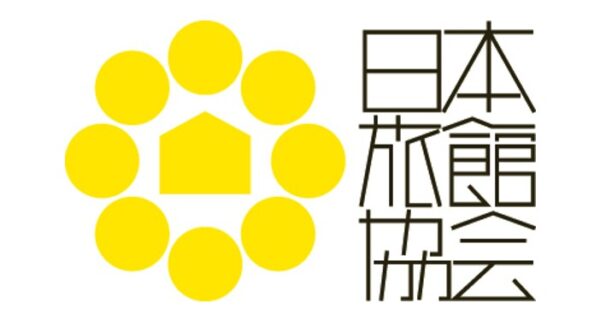日本修学旅行協会(銭谷眞美名誉会長)は8月19日(火)、東京都内で「持続可能な修学旅行に向けて~修学旅行を取り巻く環境の変化にどう対応するか」をテーマに、第18回教育旅行シンポジウムを開いた。物価高騰による修学旅行費用の上昇は経済的な理由で修学旅行に参加できない生徒を増やすことから、学校や旅行会社、受入地が今後の継続的な実施のために議論した。

主催者あいさつで竹内秀一理事長は「旅費が上昇し、コロナ禍前と状況は変わった。修学旅行は普段の学校生活で行うことができない、さまざまな経験を通じて学ぶことができる。シンポジウムで今後も継続していくための気づきを得てほしい」と呼び掛けた。
基調報告では引き続き、竹内理事長が登壇。2024年度における公立高校の国内修学旅行の内訳として、79%が交通費と宿泊費に、21%が体験に充てられたことに触れ、「学校は体験活動に費用を掛けたいと考えている。物価高騰が続き、生徒の旅費を上げられない状況が続けば、体験の費用は今後さらに圧迫されていく」と予測した。
物価高騰による生徒の旅費の上昇が難しい理由として、東京都や愛知県、大阪府などの自治体が、修学旅行費の上限や基準などを定めていることを挙げた。「旅行費用を引き上げれば、保護者の負担が増え、不参加生徒の増加につながるため、上限が設定されている」と説明。「物価高騰を受け、一部自治体では制度の見直しが行われたが、多くは上昇分に追いついていない」と語った。
また、学校に取り入れたい修学旅行のプログラムを聞いたアンケート(複数回答)では、1位が探求プログラム(70.5%)だった。2位は平和学習(18.5%)、3位はSDGsをテーマにしたプログラム(14.2%)。文部科学省によって定められた学習指導要領で、学校は探求的な学習の実施を求められていることが主な要因。
このうち探求的な学習については、具体的に「主体的な学び」や旅先の人の交流から学ぶ「対話的な学び」、事前・事後学習による「深い学び」などが求められるという。
「学校・受け地からの報告」では冒頭、学校側から東京都立飛鳥高等学校の渋谷寿郎校長が登壇した。

同校は国際理解教育に力を入れており、長年修学旅行の目的地を台湾にしていた。25年度は旅費の高騰に対応するため、行先を韓国に変え、日程を短縮し、実施時期を8月から翌年2月まで拡大。そのうえで入札を募集したが、応札はなかった。これを受け、目的地を沖縄に変更した。
渋谷校長は「東京都が費用の上限を基準に変えたが、旅費の上昇で日程や現地での活動内容に制限がある」として、26年度も沖縄に決めたことを報告した。
狛江市教育委員会(東京都)の亀澤信一専門員は、修学旅行の意義として人間関係の構築や自主的な行動などを挙げながら、「これら重要度は少しずつ変化している」と指摘した。

社会や子供を取り巻く環境はデジタル化や国際化、地球温暖化、将来の予測困難などが進んでいるため、亀澤専門員は「修学旅行では『人と人の触れ合いを大切にする』、『生徒の主体性を育む』、『将来への動機付けにする』などを重視したい」と語った。
受入側からは、北海道観光機構企画プロモーション部の長野博樹担当部長が登壇。同機構では、教育旅行関係者の視察招聘や修学旅行用のコンテンツやガイドブックなどを作成し、誘客を行っている。

長野担当部長は「北海道の面積は広いため、周遊型の修学旅行が多かった。近年は滞在型にすることで、貸切バスの利用を減らす学校が増えた。旅行費用を抑えるため、航空機を利用していた一部学校は新幹線で訪れている」と変化に対応した事例を紹介した。
JTB福島支店の佐藤しおり氏は、都市部から離れた地域に旅行会社として十分に営業活動ができず、入札時期が集中した際、すべてに応札できない現状を報告。「生まれ育った場所で修学旅行の質に差が出ないよう、配慮しなければいけない一方で、限られた時間と人員で効率を追求する必要もある」と旅行会社の立場を説明し、「JTBでは、すべての子供が等しく学びの場を享受できるよう、自治体や学校とオンラインでつなぐ『らくらくオーダー修学旅行』の提供を始めた」と語った。

パネルディスカッションでは、渋谷氏と亀澤氏、長野氏、佐藤氏の4氏が登壇。コーディネーターは日本修学旅行協会常務理事・事務局長の藤川誠二氏が務めた。今後も修学旅行を持続していくうえでの課題やこれからの方向性などをそれぞれの立場から議論した。
情報提供 旅行新聞新社(https://www.ryoko-net.co.jp/?p=154350)