令和7年9月10日、東京の豊かな自然が残る秋川渓谷で、誰もが楽しめる観光の可能性を探る「令和7年度誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業 秋川渓谷自然体験ワークショップ」が開催された。主催は東京都で、参加者は観光関係者や地方創生に携わる担当者、民間事業者など多岐にわたった。このワークショップは、障害の有無や年齢に関わらず、全ての人が自然の魅力を満喫できる「アクセシブルツーリズム」の推進を目的に、座学だけでなく、実際に五感で自然を感じるフィールドワークも実施され、参加者はアクセシブルツーリズムがもたらす感動や、具体的なビジネスの可能性を体験から深く認識した。
イベントの幕開け:当日の空気感と期待

当日は午後から雨予報だったが、参加者の熱気は高かった。会場である中村自治会館に集まった人々は、これから始まる体験と学びへの期待に胸を膨らませていた。ワークショップは天候を考慮し、当初の予定を変更して午前中にフィールドワーク、午後にセミナーを実施する運びとなった。参加者たちは、緑が鮮やかに輝く秋川渓谷を前に、アクセシブルツーリズムの持つ可能性を肌で感じる準備をしていた。一般的な観光イベントとは一線を画す、実践的な学びの場となる予感が会場に満ちていた。
白熱のプログラム:具体的な内容とハイライト
午前中のフィールドワークでは、「五感で自然を感じる実体験」と「最新の支援ツール体験」が二つの軸として展開された。参加者は、目の情報を閉ざされた状態で川原を歩く「疑似視覚障害者の手引き体験」に臨んだ。アイマスクを着用し、一歩一歩慎重に歩みを進める中で、参加者は視覚以外の五感がいかに研ぎ澄まされるかを実感した。「目の情報がない状態で歩くと、匂いや空気など、視覚以外の情報が一気に入ってくることに気づいた」という参加者の声は、この体験の意義を物語っている。また、手引きをする側も、相手への配慮や適切なコミュニケーションの重要性を再認識した。

続いては、特殊な車いすやけん引装置の体験だ。砂利道や川原といった、通常車いすでの移動が困難な場所でも、最新のアクセシブルツールが大きな可能性を切り開く様子が示された。東日本大震災の津波からの避難をきっかけに開発されたという車いすけん引装置「JINRIKI(人力)」は、最初の一歩を踏み出せば驚くほど楽に進めることを参加者に実感させた。また、フランス製のアウトドア用車いす「HIPPOcampe(ヒッポキャンプ)」は、複数人のサポートがあれば登山も可能という驚くべき性能を披露し、水陸両用の「モビチェア」は、水辺での活動を諦めていた人々に新たな希望を与えた。




午後は中村自治会館の室内で、NPO法人ユニバーサルトラベル総合研究所理事長の長橋正巳氏によるセミナーが開催された。長橋氏は、物理的なバリアだけでなく、ルールのバリア、情報のバリア、心のバリアという「4つのバリア」の存在を指摘し、多くの人々が外出を諦めている現状を伝えた。さらに、アクセシブルツーリズムは社会的な要請であるだけでなく、観光庁の試算によれば、約9,000億円もの新たな市場を創出する可能性を秘めており、介助を必要とする高齢者を含む潜在市場規模は4,000万人にも上るというビジネスとしての重要性を強調した。
参加者の声と広がる交流
セミナー終了後には、参加者同士の活発な名刺交換と意見交換が行われた。互いの知見や経験を分かち合う中で、新たなビジネスのヒントや、今後の連携への期待が膨らんだ。参加者からは、「『行動』という言葉を新たに覚えた」「自分自身が体験することの重要性を痛感した」といった声が聞かれ、このワークショップで得た学びを今後の事業に活かしたいという強い意欲が感じられた。

東京都議会議員や東京都観光部担当者からも、アクセシブルツーリズム市場の将来性や、この事業がもたらす社会的な意義について言及があった。少子高齢化が進む日本において、高齢者介護のニーズは増大し、この市場は今後さらに拡大すると見込まれる。官民が連携し、この分野での知見とアテンド方法を積み重ねていくことの重要性が改めて強調された。
イベントが示す未来:地域創生への貢献と今後の展望
このワークショップは、アクセシブルツーリズムが単なる「福祉」ではなく、地域創生に貢献する「ビジネス」であり、同時に誰もが旅の喜びを享受できる「共生社会」の実現に不可欠であることを明確に示した。参加者は、体験を通じて五感を研ぎ澄ませる重要性や、最新のツールが拓く可能性、そして何よりも「心のバリア」をなくすための具体的なヒントを得ることができた。
東京都が提供する補助金制度などの支援策が示されたことも、今後の取り組みを加速させる追い風となるだろう。イベントの最後に紹介された「知覚動考(知る→覚える→動く→考える)」という言葉が示すように、この日得た学びを行動に移し、誰もが安全・安心・快適に旅を楽しめる社会を実現するための第一歩が、この秋川渓谷の地で踏み出された。
寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部




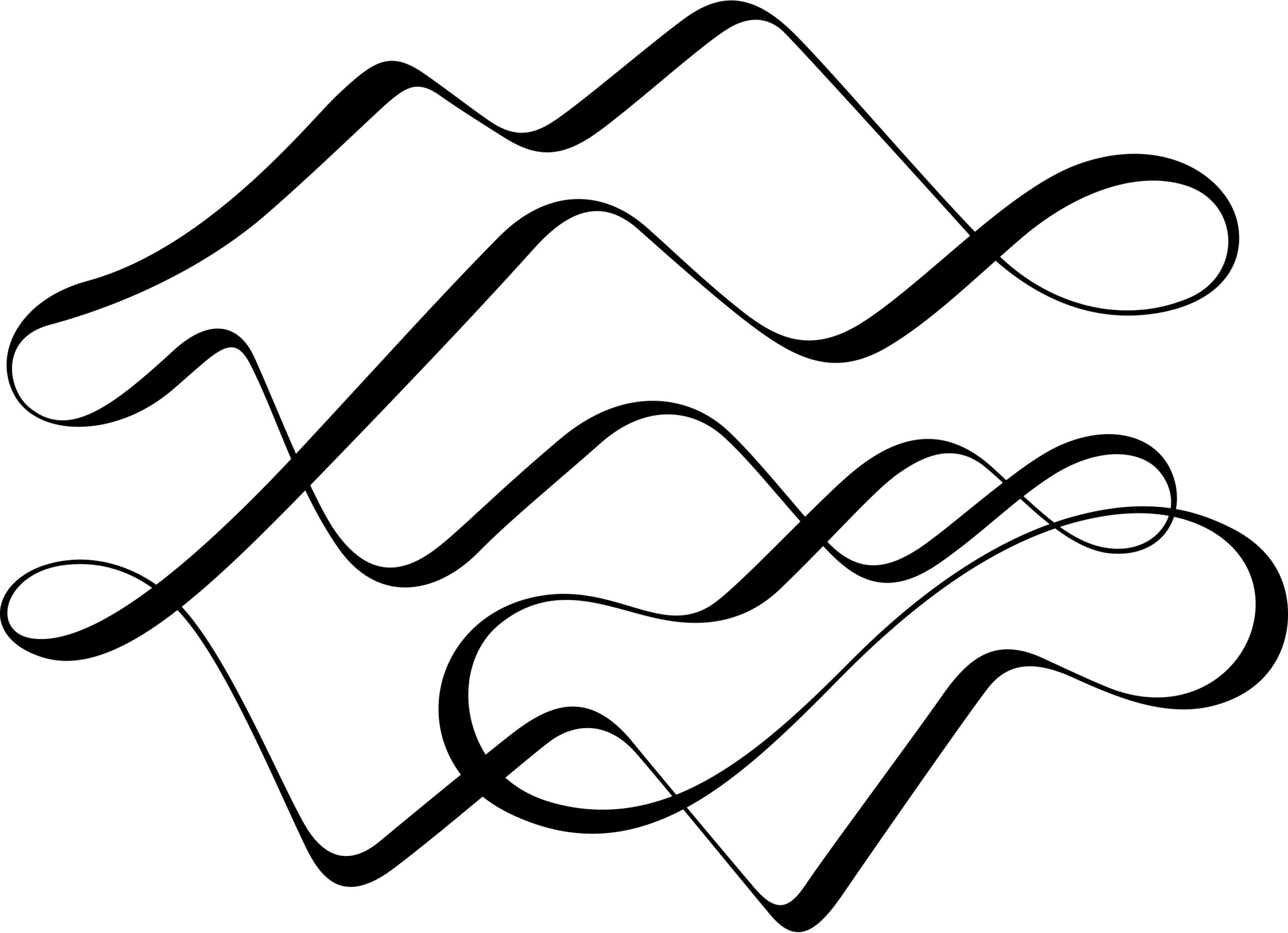

1-600x400.jpeg)



