東京都は10月2、3日、「令和7年度 誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業」の一環として、「大島トレッキング体験モニターツアー(障害者のトレッキング体験をサポートするモニターツアー)」を実施した。高齢者・障害者に特化した旅の企画などに取り組むNPO法人ユニバーサルツーリズム総合研究所の理事長を務める長橋正巳氏を講師に迎え、1泊2日でアウトドア用車いすを利用したトレッキングなど、山間部でのレジャー体験の支援や運営について研修を行った。
東京都では、障害者や高齢者等が、東京の自然を安心して楽しめる観光を推進するため、旅行業者、体験型観光提供事業者等を対象として、障害者等向けの自然体験型観光プログラムの運営ノウハウを提供する取り組みを開始している。
モニターツアーには、応募した障害者3人とその介助者、旅行会社、都内で自然体験型学習を提供する事業者など、総勢38人が参加した。以下、ワークショップの様子を紹介する。

大島の豊かな自然を舞台に、誰もが楽しめるトレッキング体験を実施
会場となったのは、東京・竹芝客船ターミナルから高速ジェット船で約1時間45分の伊豆大島。東京都心から日帰り圏にある離島として知られ、黒潮の影響を受けた温暖な気候と、三原山を中心とする火山地形のダイナミックな自然が魅力だ。

初日は、車窓からは圧巻の「地層大切断面」を見学するほか、2025年7月1日にリニューアルオープンした「伊豆大島ミュージアム ジオノス」で地質や文化の基礎知識を学んだ。火山島ならではの成り立ちを感じた後、三原外輪山山頂口で郷土料理の昼食を楽しんだ。午後は三原山を一望できる三原山外輪山展望台でワークショップとして座学に加え、未舗装路や坂道で車いす体験を行った。

2日目はホテル発の「温泉ホテルルートトレッキング」を実施。再生の一本道、ジオ・ロックガーデンなど火山の自然を間近に感じられるルートをアウトドア車いすや車いすけん引装置を活用して往復約4キロを移動した。また、地元の自然資源を活かした産業として知られる「大島椿製油所」を訪問し、伝統的な搾油技術や地域の暮らしとの関わりについて理解を深めた。

東京の自然を誰もが楽しめる場に、観光環境づくりを推進
初日の座学では冒頭、東京都産業労働局観光部受入環境課の富永信生課長代理(受入環境調整担当)が登壇し、東京都が推進するアクセシブルツーリズムの現状と、本ワークショップの趣旨を説明。富永氏は、これまで都が実施してきた「バリアフリービーチ」(八丈島)や「秋川チェアリングSUP体験」(あきる野市)など、障害者や高齢者を含む誰もが楽しめる自然体験の事例を紹介し、「今回の大島トレッキング体験を通じて、都内でも離島や山岳地といった自然フィールドでのアクセシブルな観光の可能性を検証したい。現場で見えてくる課題や改善点を率直に共有いただき、今後のバリアフリー観光のさらなる充実につなげていきたい」と述べ、参加者に積極的な意見交換と協働を呼びかけた。
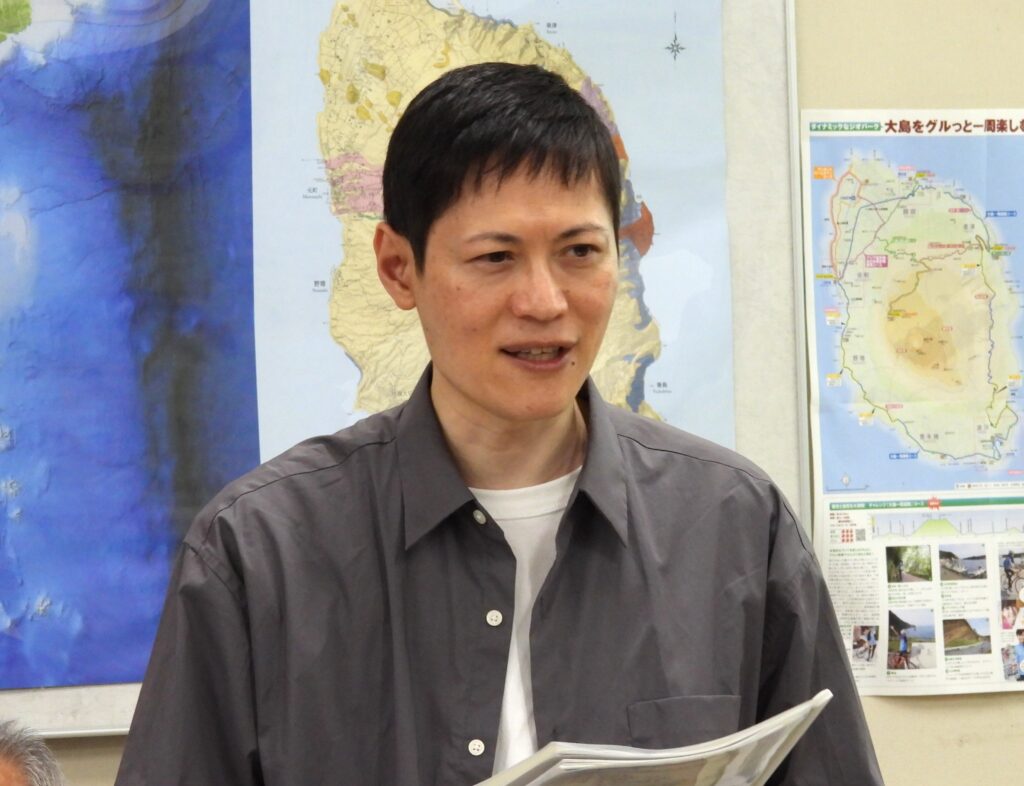
東京都では、障害者や高齢者等が、東京の自然を安心して楽しめる観光プログラムを提供する事業者等に対して、プログラムの実施に必要となる備品等の導入経費の一部を補助する「誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金」を募集している。自然体験型観光を提供する事業者や観光協会などを対象に、障害者向け備品の購入費や既存備品の改造費用を補助率5分の4以内で最大200万円まで補助する。このほか、バリアフリー情報ガイドの作成やシンポジウム・セミナーを開催するなど、さまざまな取り組みを行っている。
“旅をあきらめない”社会へ、心のバリアを越える観光の形
「誰もが楽しめる自然体験型観光」ワークショップでは、長橋氏が登壇。障害の有無を問わず誰もが自然を楽しめる観光のあり方や、現場で求められる支援・配慮について講義した。東京都が推進するアクセシブル観光の趣旨に触れながら、「自然は、誰かだけのものではない。高齢者も障害のある人も、そこに吹く風や光、音や香りを同じように感じることができる。そうした“共に感じる旅”を広げていくことが、観光に携わる私たちの役割だ」と語った。

続いて、自身が国内外で実施してきたバリアフリーツアーの経験を紹介。視覚障害のある旅行者が「風の向きで方角を感じる」と言いながら海辺を歩いたこと、歩行が難しい高齢者が「旅先で人に支えられたことが自信につながった」と笑顔を見せたことなど、具体的なエピソードを交えながら、「旅には人を元気にし、人生を前向きに変える力がある。誰もが“旅をあきらめない”社会をつくることが、私たち観光関係者の使命」と力を込めた。
その上で、障害者や高齢者が旅行をあきらめてしまう背景には、「物理的」「情報」「制度」「心」の4つの社会的障壁(バリア)が存在すると指摘し、「観光現場でこの4つを意識することが第一歩」と呼び掛けた。
①物理的なバリア(段差・急坂・通路幅などの移動に関する障壁)
②ルールのバリア(制度に関する障壁)
③情報の的バリア(情報、習慣、コミュニケーションに関する)
④心のバリア(意識・観念上の障壁)
2016年施行の「障害者差別解消法」が2024年に改正され、民間事業者にも「合理的配慮の提供義務」が課されたことにも触れ、「“前例がないからできない”ではなく、建設的な対話によって解決策を探る姿勢が求められている」と説明した。さらに、講義では「前例がないからといって断らないこと」「合理的配慮は特別扱いではないこと」「漠然としたリスクを理由に拒まないこと」を挙げ、現場での具体的な対応の考え方を示した。

また、少子高齢化や感染症の影響で観光市場の縮小が懸念される中、「外出に不自由を抱える高齢者や障害者の旅行需要を掘り起こすことは、観光市場維持のための新たな成長軸」と強調。観光庁の調査では、アクセシブル・ツーリズム関連市場は数兆円規模の潜在需要を持ち、地域の持続的観光振興にもつながると述べた。
事例紹介では、難病を抱えながらも水陸両用車いすで登山に挑む中岡亜希氏(ata Tours代表)、90歳で富士登山を達成した冒険家・三浦雄一郎氏らを紹介。「やりたいことをあきらめない」姿勢が、社会全体に“共生社会”の意識を広げる原動力になると語った。
後半では、山岳や自然体験プログラムの受入環境整備について具体的な事例を解説。段差を解消する簡易スロープ、悪路を走行可能なアウトドア車いす「HIPPOCampe」や牽引用具「JINRIKI」の活用に加え、介助人材の配置、イベント会場のバリアフリーマップ作成など、事前準備の重要性を訴えた。さらに、視覚障害者には「触察・香り・音による体験」や音声読み上げアプリ、聴覚障害者には筆談・音声文字変換アプリなど、多様なニーズに応じた対応事例も披露された。
講義の最後には、スキー場やビーチ、キャンプ場などがユニバーサルデザイン化されつつある「ユニバーサルゲレンデ」「ユニバーサルリバー」「ユニバーサルマウンテン」の映像事例を紹介。長橋氏は「自然体験は、心身のリフレッシュだけでなく、自己肯定感や社会的つながりを生む“生きる力”につながる」と締めくくった。
特異性ある4つの車いすを体感
講義後は会場を外の広場に移し、「HIPPOcampe」「JINRIKI」の使用方法を、長年にわたりバリアフリービーチやユニバーサル登山の指導を行ってきた専門家でプランニングネットワークの渕山知弘氏(オフィス・フチ)が指導。さまざまな種類の車いすの構造や安全な取り扱い方を説明、砂利道や坂道での走行体験が行われた。初めてアウトドア用車いすを扱う参加者も多く、当初は操作に戸惑う場面も見られたが、渕山氏は「観光を支える立場の人こそ、車いすの仕組みや扱い方を正しく理解しておく必要がある」と現場での安全確保や支援者としての心構えを説いた。
また、観光地でよくある段差や傾斜の通過方法、休憩時の位置取り、利用者の体調確認のポイントなど、現場を想定した具体的なアドバイスも紹介。「サポートの質は、ちょっとした配慮の積み重ねで大きく変わる」と強調し、実際に支援する立場としての気付きを促した。参加者からは、「車いすのたたみ方やブレーキ操作など、知っているようで知らないことが多かった」「実際に触ってみて初めて利用者の視点が理解できた。職場に戻ったらスタッフ全員に共有したい」といった声が上がった。
このほか、自然の中で楽しめる車いすとして、本格アウトドア用車いす「マウンテントライク」、家族や仲間と自然を楽しめるアウトドア用電動アシスト介助型車いす「eプッシュ」が披露された。大島の椿油専門メーカー「大島椿」が保有している。販売元の「nicomo」の代表田村達彦さんに使用方法をレクチャーいただいた。

火山の大地を共に歩く、大島・三原山でのバリアフリートレッキング
2日目は、宿泊先である大島温泉ホテルを出発し、三原山の中腹に広がる「温泉ホテルルートトレッキング」を実施した。出発前のブリーフィングでは、長橋理事長が全体行程を説明し、「噴火した」「私と一緒に逃げよう」など、緊急時に使える基本的な手話を全員で確認。障害のある参加者との意思疎通をスムーズにし、安心して臨めるよう準備を整えた。

ルートは、三原山の外輪山南側に位置する標高約500〜700メートルの火山地帯。「再生の一本道」と呼ばれる区間では、1986年の噴火後に再生した溶岩原の上を進み、黒いスコリア(火山れき)に生命を宿す草木の力強さが印象的だった。続く「ジオ・ロックガーデン」では、溶岩が作り出した岩壁や大小のクレータ地形を間近に観察でき、地球の鼓動を感じるような迫力に参加者の表情も引き締まった。

障害者の移動用として「HIPPOcampe」「JINRIKI」「マウンテントライク」「eプッシュ」を活用しながら、支援者と障害者がペアを組み、チーム単位で約2時間のトレッキングに挑戦。上り坂や砂利道など難所では声を掛け合い、姿勢を合わせて進む姿も見られた。火山風が吹き抜けるなか、参加者は「自然の音や匂いが五感に響く」「風景を“共有する”こと自体が体験になった」と話し、支援者も「一緒に歩くことで互いの距離がぐっと近づいた」と笑顔を見せた。

最後まで歩ききったグループが山頂方向を見上げると、外輪山の縁に立つ展望台が姿を現し、眼下には黒々とした溶岩帯が広がった。参加者の一人は「支援される側・する側というより、同じ時間を共に過ごした仲間という感覚だった」と語り、充実した表情を見せた。
約2時間にわたる体験を通して、誰もが火山島・大島の自然を“自分の足で感じる”ことの意義を確かめるトレッキングとなった。

現場で得た気づきと共創の手応え、実践を通じて学びと連携を共有
ワークショップとトレッキング体験の後には、意見交換会を開催。旅行会社や介護・福祉関係者、地域観光事業者など約10社が参加し、体験を通じて得た気づきや今後の展望を語り合った。特に、東京都のアクセシブルツーリズム推進事業における現場での課題や可能性、車いす・けん引装置などの補助器具の導入、補助金を活用した設備整備への関心が高く、旅行商品としての具体的な開発・販売に向けた意見も出された。また、こうした取り組みを一過性に終わらせず、地域間でのネットワーク構築や継続的な研修の実施を求める声も上がった。
トレッキング終了後には、参加者全員による意見交換会が行われた。冒頭、長橋氏が「禅の言葉に“知覚動考”という言葉がある。ともかく動くこと。今日ここから、まず一歩を踏み出してほしい」と呼び掛けた。続いて、渕山氏が「ユニバーサルツーリズムを推進していく鍵は、地域に根差した旅行業者の力にある」とモニターツアーを契機とした事業化を促した。地元企業として参加した大島椿からは、マウンテントライクなどの機材の導入を進めていることが紹介された。
参加者からも次のような声が寄せられた。
「車いすの娘と一緒に参加したが、あの道を登れるとは思わなかった。皆さんの支援で普段できない体験ができ、本当に嬉しい」(障害児の母)
「社会起業家として地域でフィールド化を進めたい。仲間とネットワークを築ける良い機会だった」(観光系DMC事業者)
「保険外介護で高齢者の外出支援をしているが、どんな人でも“やりたい”を叶える仕組みを広げたい」(介護支援事業者)
「車いすの活用が災害時にも役立つと感じた。助成金制度を活かして自社でも導入を検討したい」(旅行会社経営者)
「山登りは無理だと思っていたが、車いすでもできると実感した。今後は“できます”と提案できる立場になりたい」(旅行会社社員)
「高尾山の観光案内所で働いており、今後は“行けるルート”を増やすための仕組みを考えたい」(観光協会職員)
「重度訪問介護をしているが、今回の体験で“寝たきりでも旅できる”ことを伝えたい」(訪問介護職)
「母と妹が一緒に参加し、普段見られない笑顔を見られた。介護職として“できることを支える”気持ちを大切にしたい」(参加者家族)

東京都の富永課長代理は「今回の実践を通じて、誰もが安心して自然を楽しめる観光の在り方を考えるきっかけになった。今後も現場の意見を踏まえながら、都としてアクセシブルツーリズムの推進を継続していきたい」とまとめた。

参加者全体からは、「山でも海でも“あきらめない旅”を続けたい」「地域・企業・行政が連携して取り組むことが鍵」といった前向きな意見が相次ぎ、2日間のプログラムを通じて、“誰もが自然を楽しめる観光”の実現に向けた共通の意識が深まった。

【参考】
東京都「誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金」の詳細は、以下URLから。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/nature
東京都「誰もが楽しめる自然体験型観光」特設サイトは、以下URLから。
https://www.sangyo-rodo1.metro.tokyo.lg.jp/tourism/accessible/nature








コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)



