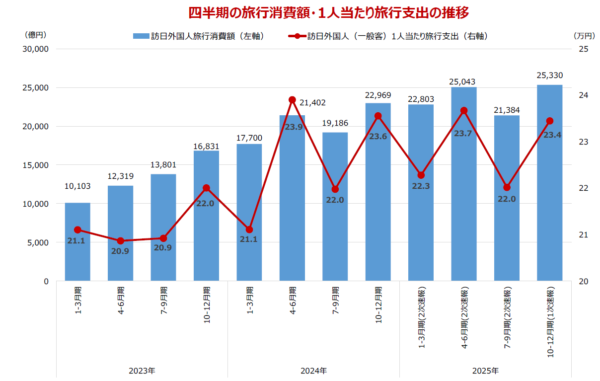筆者が初めて京都の町に触れたのは、今から約50年前のことだ。中学校の修学旅行で訪れた。その時、市電も健在、京阪電車も地上を走っていた。しかし、モータリゼーションの全盛期、路面電車は交通障害の元凶と言われた。そのため、京都市電は1978年9月末に全廃する。一方、京阪電車は1995年5月にJR東海道線以北が地下化された。このことによって、京都市内中心部には電車の運行がなくなった。そして、特に京阪電車路線上には川端通ができ、クルマ社会にとっては大きな変化が訪れた。
また、年を追うごとに、観光客数の右肩上がりとなる。その結果として、京都駅前をはじめ、中京区の旅館や民家がホテルに変貌している。
京都の宿泊施設の宿泊料金は、春「桜花」、秋「紅葉」の時期に高騰する。しかし、訪日外国人は時期を問わず、長期滞在の旅行形態となる。そのため、平日・休前日構わず、多くの宿泊施設を席巻する。筆者も京都駅八条口のホテルに宿泊したが、多くのホテルが外国人のための場所と化していた。
京都観光ゴールデンルート(東山界隈)

前回、訪日外国人が好む観光地として、東山界隈と嵐山界隈が代表的な場所であると報告した。
筆者は、週末金曜日の午後、京阪電車の祇園四条駅を振り出しに、東山界隈を八坂神社から清水寺へ歩みを進めた。また、清水寺から京都駅までもバスに乗らずに、街の姿を観察してみた。
四条通を八坂神社へ
これまで、関西私鉄の駅名は、「会社名」と「場所」を組み合わせたものが主流であった。しかし、遠方からの観光客が増えた結果、現在地がわかりやすい名称に変わりつつある。そのため、河原町駅という阪急電鉄の駅は「京都河原町」に、単に四条駅という京阪電車の駅は「祇園四条」と名乗るようになった。祇園の名前を冠することによって、祇園(八坂神社)が近いことを初めての観光客も理解できるように意図している。訪れる人々へのサービス機能の表れと言えよう。
川端通の地下に作られた駅舎から地上に出ると目の前には南座が位置している。1929年に完成した歌舞伎の劇場である。そこから東に向かうと八坂神社だ。この周辺は、京都最大の繁華街の中心地である。昼も夜も人がごった返している。

アーケードの商店街を進むと、南側に有名料亭「一力」が見えてくる。四条通と交差するのは花見小路だ。舞妓パパラッチが出没するために、各所に「撮影禁止」「立入禁止」の札が立てられるようになった。このような行為は、事件事故につながるものとなる。やはり、「郷に入っては郷に従う」、ルールは守らねばならない。
一方、かつての商店街は、京都ならではのお土産や食事処がほとんどであった。しかし、昨今は、インバウンドを意識した設えも増えている。ほどなく、四条通は東大路にぶつかり、八坂神社の西楼門が見えてくる。
石塀小路の今
楼門をくぐると、そこは一気に人種のルツボと化す。八坂神社が人気ランキングのトップ10に入っていることがよくわかる。後方の円山公園まで足を延ばすこともできるが、今日は先を急ぐ。

南楼門から下河原通を進むと左手に石塀小路が見えてくる。市電の敷石を移築した石畳と石塀が静かな佇まいの小路である。しかし、一部が私道となっており、その中に無断で入り込む観光客が多いことから2019年10月から無許可の撮影ができなくなった。最盛期に比べると観光客の数が減ったように感じる。
京都らしい風情を醸し出すこの場所、撮影できないのは残念だ。この日は撮影する観光客の姿は見受けられなかった。そして、石塀小路を抜けると「ねねの道」だ。豊臣秀吉の正室・北政所ねねが庵を結んだ古刹「高台寺」が目の前に位置する。1989年まで非公開・拝観謝絶であった寺院は、今では東山界隈の人気コンテンツの一つとなった。
二年坂から産寧坂へ
ここから先は、清水寺に向かう参道でもある。一念坂から二年坂、そして、産寧坂とつづく。古くは趣きのある料亭や土産屋が軒を連ねていた。しかし、最近は、今時の土産を売る店やソフトクリームなどを供する店に変わってきている。建物が昔のままであることが、唯一の救いかもしれない。

さて、産寧坂は、ここで転ぶと三年以内に死亡するという説もあるが、安産祈願の意味合いが強い。その由緒は、坂上田村麻呂の夫人の安産を願って創建した清水寺の子安の塔に多くの妊婦が参拝しようと訪れるようになった。
しかし、きつい坂を上り切れずに諦めたことから安産祈願のために産寧坂と名付けらえたというものだ。なだらかな二年坂に比べて、勾配がきつい産寧坂は今でも息絶え絶えになっている人も多い。
登り切ると、清水坂に到着する。右手には、樋口清之氏の名著『梅干しと日本刀』にも記された七味家の店舗もある。
清水坂からちゃわん坂
修学旅行シーズンともなると、貸切バスが列を成し、子供たちは五条通から坂を上って清水寺まで歩くことが常態化する。そのため、ここの駐車場は完全予約制となった。東京原宿の竹下通りや最繁忙期の上野のアメ横などと同様に、人の姿に酔ってしまうほどの人口密度である。
清水寺門前の坂道は、京都市内においても最大級のお土産ストリートだ。筆者が大学生の時、京都市は古都税(古都保存協力税:1985~1988年)という目的税を徴収した。清水寺などもその対象寺院となった。京都市と仏教界とが真っ向から対立し、反対するために拝観停止することとなった。アメリカでも話題となり「テンプル・ストライキ」などと言われた。この時、清水寺や門前の土産屋も開店休業状態となった。ひと一人歩かない清水坂は、後年、コロナ禍でも同様の姿を見せた。
生の声が拾う観光の形の変化
今回、あえて清水寺を目指した目的がある。古都税騒動の際に、閑古鳥が鳴く八橋屋さんの話を聞く機会を得た。「元祖八橋西尾為忠商店」というお店だ。この時からのお付き合いで、前職時代は、よく訪れた懐かしい場所である。ここの八橋は、三角でなく長四角に畳んだ形である。個人的には、一番美味しい八橋だと思っている。店員さんが「修学旅行の子供たちが、ごっつ減って、なかなか売り上げが伸びへん」とこぼしていた。外の坂道には、ひっきりなしに観光客が通っているのに、お土産にも変化が生じているのだ。
あまりにも人が多いので、清水寺を目指すのは止め、途中からちゃわん坂(清水新道)に抜けることとした。
このどんつきに、もう一つの目的地がある。それは「吉田清栄堂」というお土産屋だ。こちらも前職時代からずっとお世話になったお店である。かつては、清水焼の販売が主流であったが、昨今、清水焼は売れず、焼き物が陳列されていた場所は、カフェに変わった。メインルートである清水坂は、行き来するのも困難な状況であるのに対して、こちらはゆっくりと時間が流れている。「昔と変わったやろ。外国人ばっかり。彼らは平日に来て買い物してくれる。けど、週末にやってくる日本人は、買い物せーへん。外国人さまさまや」と若女将は話してくれた。
五条坂から京都駅へと
清水寺を後に、ちゃわん坂を下る。東大路にある五条坂バス停は、歩道も狭くバスを待つ人々が長蛇の列を成す。バス停を移動するなりの措置をすべきと考えるが、なかなか実現しない。渋滞で遅れた路線バスは、満員で何台も通過していくことが少なくない。この状況を改善するには、観光客用の特急バスのバス停だけを移動する方法が最良と考える。

八坂神社から歩いてきたが、途中、多くの着物姿の観光客を見かけた。そのほとんどが外国人である。周囲を見渡すと、坂の途中に「着物レンタル」というお店が数多く存在している。今まで、お土産屋さんや旅館として営業していた建物が、業態を変え展開しているのだ。後日、インターネットの地図サービスを閲覧すると、何十軒ものレンタル会社がマーキングされていた。
東京浅草にも多くの「着物レンタル」店が営業している。基本的に一日レンタルなので、浅草には、午前中早い時間にやってくるようだ。そして、夕刻には着物を返し帰路につくという。祇園周辺から清水寺までも雨後の筍のように多くの会社が参入している。歩き疲れ、着崩れた着物姿は見るに堪えない。
着せ替え人形のような「えせニッポン体験」は、外国人が好む体験コンテンツなのだろうか。「ホンモノ」を体験させる取り組みこそ、長時間の滞在を生み経済効果の向上につながる。しかし、「えせ」体験は、初見の観光客もリピーターも、がっかりさせる体験となってしまうのではないだろうか。
新たなコンテンツと永続性

ここも新たなコンテンツに
かなり歩いたが、渋滞満員のバスには乗らず、京都駅まで徒歩移動することとした。
ほどなく、五条大橋を越え、高瀬川沿いに旧五条楽園あたりを徘徊する。有名サウナ「梅の湯」付近では、水辺のプロムナードの工事中であった。
しばらくすると、新たな観光コンテンツとして、脚光を浴びることであろう。
いづれにせよ、京都観光は日本を代表するものである。永続性のある観光、ニッポンを愛してもらう取り組みを真摯に議論して、より良いモノ・コトを提供していかなければ、好まれる国にはならない。そのため、6,000万人の外国人がやってくる時代に、一過性の取り組みにならないよう、しっかりとコンテンツをブラッシュアップすることが望まれる。今がその準備期間だ。
第1回目の記事は、こちらから https://tms-media.jp/posts/70791/
第2回目の記事は、こちらから https://tms-media.jp/posts/70794/
(おわり)
(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8
取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長





.jpg)