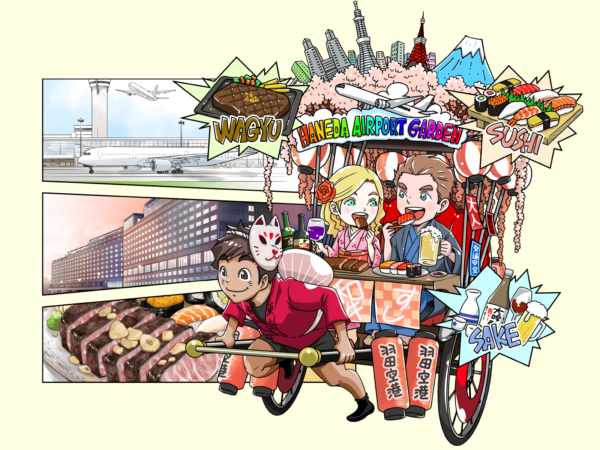住吉大社は、全国にある住吉神社の総本社である。山口県下関市の住吉神社、福岡県福岡市の住吉神社ともに「三大住吉」の1つに数えられる。
大阪市南部、古くからの陸地・上町台地の西端に大阪湾の方角に向いて、お社は鎮座する。古くは外交上の要港の住吉津・難波津と関係し、航海の神・港の神として祀られた神社だ。かつては、お社の目の前は海岸に面していた。そして、江戸時代には広く庶民からも崇敬されていた。「住吉」の読みは、現在は「スミヨシ」だが、元々は「スミノエ(スミエ)」だったと言われる。
さて、住吉大社には四つの本宮がある。住吉大神と神功皇后を祀る。そして、第一・第二・第三本宮が縦直列、第三・第四本宮が横並列という独特の配列だ。その形は、あたかも大海原をゆく船団のようだ。また、「住吉造」と称される本殿は、神社建築史上最古の様式の一つでもある。四本宮すべての本殿が国宝に指定されている。そして、住吉鳥居は、貫 (ぬき) の両端が柱から外に出ないことと、柱が四角であることが珍しい。
参道脇の道路には、チンチン電車(阪堺電車)がゆっくりと通り抜けていく。天王寺と恵美須町からやって来る線路が、この場所で合流し、堺の浜寺まで走っている。600基もある石灯篭を愛でつつ、摂津国の一之宮を拝する。下町情緒を感じるノスタルジックな小旅行を味わうことができる門前町だ。
(2022.11.22.撮影)
(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8
取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長





.jpg)