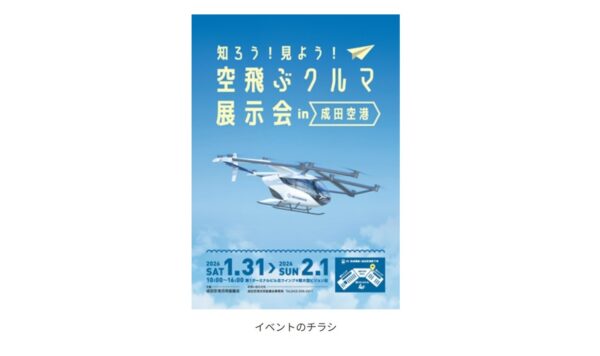サムライゆかりのシルク~日本近代化の原風景に出会うまち鶴岡~
戊辰戦争と庄内藩「ラストサムライ」
明治新政府(薩長軍)と激しく戦い、他藩が敗北降伏する中で最後まで戦い、明治元(1868)年9月26日、庄内藩は恭順するも最後まで新政府軍の自領への侵入を許さなかったことから「ラストサムライ」とも言われています。
庄内藩酒井氏は、江戸幕府による転封が一度もなかった数少ない譜代大名の一つであり、藩主・家臣・領民の結束が極めて固い藩であったため、降伏後、転封を命じられましたが、30万両の献金を納めて庄内に復帰、酒井氏の子孫は今も鶴岡に住み続け「殿様」として親しまれています。
処分が軽く済んだのは西郷隆盛の指示によるとされ、旧藩主や藩士・家老は鹿児島を訪れ、西郷と交流しました。そして庄内藩の重臣であった菅実秀(すげさねひで)は、「日本の近代化に貢献するために、荒れ地を開墾して桑を植え、養蚕を手掛ける」ことを西郷に相談し、西郷から同意を得たことが松ヶ岡開墾につながりました。

松ヶ岡開墾場と日本近代化の原風景に出会うまち「鶴岡」
この松ヶ岡の開墾は、明治維新直後の廃藩置県の折、菅実秀が旧藩士の先行きを考え、養蚕によって日本の近代化を進め、庄内の再建を行うべく実施したもので、旧庄内藩士3千人が刀を鍬に持ち替え、広大な土地を開拓しました。
広大な松ヶ岡開墾場の中心地には開墾本部として使われた「本陣」や瓦葺の上州島村式と呼ばれる「三階建の蚕室」が五棟現存しており、一棟は修復されて松ケ岡開墾記念館になっています。
明治時代初期に行われた士族授産の開墾地の中で、山形県鶴岡市を中心とする庄内地域は、養蚕から絹製品生産までの一貫した工程を「生きた産業」として現在に継承しており、鶴岡市内には日本近代文化の発展が感じられる史跡が今も残っていることから、平成29年、「サムライゆかりのシルク~日本近代化の原風景に出会うまち鶴岡~」として日本遺産に認定されました。
鶴岡市内にある、絹織物の精練等を担う羽前絹練(うぜんけんれん)では、明治時代創業の工場と昭和15年建築の事務所が当時のままに活用されており、往時を偲ぶことができます。そして旧庄内藩主酒井家により創設された「致道博物館」には、田麦俣地区で養蚕を行っていた多層民家の一棟(旧渋谷家住宅)が移築展示されていますが、同じく移設された「旧西田川郡役所」では、桑園整備への資金貸付や養蚕指導など、当地での絹産業をあらゆる面で支援していました。

田麦俣集落の養蚕農家「旧遠藤家住宅」
田麦俣地区は、庄内地域と村山地域を結ぶ六十里越古道沿いの集落で、四層構造の多層民家の里として知られ、松ヶ岡の開墾により大きな影響を受けた地域の一つです。
明治時代の中頃、現金収入の源として養蚕が盛んになり、民家の二階以上が養蚕の場所として使用されるようになっていきましたが、田麦俣地区は、山間部の傾斜地に位置し、建物の新築や増築が困難であったため、毎日の暮らしと作業・養蚕のための部屋が一つの建物の中にまとめられ、屋根の改造が行われました。
田麦俣集落の養蚕農家「旧遠藤家住宅」は、その多層民家の代表的なもので、一層目は家族の居住用、二層目は住み込みの使用人たちの居住用と作業場、三層目が養蚕、そして四層目が物置として使用されました。
この建物では、養蚕の作業効率を高めるため、屋根裏の改造が行われており、四方の屋根から採光と煙出しができるように「高はっぽう(高破風)」と呼ばれる高窓が設けられていますが、これを屋根の側面から見ると「武者のかぶった兜」の姿に似ていることから、「兜造り」と呼ばれています。

“ジャパンシルク源流の地”と南洲翁
松ヶ岡の開墾は、鶴岡市を中心とする庄内地域における絹産業隆盛の大きな契機となり、日本全体の近代化にも貢献した“ジャパンシルク源流の地”ですが、この庄内には戊辰戦争終結時での西郷隆盛に対する恩を忘れないために西郷を祀る南洲神社があります。
しかし、西南戦争が起きた際、”庄内の西郷”とまで言われた菅実秀は、「庄内も挙兵すべし」と西郷救援の声が藩内で声高に上がる中にあって、全力を挙げてこの動きを阻止しました。幕末・明治の「サムライ」であった菅は、西郷の“自分に対する「義」より、生き残って新たな日本の発展に尽くす人材になってほしい”と言う彼の思いを誰よりも理解していたのでしょう。
菅実秀(菅臥牛翁)の功績と『南洲翁遺訓』
実際、菅実秀は、西郷没後は鶴岡に隠棲し、「御家禄」と称された藩主側近保守派の頭領(臥牛翁)として、荘内銀行の前身である六十七銀行、米商会所や山居倉庫の設置、蚕種、製糸、機業等酒井伯爵家の関連事業を興し、日本の発展に尽くしました。
そして明治22年(1899)の大日本帝国憲法発布の特赦によって、西南戦争での西郷隆盛の賊名が除かれると、菅実秀は赤沢経言や三矢藤太郎に命じて『南洲翁遺訓』(西郷隆盛の考えや教えをまとめた書)を編纂させ、その出版物の配布を通して西郷隆盛のいわゆる「敬天愛人」思想を全国に知らしめたのです。
「サムライゆかりのシルク~日本近代化の原風景に出会うまち鶴岡~」のストーリーの中で、旧庄内藩士が刀を鍬に持ち替え、庄内地域を国内最北限の絹産地としたきっかけが、西郷南洲翁と菅臥牛翁の対談(徳の交り)であったことは興味深い話です。

※メインビジュアルは、松ヶ岡開墾場「三階建の蚕室」と平成芭蕉
寄稿者 平成芭蕉こと黒田尚嗣(くろだ・なおつぐ)クラブツーリズム㈱テーマ旅行部顧問/(一社)日本遺産普及協会代表監事