北前船ゆかりの自治体が保有する伝統的工芸品の魅力を国内外へ発信し、新たな販路の創出と文化価値の向上をめざす「北前船伝統的工芸品ネットワーク(仮称)」の発起人会が11月21日、長野県松本市内で開かれた。北前船日本遺産推進協議会に加盟する52自治体のうち、今回は伝統的工芸品を有する17自治体が参画。活動方針や規約案、来年度の事業と予算案などの協議が行われ、来年1月下旬に予定されている設立総会への重要な一歩となった。
歴史的つながりを現代の工芸振興へ
冒頭、発起人代表として新潟県村上市の高橋邦芳市長があいさつした。北前船の交易によって各地の民衆生活に根付いた工芸文化に触れ、「国内はもちろん、世界に冠たる日本工芸を共有する自治体が、北前船という歴史的キーワードで再びつながる意義は大きい」と強調した。村上市や新潟県佐渡市の無形文化遺産登録の進捗、石川県の世界遺産登録などにも言及し、「歴史・文化・工芸を重層的に結びつけ、自治体連携で世界発信する強力なプラットフォームにしたい」と述べた。

歴史と工芸を連携の軸に
協議ではまず「設立趣意書(案)」が共有された。趣意書では、北前船の交易を通じて各地域で育まれた伝統的工芸が、古くから生活文化を彩り、贈答品や交易品として地域経済を潤してきた歴史的背景が示されている。こうした価値を現代に継承し、次世代へ発展させるため、伝統的工芸品を有する自治体が連携し、工芸文化の振興、産地支援、さらには世界市場への展開を共通の目的として組織化を図ることが提起された。
参加予定自治体は、青森から九州まで広く点在する17自治体。漆器、焼物、金工、木工、織物など、多様な工芸品を持つ地域が一堂に連携することで、産地間の横断的な協力体制を築き、広域での発信力強化や販路拡大につなげていく狙いが示された。
国内外での発信強化と若手育成
協議では、今後の活動方針として六つの柱が示された。第一に、北前船ゆかりの伝統工芸品の周知と体系的な情報発信を進めること。第二に、国内外の展示会やイベントを通じ、産地の魅力を効果的にプロモーションすること。第三に、工芸を核に据えた観光振興、いわゆる「工芸ツーリズム」の展開で地域の交流人口を広げることが掲げられた。
さらに、SNSなどデジタル手法を活用した広域的な連携、後継者育成や若手作家の支援体制づくり、北前船交流拡大機構など関係団体との協働も方針に盛り込まれた。
こうした方針に関連して、北前船交流拡大機構の浅見茂専務理事からは、海外展開の実務経験にもとづく具体的な指摘があった。浅見専務理事はこれまでのイタリア・ミラノで開かれたミラノ・フォーリーサローネでの出展事例を踏まえ、「工芸を海外に届けるには、作家や産地の思いに寄り添った展示設計が欠かせない。現地で得た反応を次の作品づくりに生かし、その学びを他の産地とも共有する循環が必要だ」と述べ、展示を単発で終わらせず、販路形成や継承につなげる仕組みづくりの重要性を強調した。

発起人会では併せて、備前焼や曲げわっぱの海外展開の実績が共有され、福井県や秋田県の出展経験、鳥取県で進む準備状況も紹介された。海外での販路開拓に向け、自治体が連携して挑戦できる具体的な機会が示され、ネットワークとしての可能性が議論された。
高橋市長は「海外展開は理念だけでは進まない。費用や体制を現実的に見据え、自治体の予算編成との整合もとりながら段階的に取り組むべきだ」と述べ、慎重かつ着実な推進方針を示した。
名称は「ネットワーク」を採用
続いて示された規約案は全11条で構成され、組織名称には“ネットワーク”が採用された。これは、自治体同士が横断的につながり合う関係性を明確に表す言葉としてふさわしいとの判断によるもの。会長1名、副会長若干名、幹事1名を置き、さらに専門家や関係機関を顧問に迎えることで、産地支援や海外展開に必要な知見を広く取り込む体制を整える。
高橋市長は、「産地や作家の支援には多様な視点が欠かせない。産業界やインフルエンサー、学識者など幅広い専門性を取り込みながら進めたい」と述べ、顧問を含む外部協力者の拡充の重要性を語った。
基盤整備から情報発信強化へ
令和8年度の事業計画では、ネットワークの基盤整備を中心に据えた。主な取り組みとして、公式ホームページの開設、新潟で開催予定のフォーラムでの工芸品展示、国内外への情報発信の強化が挙げられた。
収入は参加自治体からの負担金を主な原資とし、この財源をもとに事業を展開していく。発足後の最初の一年間は、総会運営や情報発信体制の整備など、組織としての基盤を固める期間とする。
工芸は「富裕層に届く日本の強み」
発起人会には、オブザーバーとして有識者や国の関係者らが出席し、今後の展開に向けた提言が相次いだ。
跡見学園女子大学の篠原靖准教授は、国が進める「工芸ツーリズム」の動向を踏まえ、「これまでのPR型から、販路形成へとステージが変わりつつある。課題の整理とモデル形成をこのネットワークが担うことに大きな期待がある」と指摘した。

財務省理財局国有財産企画課政府出資室の二宮悦郎室長は、欧州での経験をもとに、「日本の伝統工芸は欧米の超富裕層に届く唯一無二の文化資源。しかし、政府内に専任の担当部署がないため、これまで仲介機能が不足してきた。自治体が広域で連携する取り組みこそが欠落していた部分を補う」と強調。京都で実施された「食×工芸×アート」の国イベントの成功例も紹介し、連携による価値創造の可能性を示した。

さらに北前船交流拡大機構の森健明理事長代行は、産地や作家の思いを尊重した展示設計の重要性や、若手作家を海外に派遣した際の成果と課題を具体例とともに説明。「展示はゴールではなく、販路拡大と継承につなげる仕組みが必要」と述べた。

岡山県備前市の長崎信行市長は、ミラノでの備前焼出展を振り返りながら、「海外で工芸品を紹介する場は、単なる展示ではなく、産地の価値や作家の思いを国際的に共有できる貴重な機会になる」と述べた。さらに「一自治体だけでは継続が難しい取り組みも、ネットワークとして協力することで実現の幅が広がる」とし、広域連携への期待を示した。

発起人である新潟県佐渡市の渡辺竜五市長は、世界遺産登録を契機とした文化発信に触れつつ、「佐渡には能、金工、木工など多様な文化資源があり、工芸はその中核を担う存在。北前船の歴史的つながりを軸に、文化と工芸を一体で世界に届ける取り組みが新たな可能性を生む」と発言。工芸と文化遺産の相乗効果を強調し、「全国の仲間とともに、若手の育成や市場開拓にも挑戦したい」と意欲を語った。
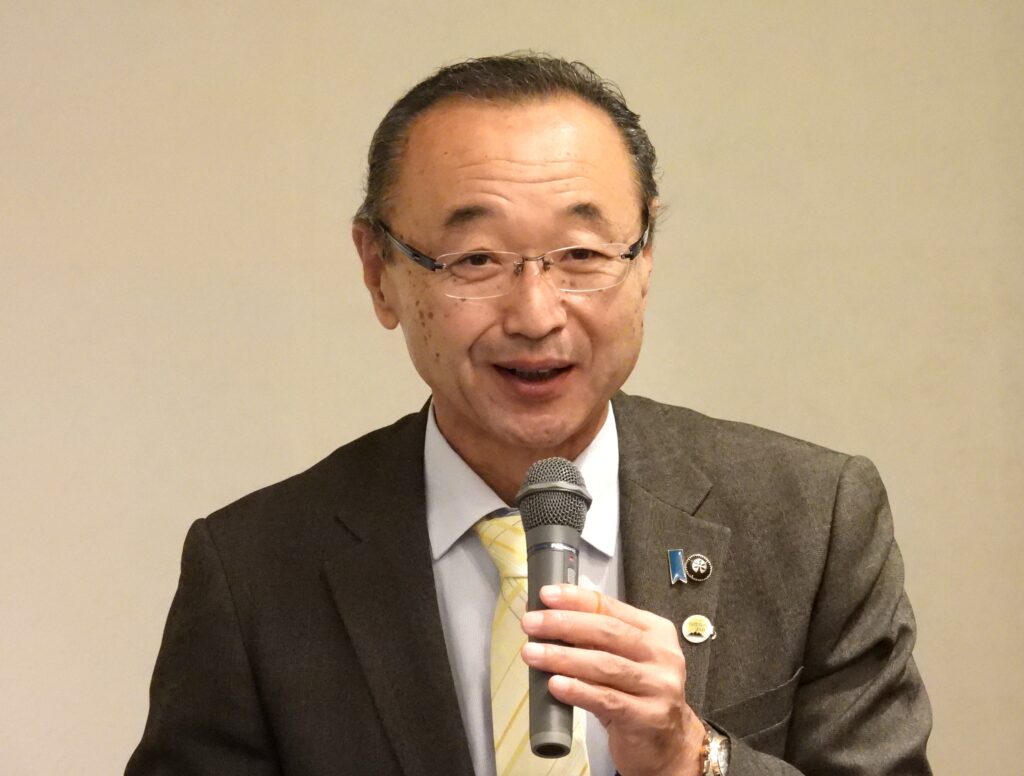
設立総会は富山・高岡で開催予定
設立総会は令和8年1月下旬頃に富山県高岡市の生涯学習センターで開催される予定で、オンラインを併用したハイブリッド形式も検討されている。日時は、今後調整の上で決まる。
閉会にあたり、発起人である石川県輪島市の坂口茂市長は「震災からの復興過程においても、工芸文化は地域の誇りであり、未来を切り拓く力になる。全国の仲間と共に一歩を踏み出したい」と述べ、会は締めくくられた。

取材 ツーリズムメディアサービス編集部











