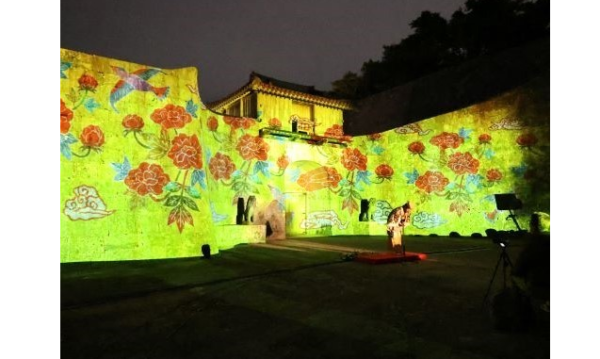北前船を軸に全国52自治体が参画する北前船日本遺産推進協議会。各地に残る港町の文化を再評価し、歴史を未来につなぐ取り組みが続いている。その延長線上で11月21日には、新たに「北前船伝統的工芸品ネットワーク(仮称)」の立ち上げに向けた発起人会が長野県松本市で開かれた。この動きの中心となり、発起人である3首長に加え、国から有識者、北前船交流拡大機構の実務者が集まり、工芸が直面する課題と今後の可能性について意見を交わす座談会が発起人会の同日に実施された(会場は、長野県松本市のホテルブエナビスタ)。
座談会には、発起人代表である新潟県村上市の高橋邦芳市長、発起人の石川県輪島市の坂口茂市長、同新潟県佐渡市の渡辺竜五市長のほか、有識者として財務省理財局国有財産企画課政府出資室の二宮悦郎室長、そして北前船交流拡大機構の浅見茂専務理事が参加した。進行役は内閣府地域活性化伝道師や総務省地域力創造アドバイザーなどを務める跡見学園女子大学の篠原靖准教授が務め、各地域が抱える状況や今後の方向性が具体的に語られた。
座談会では、全国の産地で進む「静かな危機」を背景に、広域連携の必要性が各首長から語られた。進行役を務めた跡見学園女子大学の篠原准教授は冒頭、「伝統工芸は産業と文化の境界にあり、地域だけでは解決しきれない課題が増えている。広域で知恵を持ち寄る時期に来ている」と指摘した。
「このままでは承継できない」 村上市・高橋市長が持つ危機感
高橋市長は、日本遺産の認定を得たことを契機に実施した工芸産地調査で、後継者不足や技術喪失の危機が極めて深刻であったことを明かし、「村上が認定されたことで地域の文化的価値を整理する機会を得たが、調査を重ねるほど『このままでは将来に承継できない工芸』が全国に点在している現実が見えてきた」と述べた。中には生産体制が崩れつつある産地もあり、技術が途切れれば再生が難しい業界も多い。
また、高橋市長は伝統工芸の構造的課題にも触れた。「多くが少量生産・高付加価値型で、地域だけの努力では維持が難しい。販路開拓や若手育成など、広域での取り組みが欠かせない」と述べ、今回のネットワーク発足の必要性を示した。

「今しかない」 佐渡市・渡辺市長が語る現場の変化
渡辺市長は、かつて若手陶芸家の集積で知られた「無名異焼」が現在は2軒のみになった現実を語り、産地が急速に縮小する背景を説明した。「40年前は若手10人が集い、人間国宝を目指すような熱気があった。しかし時代とともに、家業を継がない選択をする若者が増え、産地が維持できない局面が一気に表面化した」と話した。「伝統的工芸品の認定を“あえて受けない”職人もいたほど、誇りと葛藤があった」とも明かした。
さらに渡辺市長は、備前焼など他産地の視察を通じて、外部との接点が産地再生の重要な契機になると実感したことを語った。「文化への関心は海外で確実に高まっている。島の中だけで完結していては未来は描けない。今、動かなければ間に合わない」と述べ、広域連携への強い期待を示した。

輪島塗の再起へ、輪島市・坂口市長「手を動かす場がなければ技術は落ちる」
坂口市長は、能登半島地震で85%の工房が被災し、職人が手を動かせなくなった実情を説明。「技術は繊細で、期間が空けば確実に落ちてしまう。被災はその危機を一気に表面化させた」と語った。輪島市では仮設工房の整備や若手育成校の立ち上げを進めているが、「復旧需要がピークを過ぎた後、市場が縮む可能性は避けられない」とし、長期的な販路拡大の必要性を強調した。
さらに「国内市場だけでは産地を支えきれない。海外展開に挑戦し、全国の産地と横連携することで技術を維持できる」と述べた。輪島塗のように高度な分業制を持つ産地は、「一度途切れれば再構築は困難」との危機感も示した。

「日本工芸の曖昧さは、海外では強み」 財務省・二宮室長が語る市場性
議論の後半では、工芸の海外展開の可能性が焦点となった。財務省の二宮室長は、欧州での経験から日本工芸の評価と課題を語った。
「欧州では『日本の工芸は品質が高く独自性がある』と確かな評価がある。しかし作り手自身がその価値を十分に理解していないケースも多い」と指摘。日本工芸が持つ「実用品であり、芸術品でもある」というあいまいさについては、「その境界を行き来するあいまいさこそ海外では魅力になる」と述べた。一方で国内では、このあいまいさが所管省庁の不明確さや支援の遅れにつながったと分析した。
二宮室長は、「海外経験を持つ職員が全国的に少ない。意欲ある自治体がまずモデルをつくり、成功例を横展開すべきだ。北前船ネットワークは、そのプラットフォームとして最適だ」と述べ、広域展開への期待を示した。

若手デザイナーの力 北前船交流拡大機構・浅見専務理事の実感
北前船交流拡大機構の浅見専務理事は、イタリア・ミラノで出展した「ミラノ・サローネ」など海外展示の現場を通じて感じた現状と可能性について語った。浅見氏が強調したのは「若手デザイナーとの協働」が工芸に新たな光を当てている点である。
「ミラノ・サローネにおける35歳以下の若手デザイナーによるプロトタイプ展示『サローネサテリテ』では、日本の20〜30代デザイナーが継続的に高い評価を受けている。若手の感性と工芸の技が結びつけば、新しい市場を切り開く力が生まれる」と述べ、工芸×デザインの相乗効果に注目した。
浅見専務理事はまた、展示が単発のイベントで終わる現状にも触れた。「現地での反応を次の制作に生かし、産地間でも共有できる『循環型の仕組み』を整える必要がある。広域ネットワークができれば、経験を蓄積し共有する仕組みをより大きく育てることができる」と述べ、組織的な展開への期待を示した。

北前船のつながりを、未来の工芸へ
座談会の終盤では、同ネットワークの発起人である3首長がそれぞれ今後の展望を示した。高橋市長は「北前船の歴史がつないだ52自治体の中には、工芸を持つ地域が21もある。課題を共有し、方向性を一致させることで、工芸の未来に向けた大きな力が生まれる」と語った。
坂口市長は「海外展開に踏み出すことでデザインや価値提案が革新され、国内市場にも新しい波が起きる」とし、広域連携が産地の再生に向けた推進力になるとの考えを述べた。渡辺市長は「鍵は情報発信だ。優れた文化資源であっても伝えなければ届かない。国内外へ積極的に発信し、その反応を職人へと返すことが必要だ」と述べた。
有識者の立場から、二宮室長は「工芸がもつ『実用品とアートの両面性』は日本独自の強み。これを十分に翻訳して海外へ伝えられれば、市場は確実に広がる」と指摘したうえで、「一自治体では成立しない取り組みを共同で進める意義は大きい」と広域連携に期待を寄せた。
実務者として現場を見続けてきた浅見専務理事は、「若手デザイナーの感性と工芸技術が結びつく現場では、確かな手応えが生まれている。ネットワークが育てば、その成功例を産地間で共有でき、循環的に発展させられる」と述べ、継続的な仕組みづくりの重要性を強調した。
篠原准教授は、「北前船はかつて、人と物と文化をつないだ流通の要だった。今回の取り組みは、その『つなぐ力』を工芸の世界で再現する試みだ。地域単独では難しい課題も、連携することで未来を描ける。ここから次の展開が始まる」と総括した。

北前船はかつて、地域ごとに異なる文化や技術、人々の営みをつなぐ役割を果たした。その歴史的な航路が、今度は日本の工芸を未来へと導く新たなネットワークとして動き出そうとしている。日本の技を守り、育て、世界へ届けるための挑戦は、ここから本格的に進むことになる。
取材 ツーリズムメディアサービス編集部 長木利通