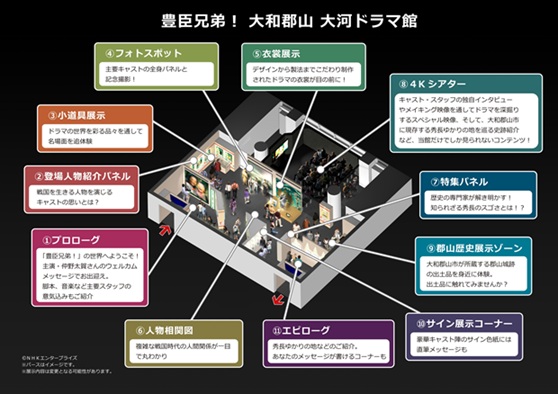神奈川県三浦市は11月29、30日、「三崎マグロのルーツは江戸にあった! ‘’江戸海道‘’がつなげたマグロと江戸の物語を訪ねてモニターツアー」を開催した。江戸と三浦を結ぶ「江戸海道」がテーマ。2027年(大河ドラマ、ディスティネーションキャンペーン神奈川、花博)に向けて三浦を「食のまち」としてリブランディングが図られている。今回は、同モニターツアーの様子を紹介する。
モニターツアーは、観光庁が令和8年度に取り組む「地域観光魅力向上事業」の一環として実施。行程には、市内の史跡や伝統芸能、漁港、農村景観、地場食材、飲食店などの市内観光資源を立体的に組み合わせられ、三浦市が掲げる「食のまち」としてのポテンシャルを体感できる内容となっている。今回のモニターツアーは日帰り5人、1泊2日5人の計10人が参加した。
【初日】三崎城址から城ヶ島へ 歴史と海に触れる
伝統芸能「チャッキラコ」から始まる三崎の物語
三浦市は初日、京浜急行電鉄(京急電鉄)の三崎口駅で集合。三浦市役所第二分館で江戸海道と同事業の趣旨が紹介したあと、三崎城址や北条湾周辺を歩き、城下町として栄えた三崎の成り立ちが解説された。湾を見下ろす高台からは、漁港と町並みが一望でき、海とともに生きてきた地域の歴史が実感できた。

続いて、「チャッキラコ三崎昭和館」を訪問。チャッキラコは、少女たちが扇と稲わらの束を手に新年の豊漁・商売繁盛を祈って踊る三崎の民俗芸能で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。館内では昭和初期に撮影された貴重な映像や保存団体による実演を鑑賞するほか、参加者自身も踊りの一部を体験した。三浦市は「食だけでなく、地域の暮らしと信仰を支えてきた文化そのものを伝えたい」と話す。

寿司で知る、三崎まぐろの奥深さ
昼食は、老舗寿司店「紀の代(きのだい)」で、地元で水揚げされたまぐろを中心に、白身魚や白子、アナゴの天ぷらなどを織り交ぜたにぎり寿司のコースが提供された。

脂の乗った赤身や中トロになどに、「同じまぐろでも味わいがまったく違う」と参加者の驚きを誘った。市は、三崎まぐろのブランド力を再認識してもらう場とした。

海南神社と常夜灯楼 江戸と三崎を結んだ信仰と物流
午後は、三浦市は三崎の産土神である海南神社へと歩を進めた。海上安全と豊漁の神として崇敬を集めてきた同社の境内には、日本橋の魚市場関係者が寄進した「日本橋新肴場寄進常夜灯楼」が建つ。

江戸の市場と三崎の港が、海上輸送で密接につながっていた証しであり、昇殿参拝の後、灯楼の由来などが詳しく説明された。休憩時には、ところてんをアレンジしたスイーツが供され、海藻文化が根づく三浦らしい一品として好評を得た。

※日帰り参加者の行程は終了。
船で自転車を運ぶ「海の道」、城ヶ島灯台から夕陽を望む
続いて参加者は、産直施設「うらりマルシェ」から船に自転車を積み込み、城ヶ島へと向かった。漁船やヨットが行き交う海を横切る移動そのものを体験コンテンツと位置付け、江戸時代から続く「海の道」を実感してもらう趣向だ。

城ヶ島に上陸すると、島内をサイクリングで周遊した。城ヶ島海岸からは、断崖絶壁が続く海岸線の景観を楽むほか、クライマックスとして城ヶ島灯台周辺から夕陽を眺望。水平線に沈む太陽と赤く染まる空と海に、参加者からは感嘆の声が上がった。「食の旅」でありながら、景観体験も含めて五感すべてで三浦を感じられる内容となった。
三崎宿と「くろば亭」 暮らすように泊まり、地域を学び・味わう
夕刻は、一棟貸し宿泊施設「三浦半島の旅宿 三崎宿」に到着。かつての蔵などをリノベーションした宿は、歴史的な建物の風合いを残しつつ、現代的な設備を整えた造りで、「城下町に住むように泊まる」時間が演出されている。同宿は、三浦市における今後の泊食分離型観光モデルの拠点の一つと位置付けられている。三崎宿は市内に「蔵宿」「旅宿」「酒宿」「本陣」など、7棟を展開している。

夕食会場は、地元で人気のまぐろ料理店「くろば亭」。まずは店前で、巨大なまぐろの頭部を使ったダイナミックな解体ショーが行われ、包丁が骨に当たる音や脂の切り口の輝きに、参加者は食材への敬意を新たにした。店内では「まぐろ一匹黒船フルコース」が提供され、内臓珍味や、本マグロ希少部刺身のほか、煮付け、揚げ物、寿司など、まぐろを使った「頭から尾まで余すところなく味わう」文化を体感した。


夕食後には、老舗の「三冨染物店」で大漁旗の絵付け体験が行われた。漁師の無事と大漁を願って掲げられてきた大漁旗は、三浦の港町を象徴するアイコンだ。これまで一般向けの体験としては行われていない「大漁旗下絵制作体験」を新たな観光コンテンツとしての可能性を試す形で実施。参加者は職人の指導を受けながら、手に下絵制作で使うのりを手にしながら多様な線を描き入れた。

【2日目】漁港の朝から海防の記憶へ 三浦の暮らしと歴史を体感する
漁港の朝からスタート 「働く現場」を見学
2日目の朝、参加者は三浦市の案内で、三浦市三崎水産物地方卸売市場内にある「魚市場食堂」へ向かった。まだ市場に活気が満ちる時間帯、場内で働く人々に混じって席に着く。朝食として供されたのは、脂がたっぷりとのった鮭ハラス焼きと、刻んだまぐろを贅沢に盛り付けたまぐろのたたきが一皿で味わえる定食だった。香ばしく焼かれた鮭の旨みと、まぐろの濃厚な味わいが口に広がり、参加者からは「朝からこれほどの内容とは思わなかった」と驚きの声も上がった。日々市場で働く人々が食べている普段の朝ごはんを共に味わうことで、三浦の食が暮らしの中に根づいていることを実感する時間となった。

食後は、近海ものの競りが行われる市場と、まぐろの入札を行う市場を見学するほか、上層部から城ヶ島や海を望んだ。展示を通じて三浦の海と人の関わりを学んだ後は、海防陣屋跡へ移動。専門ガイドが三浦の地が江戸時代に異国船の来航に備える最前線だったことをフリップなどを使いながら解説。ペリー来航時の緊迫した状況や、沿岸防備のために築かれた砲台の役割を、地形を指し示しながら説明した。参加者は当時の緊張感に思いを重ねた。

市場の食から始まり、海防の歴史へと視点を広げる行程は、三浦が単なる食の観光地ではなく、国の行く末を見据えてきた土地であることを浮かび上がらせた。味覚だけでなく、土地の記憶や時間の重なりを感じるひとときとなった。

干し大根と太鼓の響き 三浦海岸で農と文化の現在を見る
三浦海岸まで足を運ぶと、冬の風物詩である三浦大根の天日干しの光景が広がっていた。浜辺一帯に白い大根が吊るされ、海風に揺れる様子は、沢庵漬けづくりのための工程であり、農漁村の暮らしと気候が密接に結びついていることを物語る。

海岸では、海防陣屋太鼓の生演奏も行われるほか、太鼓の担ぎ手から指導を受けて実際に打つ体験をした。波音と太鼓の響きが混ざり合う中で、「今を生きる文化」としての太鼓の魅力が伝えられた。

昼食は「さかな料理まつばら」で、江戸時代に大名が好んだとされるねぎま鍋と、まぐろの切り身や生シラスをふんだんに盛り込んだ三浦丼が提供された。ねぎまとは本来、脂の乗ったまぐろのトロと葱を煮込む鍋料理で、江戸の庶民から武家まで幅広く愛された。三浦市はこれを、自らのまぐろ資源と結びつけた歴史あるご当地鍋として再評価し、今後ブランド化を進める考えだ。

快晴のサイクリングで畑の中へ サンコロ石と天神丸
午後は快晴の空の下、参加者はサイクリングで三戸浜方面へと向かった。ペダルを進めると、道の両脇には大根やキャベツなど冬野菜の畑が一面に広がり、海から吹き付ける風が作物を揺らす。視線を上げればすぐ先に海が見え、畑と海がこれほど近接する風景に、参加者は足を緩めながら周囲を見渡した。

道中では、黒船来航にゆかりがあると伝えられる「サンコロ石」などの史跡にも立ち寄り、異国船を警戒していた当時の緊張感に思いを巡らせた。参加者からは「都心からこれほど近い場所で、海と畑の両方を一度に楽しめるのは貴重だ」との声が聞かれた。

サイクリングを終えた一行は、海辺にたたずむ「三戸カフェ」でひと息ついた。ここで振る舞われたのは、新名物として注目される「黒船ところてん」。透明感のあるところてんの上にソフトクリームを重ねたスイーツで、黒船をイメージした見た目が印象的だ。磯の香りをほのかに残すところてんと、冷たい甘さのソフトクリームの意外な組み合わせに、参加者は「さっぱりしていて食後にちょうどいい」「三浦らしい発想」と笑顔を見せた。

ツアーはその後、再び三崎口駅へと戻り、解散となった。2日間を通じて、参加者は三浦の海と畑、そこに積み重ねられてきた歴史や文化が互いに結びつき、現在の食や暮らしを形づくっていることを肌で感じた様子だった。単に名所を巡るのではなく、土地の営みを体感する旅として、強い印象を残す行程となった。
「食のまち三浦」へ 地域ぐるみでの横展開を図る
三浦市は、今回のモニターツアーを通じて得られた声をもとに、地場産品消費拡大協議会飲食分科会を中心に、ねぎま鍋やまぐろづくしメニューの横展開、泊食分離型への対応強化を図る方針だ。城下町の宿に泊まり、夜はまちへ繰り出して地元の料理店を巡るスタイルを確立することで、「泊まる」「食べる」「歩く」を分けて楽しむ観光のあり方を提案していく。

2027年には、大河ドラマや国際園芸博覧会(GREEN × EXPO 2027)花博など、神奈川県に注目が集まる大型イベントが予定されている。三浦市はそれまでの期間を「食のまちづくりを確立する助走期間」と位置づけ、江戸海道のストーリーとともに、まぐろ、三浦野菜、伝統芸能、港町文化を束ねた新たな観光ブランドの確立を目指す考えだ。今回のモニターツアーは、その方向性を具体化する一歩として、三浦市の取り組みの可能性を強く印象づけるものとなった。
取材 ツーリズムメディアサービス編集部