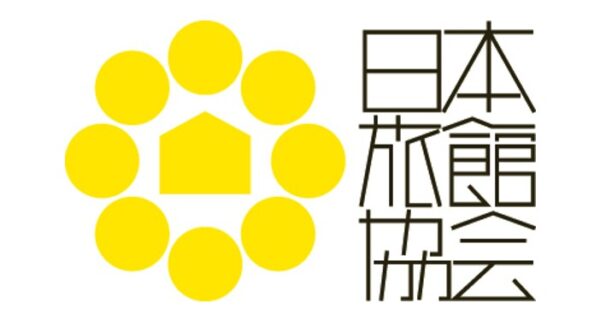2025年4月13日から10月13日まで、2025年日本国際博覧会(略称:大阪・関西万博)が行われる。その舞台は、大阪湾に浮かぶ人工島「夢洲(ゆめしま)」だ。吹田市千里で日本万国博覧会が開催されてから55年の時が流れた。
冒頭の写真からもわかるように、既に会場にはメインパビリオンを囲む空中回廊「大屋根リング」も見える。(左下の五角形の島が「夢洲」)
そして、2月22日は開催までのカウントダウン、50日前である。関連するイベントがJR大阪駅などで行われる予定だ。

https://osakaschedule.jp/?p=80075
大阪・関西万博のホームページは、こちら
水都「大阪」
水の都と呼ばれてきた大阪は、西の大阪湾に淀川が注ぎ込む。北に六甲や北摂の山々、東に生駒、金剛山地、南に和泉山脈に囲まれている。そして、その土地の多くは、干拓や埋め立てによって形成されてきた。そのため、地下水くみ上げによる地盤沈下が発生している場所が少なくない。
大阪の町は、古代より中国や朝鮮半島との往来の拠点としていくつかの港が開かれた。それらは、住吉大社の西に住吉津や中央区三津寺付近の難波津。また、現在の堂島川周辺の渡辺津や江口、堺市の榎津が代表例である。そして、難波津に難波京が置かれ、奈良時代から平安時代の朝廷の玄関口となっていた。
秀吉が町を大変革する
豊臣秀吉が大坂城を造営すると河川改修を進める。淀川から分かれる大川(旧淀川)を外濠として数多くの掘割が開削される。広い街路や太閤下水を築き、町家の高さを統一した。その結果、整然とした城下町が造り上げられた。
城郭西側の船場(せんば)が「水の都」と呼ばれる街の原型となる。そして、縦横無尽に広がる堀川は、大阪の物流の動脈として「天下の台所」を支える重要な役割を担った。300年余り廃れることがなかった。

江戸時代ともなると、京都と大坂を結ぶ商業荷物や建築資材を運搬する船や物見湯山の行楽船、旅客船が行き交う。そのため、大阪は数多くの船によって、にぎわいを見せた。
今回の万博でも、京都伏見から夢洲に向けて、「舟運」を活用した観光コンテンツも復活されると言う。
クルマ社会からの再生
第二次世界大戦の後、クルマ社会が到来した。そのため、市中の川や堀は埋め立てられていく。心斎橋や四ツ橋、長堀橋などの橋の名を冠した地名が残っていることは、その名残である。
2001年、大阪の水に親しむ再生の取り組みが、内閣官房・都市再生プロジェクトに指定される。それを契機に親水空間の整備やにぎわいづくりなどのプロジェクトが展開された。
2004年には、道頓堀川沿いの遊歩道整備がオープン。憩いの場を形成、川沿いの店舗が増えている。そして、2008年には、かつてのにぎわいを再現する船着場を八軒家に作る。また、堂島川沿いには福島港(ほたるまち港)も開港する。
一方、大阪の歴史・文化の中心である中之島エリアは、2010年に中之島公園が親水性を高めた都市空間として再整備、水都大阪のシンボル景観となっている。
歴史を刻んできた淀川の流れ
大阪の町は、淀川が作り上げたと言っても過言ではない。大阪平野を俯瞰すると、そのルーツを垣間みえる。
京都の町中には、鴨川と桂川が流れる。そして、双方は市街地南部で合流する。その後、琵琶湖に端を発する宇治川と奈良との県境からの木津川が合流して、淀川と名前を変える。そのため、平安京の時代から国内外との交流手段として水運が発達した。
また、合流する辺りは、南側は石清水八幡宮、北側は大山崎、天王山と山が迫まり、交通の要衝となる。それ故、豊臣秀吉と明智光秀が、この地で天下取りの戦いを行なったことも重要な場所であったことがうかがえる。
それ故、秀吉は天下統一後、この淀の地に城を築く。茶々こと、淀君の名前の謂れである。京都から大坂への街道整備も進められた。伏見から大坂までは、三十石舟が行き来して、陸運、水運ともに大きく発展し、大阪が「水都」と呼ばれる原型を作り上げた。
大阪・関西万博がもたらすもの
30年前の阪神大震災以降、大阪経済は停滞したと言われ続けている。経済をリードしてきた町も、首都圏への一極集中を回避できずに企業・団体が低迷している。しかし、関西圏には、首都「東京」にない素晴らしいモノ・コトが数多く残されている。大正ロマン・昭和レトロと言われる凝った建造物や縦横にめぐる運河を活用した舟運観光の精度の高さなど、観光コンテンツとしての価値は高い。これは、隣に京都を配することもその要因と言える。
東京は、常に開発され続け、日一日と「昭和喪失」を目の当たりにする。一方、大阪は、水上バスや屋形船、クルーズ船などを活用し、かつての善きモノを残している。その意味からも、万博期間中の伏見から大阪への水辺に触れる観光船は、大阪観光の新たな切り口となるものと考える。
浪速のことは、夢のまた夢・・・
入場券の販売状況が芳しくないと言われる万博。さまざまな悪いニュースも拡散されている。しかし、地下鉄「夢洲駅」の開業や数多くのパビリオンの完成といった明るいニュースも聞かれる。
会期に入ると「万博、行ってみようか」などという話題も、必ず増えてくると考える。天気予報の精度が上がり、予約が直近化することも規定路線。それ故、当日券販売もやむないと感じる。
万博が成功裏に終了し、私たちが今年末を振り返る時「2025年は大阪が熱かった!」と語られることを望みたい。秀吉も、そう思ってくれることであろう・・・。

寄稿者 観光情報総合研究所 夢雨/代表
(これまでの寄稿は、こちらから)https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=181





円形.jpg)