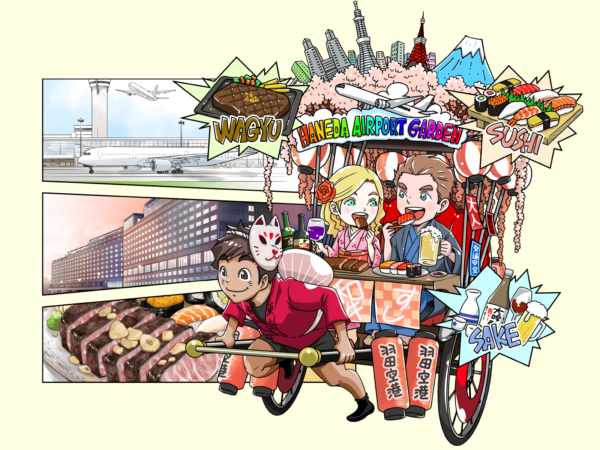戸隠神社は、宝光社、火之御子社、中社、 九頭龍社、奥社(旧奥院)の五つの社を配する。10世紀から11世紀にかけて創建された。その中でも、九頭龍社と奥社は紀元前と言われている。
平安時代には天台・真言密教と神道が習合していた。そのため、神仏混淆の戸隠十三谷三千坊と呼ばれる修験道の聖地であった。その後、天台・真言両宗の法論闘争が繰り返される。しかし、江戸時代に入り、寛永寺の末寺となり「戸隠山領」が成立した。その結果、修験道場から門前町に変わった。
明治時代になると、神仏分離令、修験宗廃止令によって廃仏毀釈が起きる。その結果、戸隠山顕光寺から戸隠神社と変わり、独立した存在となる。
さて、ここ奥社は、戸隠山が神話に記される「天岩戸」とされている神域だ。そして、長野市内から一番遠くに位置する奥社は、まっすぐ2kmほどの参道が伸びている。また、途中には赤い山門「隋神門」があり、山門越しに立ち並ぶ杉並木が荘厳さを見せている。その先の本殿内部には「本窟」「宝窟」という非公開の窟がある。まさしく、今に残された「天岩戸」である。苦労して歩いてきた社は、神秘さを感じる。
早朝から奥社を目指す参詣人は多い。神々しい兆しが人の穢れを払拭してくれるようだ。
(2009.10.29.撮影)
(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8
取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長





.jpg)