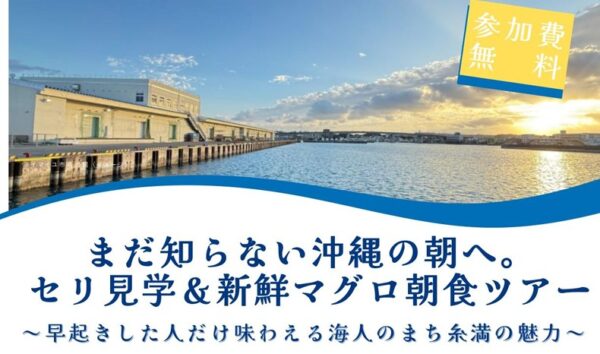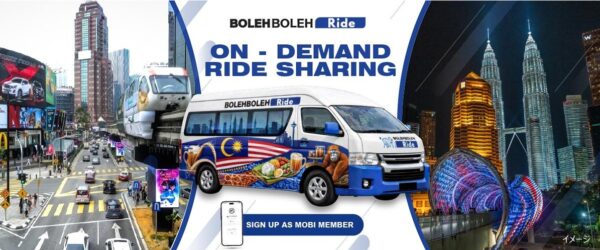先ごろ開催された旅行テクノロジー業界の国際会議「WiT Japan & North Asia」では、「Japanese OTAs: Building For The Next Age」として、毎年恒例の国内OTAのセッションが開催された。今回は楽天、リクルート、JTBといったおなじみのメンバーに加え、旅のサブスクリプションサービス「HafH」を運営するKabuK Styleも参加。AIの活用を中心に議論が交わされた。
4社のAI活用状況は?顧客対応にどの程度有用?
パネルディスカッションでは、モデレーターを努めたWiT Japan共同創業者でベンチャーリパブリック代表取締役社長の柴田啓氏が各社にAIの活用状況を尋ねた。
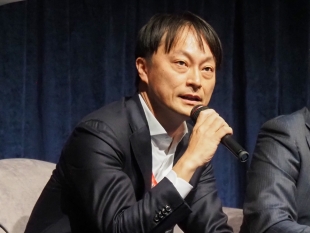
これに対し、楽天グループ トラベル&モビリティ事業 事業戦略部ジェネラルマネージャーの皆川尚久氏は、これまでのバックヤードでのAIの活用に加え、新たに昨年からAIを活用したユーザー向けのコンシェルジュサービスを試験的に導入していることを説明。「詳細を話せる段階ではないが、ユーザーの動向を見ながらプロダクトを改善し、実用化に向けていきたい」と話した。
リクルート 旅行ディビジョン Vice Presidentの大野雅矢氏は、昨年と同様、試験導入中の「じゃらんAIチャット」について言及。利用者のコンバージョンレート(CVR)が高いというメリットがある一方、「活用している絶対数が限られており、全面的な導入に至っていない」と現状を述べた。
JTB Web販売事業部長の岩田淳氏は「会社として活用が進んでいないのが現実」としながらも、社員の意識変革に取り組んできたことに触れ、現在はマーケティングのオートメーション化やツアーの値付けなど、内部で活用し始めている旨を語った。ただし「お客様に向けたサービスにたどり着くまでは、まだ計画が必要」という。

KabuK Style代表取締役の砂田憲治氏は、展開するサブスクサービス「HafH」で価格・行動・キャンセル予測を実施していることを説明した。現在は客室タイプのマッピングに注力しているが、日本の客室タイプの表記が統一されておらず、「世界的にかなり特殊なマーケット。マッピングが進まなかった」と振り返った。ただし、この1年で精度を約8割まで上げており、「どこかでリスクをとればディストリビューション可能なレベルになってきている」という。
また、同氏は生成AIの活用として、公式LINE上で旅行相談ができるAIサービス「ハフっち」の提供を開始したことを説明。そのうえで、AIのさらなる活用を見据え、「来年のWiTの大きなテーマがMCP(Model Context Protocol)になっているのでは」と持論を語った。MCPとは、AIとPMSやサイトコントローラなどさまざまな外部システムをスムーズにつなぐための標準プロトコル、つまり仕組みのこと。MCPを利用すれば、共通フォーマットでデータがやり取りできるようになるため「AI用のUSBポート」とも例えられている。
AIを活用した10年後の旅行の姿とは 流通における課題も
また、ディスカッションでは、柴田氏がAIの発展を踏まえたうえで「10年後の旅行はどのように変化しているか」を質問した。これに対し、楽天の皆川氏は「旅行の検討段階から予約完了まで一気通貫でできるようになる」と予測。加えてパーソナライズされた世界で、AIによるさまざまなコンシェルジュサービスが実現しているとの考えを語った。ユーザーインターフェイスも現在のスマートフォンから「これまでと全く違うユーザー体験が提供される」との見通しだ。

JTBの岩田氏も、AIがパーソナライズされたコンシェルジュサポートを提供する旅行が一般化すると予想した。その一方で、旅行者があえてAIを使わず、未知の体験を求めて旅行を自分で計画・手配するケースも増えると予想。「情報を得てから行くのではなく、初めて旅行先を訪れたときに感動を得る場面がある、そうした経験を求めるお客様も増えてくるのでは」と話した。
リクルートの大野氏は、AIにより旅行者と各地の観光事業者のマッチングが進むと予想した。ただし、「10年後の予測は難しい。大きなイメージを持ちつつ、手探りで現実に即した手を打つ努力をしなければならない」とも話した。
一方で「現在と変わらない」と回答したのがKabuK Styleの砂田氏だ。AIの活用による更なる発展は技術的には可能としながらも、そのために必要な大量の学習データを旅行会社が自社で囲い込み、共有しないことが障壁になっていると指摘。旅行業界の発展のためにはデータを開放してオープンな環境を作るべきと主張した。
続いて柴田氏が「OTA以外に10年後に旅行流通でそれなりのシェアを獲得しているプレイヤーは?」と尋ねた質問では、楽天の皆川氏が「全く違うユーザー体験を提供できるAI専業プレイヤー」、JTBの岩田氏が「サプライヤーの直販、またはそれを束ねる企業」と回答した。

一方、リクルートの大野氏は「AIエージェント的なプレイヤーがユーザー接点をとる」としながらも「事業者の経営・業務支援など深いところに入り込めば、日本固有のマーケットで我々自身のプレゼンスを高められるのでは」と語った。
砂田氏は音楽業界を例に10年後の展望を説明。音楽業界ではストリーミングサービス「Spotify」が人気で収益を挙げているが、「その裏でレーベル側もしっかりと収益を確保している」ことに触れ、「旅行業界もそういった構図になることはありうる」との見解を示した。
ただし、旅行業界の課題として「商品在庫へのアクセスが難しい」点を説明。特に日本の旅館が顕著だが、大手旅行会社やOTAが在庫を独占する傾向にあるという。砂田氏はAIエージェントの台頭などにより、大手旅行会社やOTAとコンシューマーとの接点が減少することがありうるかもしれないとしながらも「なかなかひっくり返すのは難しい」との考えを述べた。
情報提供 トラベルビジョン(https://www.travelvision.jp/news/detail/news-117913?pg=2)