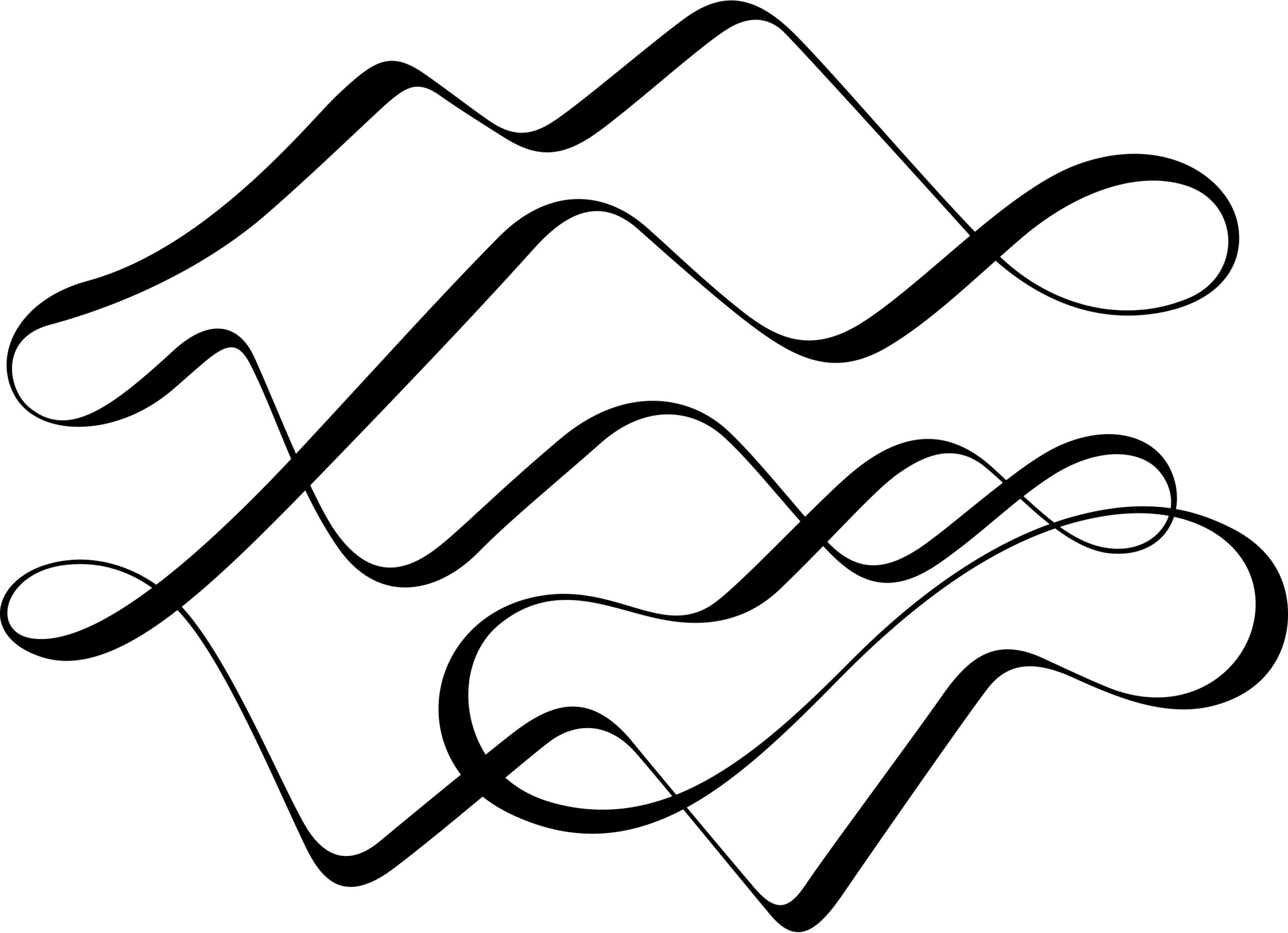JSTS-D(Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations、日本版持続可能な観光ガイドライン)は、日本の観光地がグローバルな旅行市場で選ばれ続けるための羅針盤である。国連世界観光機関(UNWTO)の国際基準に準拠しつつ、日本の文化や実情に合わせて策定されたこの指標は、単なる環境配慮にとどまらない。オーバーツーリズム対策から地域経済の活性化、文化振興まで、観光地経営が直面する多様な課題を解決するフレームワークを提供する。
本稿では、JSTS-D導入がもたらす7つの具体的なメリットと、その実践に向けた7つのステップを詳説する。
JSTS-Dが観光地経営の未来を拓く7つのメリット

JSTS-Dの導入は、観光地にとって多岐にわたる戦略的価値を持つ。
- 国際競争力の飛躍的向上
世界の旅行者のサステナビリティへの関心は、今や旅行先選定の主流となりつつある。特に欧米豪の高付加価値市場では、持続可能性への配慮が不可欠である。国際基準に準拠したJSTS-Dへの取り組みは、こうした審美眼の厳しい旅行者層に対する最も強力なアピールとなる。 - 世界基準の「お墨付き」による信頼性獲得
JSTS-DはUNWTOなどが提唱する世界基準に準拠している。このガイドラインに沿った取り組みは、単なる自己満足ではなく、国際社会から「信頼できる持続可能な観光地」としての評価を得るための客観的な証左となる。事実、JSTS-Dモデル地区は国際的な表彰制度で選出されるなど、具体的な成果を上げている。 - 日本の実情に即した唯一の国際公認指標
海外で開発された指標をそのまま導入するには、文化や慣習の違いから多くの障壁が存在する。JSTS-Dは、日本の風土や社会に合わせて開発されているため、地域が過度な負担を感じることなく、実情に即した形で持続可能な観光に取り組める点が最大の強みである。 - 観光地が抱える多様な課題への対応力
その適用範囲は、オーバーツーリズム対策や環境保全にとどまらない。危機管理、戦略的な誘客促進、雇用の創出と安定、そして地域固有の文化保護まで、観光地経営が直面するほぼすべての課題に対応できる包括的な指標となっている。 - 客観的な自己分析による現状把握と施策の明確化
JSTS-Dは、地域が「何ができていて、何ができていないか」を客観的に可視化する「自己分析ツール」として機能する。これにより、地域の強みと弱みが明確になり、限られた資源をどこに投下すべきか、取るべき施策の優先順位を合理的に判断できる。 - 多様な関係者間の合意形成を促す「共通言語」
持続可能な観光地経営は、行政、DMO、民間事業者、そして地域住民など、多様なステークホルダーの連携なくしては実現しない。JSTS-Dは、これらの関係者が同じ目標を共有し、対話し、協働するための「コミュニケーションツール」となり、地域一体となった取り組みを強力に推進する。 - 地域ブランドの価値向上とプロモーション強化
「JSTS-Dロゴマーク」の使用は、地域が持続可能な観光に取り組んでいることの何よりの証明となる。この取り組み自体が旅行商品としての付加価値となり、地域のブランディング力を高め、国内外へのプロモーション活動において強力な武器となる。
のFAQを公開しました-2-1024x576.png)
JSTS-D導入を成功に導く7つの実践ステップ
JSTS-Dの導入と運用は、以下の7つのステップで進めることが推奨されている。
- 実施主体における意識の醸成
まず、行政やDMOなどの実施主体がJSTS-Dの意義と目的を深く理解し、関係者へその重要性を伝え、協力体制の基盤を築く。 - 観光地プロフィールの作成
地域の歴史、文化、自然環境、観光資源などの基本情報を網羅したプロフィールを作成し、関係者間で地域の現状に対する共通認識を醸成する。 - ワーキンググループ(WG)の形成
観光関係者だけでなく、都市開発、環境、農林水産、文化、医療など、地域を構成する幅広い分野からメンバーを招集し、横断的なWGを組織する。 - 役割と責任の明確化
WGの各メンバーが担当する指標項目を明確に割り振り、データ収集や取り組みの実施における責任の所在を確立する。 - データ収集と取り組みの着実な実施
各項目に基づき、必要なデータを収集・記録し、具体的な改善策を実行に移す。最初からすべての項目に完璧に取り組む必要はない。地域にとって最も重要、あるいは着手しやすい項目から始めることが、継続の鍵となる。 - 結果の分析と評価
収集したデータや取り組みの成果を定期的に分析・評価し、目標達成度や改善の進捗を確認する。 - 継続的な改善(PDCAサイクルの実践)
分析結果に基づき、次の計画(Plan)を立て、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)を繰り返す。このPDCAサイクルを回し続けることで、持続可能な観光地経営は着実に進化していく。
未来への投資としてのJSTS-D

JSTS-Dは、単なる認証取得を目的とするものではない。それは、自らの地域の強みと弱みを客観的に把握し、多様なステークホルダーが同じ未来図を描くための「共通言語」であり、持続可能な観光地経営を実現するためのPDCAサイクルを回し続けるための「実践ツール」である。
未来の世代に豊かな地域資源を受け継ぎ、世界から選ばれ続ける観光地であるために、今こそJSTS-Dという羅針盤を手に、新たな航海へ乗り出すときではないだろうか。
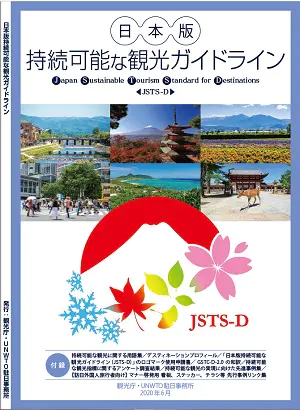
日本版 持続可能な観光ガイドライン( JSTS-D) は下記のリンクよりご覧いただけます。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810000951.pdf
寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しました-2-1-1024x576.png)