観光庁のJSTS-Dは、日本の観光をどう変えるのか。京都の観光モラル、阿蘇の体験型観光、白川郷の文化継承など、全国の先進事例を分析し、持続可能な地域創生のヒントを探る。
観光客数の回復が鮮明になる一方、オーバーツーリズムの再燃や地域文化への影響が新たな課題として浮上している。このような状況下で、日本の観光が目指すべきは、単なる訪問者数の回復、すなわち「量」の追求ではない。地域と旅行者の双方にとって価値の高い体験を創造する「質」への転換である。
この重要な転換を導く羅針盤として、観光庁が推進するのが「JSTS-D(Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations/日本版持続可能な観光ガイドライン)」である。JSTS-Dは、自治体や観光地域づくり法人(DMO)が、持続可能な観光地マネジメントを行うための指標を示すものだ。本稿では、JSTS-Dの理念を体現し、独自の挑戦を続ける全国の先進事例を分析し、「住んでよし、訪れてよし」の観光地づくりに向けた実践的な道筋を探る。
【視点1】オーバーツーリズムを乗り越え、住民との共生を図る

持続可能な観光の根幹をなすのは、地域住民の生活と観光との調和である。JSTS-Dは、この共生を実現するための具体的なアプローチを示している。その好例が、歴史的に観光客と向き合ってきた地域での取り組みだ。
- 京都市では、事業者や旅行者が守るべき理念として「京都観光モラル」を策定した。これは単なるマナー啓発にとどまらず、市民生活と観光の調和という明確な目標を掲げ、あらゆるステークホルダーに行動変容を促す枠組みである。観光客が集中する時間や場所を分散させる情報発信なども含め、地域全体のマネジメントに繋げている。
- 北海道美瑛町も、農業という基幹産業と観光の両立に長年取り組んできた。農地への無断立ち入りという深刻な問題に対し、「美瑛観光ルールマナー110番」の設置や粘り強い啓発活動を展開。観光客に美しい丘の景観が農家の営みによって維持されていることを伝え、敬意ある行動を促している。
- また、豊かな自然を抱える北海道知床では、ヒグマの活動期に一部エリアでのガイドツアー利用を義務化するなど、科学的根拠に基づいた季節ごとの入域制限を導入した。これにより、旅行者の安全確保と希少な生態系の保全、そして混雑緩和を同時に実現している。
【視点2】地域資源を再発見し、高付加価値な体験を創出する

JSTS-Dが重視するのは、地域の文化や自然という「本物」の価値を保護し、それを高付加価値な観光体験として磨き上げることである。これは、安易な消費型の観光から脱却し、地域経済の好循環を生み出すための重要な戦略となる。
- 熊本県阿蘇市は、「千年の草原」と称される広大な景観を保全するため、観光を積極的に活用する。草原でのサイクリングやトレッキングといったアクティビティを開発し、その参加費の一部を草原の維持管理費用に充当する仕組みを構築した。旅行者は雄大な自然を満喫しながら、その保全に直接貢献できるのである。
- 世界遺産を有する岐阜県白川村の取り組みは、文化継承と観光を結びつけた独創的な事例だ。合掌造り集落の茅葺き屋根の葺き替え作業を、旅行者が参加できる「体験ツアー」として商品化した。これは、旅行者にとっては唯一無二の文化体験となり、地域にとっては伝統技術の維持・継承と関係人口の創出に繋がる、まさにWin-Winのモデルといえる。
- 沖縄県久高島は、「神の島」としての神聖な文化を何よりも優先する。島独自のルールを策定して来訪者に周知徹底する一方、住民と旅行者の双方にアンケート調査を実施。地域の許容量(キャパシティ)を見極めながら、文化継承を核とした持続可能な観光のあり方を模索し続けている。
【視点3】旅行者が主役に。「貢献」を促す新しい観光の形

近年の旅行者は、単なる消費者であることに留まらない。「旅行を通じて地域に貢献したい」という意識を持つ層が確実に増加している。JSTS-Dの理念は、こうした新しいニーズに応える観光商品を開発する上でのヒントも与えてくれる。
- 高知県土佐清水市では、美しいサンゴ礁の生態系を脅かすオニヒトデを、ダイバーである旅行者が駆除するツアーを実施している。環境保全活動にエンターテインメント性を加えることで、旅行者は楽しみながら海の生態系を守る活動の当事者となることができる。
- 京都市を拠点とする(一社)ツーリストシップは、地域と旅行者の良好な関係性を「ツーリストシップ」という言葉で定義し、その概念を広めている。収益の一部が地域に還元される商品を企画・販売し、旅行者が意識的に地域貢献を選択できる仕組みを提供しているのだ。
これらの事例は、観光が地域の課題解決に直接貢献できる可能性を示している。「旅行者にゴミ拾いを義務付ける」という阿蘇の草原アクティビティの試みに、参加者から反発どころか賛同の声が多く寄せられたという事実は、旅行者の意識が大きく変化していることを象徴しているだろう。
「住んでよし、訪れてよし」の未来へ
今回紹介した事例は、全国で始まっている挑戦のほんの一部に過ぎない。しかし、いずれの事例にも共通しているのは、JSTS-Dが示す「環境」「文化」「社会・経済」の3つの側面を統合的に捉え、自らの地域の価値を再定義しようとする強い意志である。
JSTS-Dは、画一的な正解を示すマニュアルではない。それぞれの地域が自らの課題と向き合い、その土地ならではの魅力を未来にわたって守り、育んでいくための思考のフレームワークであり、実践のための羅針盤である。
「量から質へ」というスローガンがリアリティを帯び始めた今、このガイドラインをいかに活用し、地域と旅行者の双方に豊かさをもたらす観光を創造できるか。日本の観光地域づくりの真価が問われている。
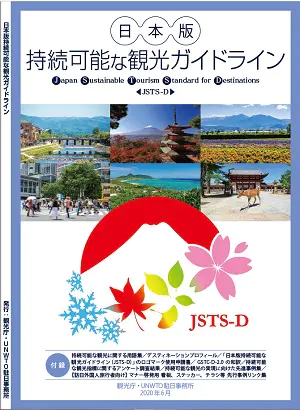
日本版 持続可能な観光ガイドライン( JSTS-D) は下記のリンクよりご覧いただけます。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810000951.pdf
寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しました-3-1024x576.png)



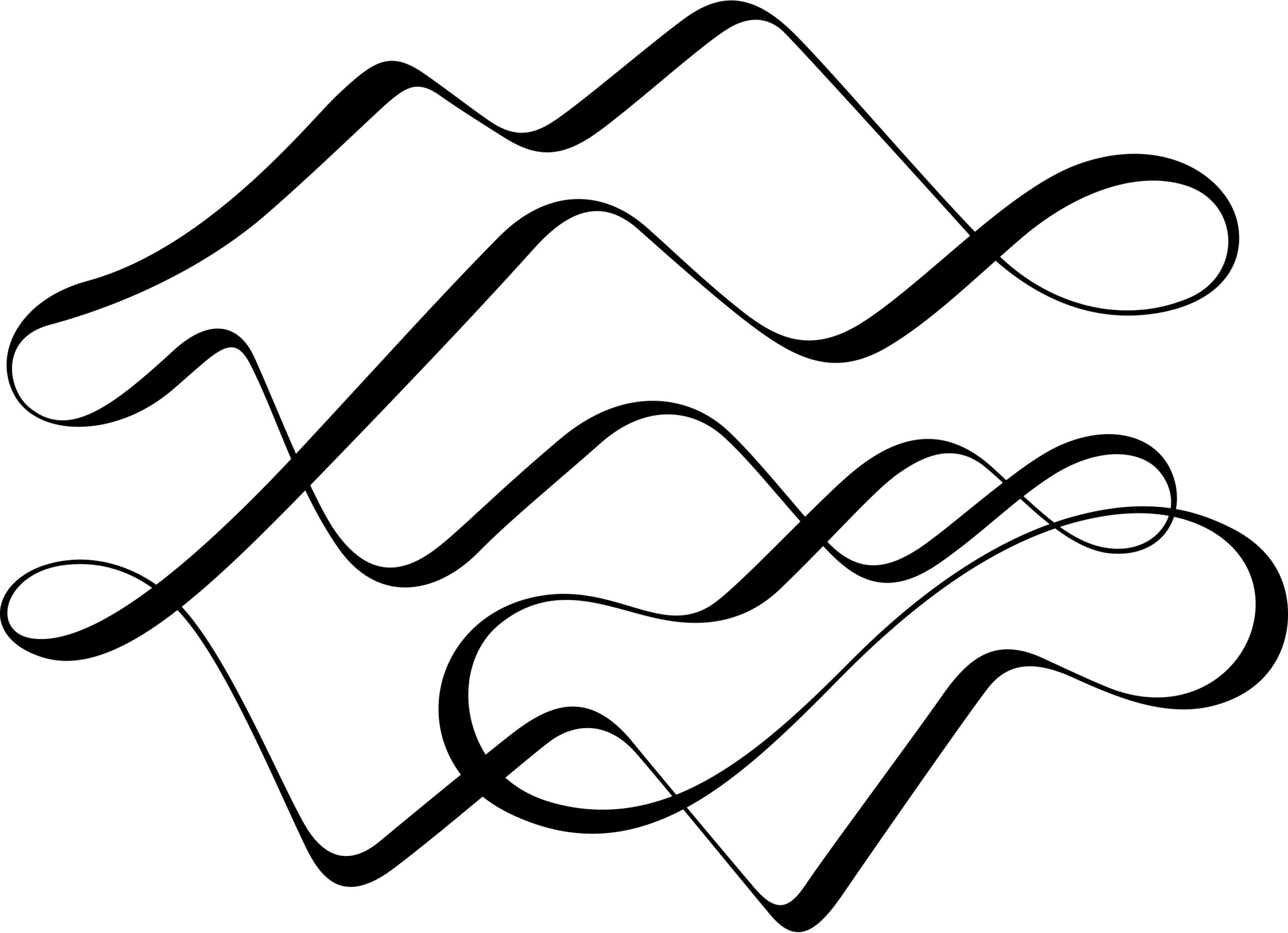



コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)


