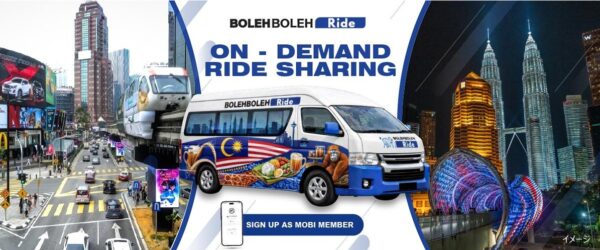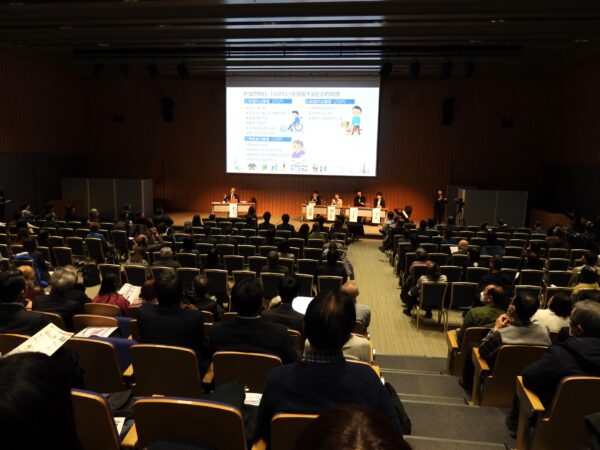先ごろ開催された旅行テクノロジー業界の国際会議「WiT Japan & North Asia 2025」では、旅行・航空関連のデータサービスを提供するOAGからアジア太平洋地域統括のマユール・パテル氏が登壇。アジア太平洋地域における航空市場の現状と今後の見通しについて解説した。
パテル氏によれば、2024年のアジアにおける航空座席供給量は、2019年比でわずか0.5%増の約21億席にとどまった。北東アジアも1.3%増で「コロナ前に予想されていた10%超の成長には遠く及ばない」状況だ。このうち韓国と日本は成熟市場であり、中国は座席こそ増加しているものの、ビザの発給や路線開設の一部制限などの課題があるという。
一方で、インドは急成長を遂げており、中央アジアも市場規模こそ小さいながら19年比40%以上の伸びを記録。中央アジアの伸びの背景にはロシアからの渡航需要の増加があるとした。
航空機の発注数は世界トップ、新たに年間5.7万席を供給へ
パテル氏は北東アジアは座席供給量の伸びこそ鈍いとしながらも、航空機の発注数ベースでは世界のトップにあることを強調した。2030年までに約2100機の新機材が導入される見込みで、1機あたり200席、1日6便、年間330日の稼働を仮定した場合、2030年までに年間8億2100万席の追加が見込まれるという。
パテル氏は「このうち35%は機材の更新」としながらも、「実質的に年間約5万7500万席が新たに増加する」と語り、北東アジアの航空市場におけるさらなる供給量の拡大に期待を示した。
北東アジアの1/3はLCC、韓国で「革命」 旅行ニーズの細分化も
LCCの急成長も供給増加の大きな要因だ。パテル氏は「北東アジアにおける航空座席のおよそ3席に1席はLCCが運航している」と延べ、LCCの存在感が急速に高まっていることを指摘。なかでも韓国では「LCC革命」が起きており、LCCの座席が全体の44%を占めるという。ただし、韓国ではLCCとFSCの競合が激しく、同じ時間帯に過剰供給されているケースもあるとした。
一方、LCCの比率が低いのが中国で約11%。日本でも既存のFSCの影響力が強く約20%にとどまっているという。パテル氏は「北東アジアは最も保守的で慎重な市場」としつつ、「新機材の7割がLCC向けであり、今後LCCが勢いづいていく」との見方を示した。
さらにパテル氏は旅行者のニーズの細分化についても言及した。親子旅行や女子旅、ひとり旅、親の資産を使った旅行など、目的や形態でさまざまなスタイルが登場しているという。
同氏によれば、現在旅行市場の中心となっているのはミレニアル世代(1981年〜1996年生まれ)だが、ベビーブーマー世代(1946年〜1964年生まれ)も同じ水準で旅行しているところ。また、Z世代(1997〜2012年生まれ)は収入や退職を待たず「今ある予算」の中で旅行を楽しむ傾向が強い。
パテル氏は今後はα世代(2013年以降生まれ)の動向も注目されるのではとし、「こうした細分化された市場において、いかにトラベルテックを導入しているか」が鍵になるとした。
情報提供:トラベルビジョン