「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」は、単なる認証取得のための基準ではない。それは、地域が自らの足で未来へと歩むための「羅針盤」であり、50年、100年先を見据えた持続可能な地域経営を実現するための実践的なツールである。
観光庁が示すように、JSTS-Dの導入は地域に「自己分析」「合意形成」「プロモーション」という3つの大きな効果をもたらす。本記事では、この3つの効果が、いかにして地域の課題解決と価値創造に繋がるのかを具体的に解説する。
① 自己分析ツール:地域の「今」を客観的に把握し、未来を描く

多くの自治体やDMOが直面する「何から手をつけるべきか分からない」という課題。JSTS-Dは、その第一歩として、地域の現状を客観的かつ網羅的に把握するための強力な「自己分析ツール」として機能する。
JSTS-Dは、観光計画から環境負荷、文化遺産の保護、地域住民の福利まで、47の指標で構成される包括的なフレームワークである。これは、いわば地域の「健康診断書」だ。この基準に沿って自己評価を行うことで、これまで感覚的に捉えていた混雑や騒音といった課題から、見過ごされがちだった強みや潜在的なリスクまで、あらゆる側面が可視化される。
このプロセスを通じて、地域は世界基準と自らの現在地とのギャップを明確に認識できる。それは、将来目指すべき観光地の姿を具体的に描き、実効性のある戦略を立てるための揺るぎない土台となる。さらに、問題を早期に発見し、深刻化する前に対処する「アーリーウォーニングシステム」としての役割も期待できるだろう。
② コミュニケーションツール:多様な主体を繋ぎ、地域一体の体制を築く

持続可能な観光は、行政だけで成し遂げられるものではない。地域住民、観光事業者、各種団体など、多様なステークホルダー(利害関係者)の協力が不可欠である。JSTS-Dは、これらの主体が同じ目標に向かうための「共通言語」として機能し、地域全体の合意形成を促進する。
JSTS-Dが示す客観的なデータや分析結果は、感情論や個々の利害を超えた建設的な対話の土壌を作る。例えば、観光課の職員が環境課や建設課、さらには地域の宿泊施設や交通事業者と連携する際、JSTS-Dの指標は具体的な協力点を明確にし、セクターを横断した取り組みを円滑にする。
これは、地域全体で持続可能な観光を推進する体制を構築し、その担い手となる人材を育成する絶好の機会でもある。また、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」の全17目標に対応しているため、JSTS-Dへの取り組みは、SDGs達成に向けた自治体の具体的な行動計画そのものとなり得るのだ。
③ プロモーションツール:「選ばれる観光地」としての国際的なブランド力を高める

JSTS-Dは、世界基準であるグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会(GSTC)の基準に準拠している。そのため、JSTS-Dに沿った取り組みを進めること自体が、その地域が国際的に認められたサステナビリティ基準を満たしているという「お墨付き」となる。
ブッキング・ドットコムの調査で世界の旅行者の86%がサステナブルな旅行を望むと回答したように、持続可能性はもはや観光地の選択における重要な判断基準である。特に、消費額の大きい欧米豪の富裕層においてその傾向は顕著だ。「サステナビリティに取り組まない観光地は淘汰される」という厳しい現実が、すぐそこまで迫っている。
この状況下で、JSTS-Dに基づいた取り組みを積極的に発信することは、他地域との明確な差別化要因となり、国際競争力を飛躍的に高める。実際に、観光庁のモデル事業に参加したニセコ町や白川村、京都市などが国際認証機関から表彰された事実は、日本の地域が持つ潜在能力をJSTS-Dが引き出し、世界的な評価に結びつけられることを証明している。
まとめ:未来への投資としてのJSTS-D
JSTS-Dは、短期的な観光客数の増加のみを追う旧来の観光振興策とは一線を画す。それは、地域の文化や自然環境を守り、住民の暮らしを豊かにしながら、訪問者にも質の高い体験を提供するという、長期的視点に立った地域経営の哲学そのものである。
自己分析を通じて足元を見つめ直し、対話を通じて地域全体の結束を固め、そして国際社会に向けてその価値を堂々と発信する。この一連のプロセスこそが、地域が変化の激しい時代を乗り越え、将来にわたって「選ばれ続ける場所」であるための最も確実な投資といえるだろう。まずは自地域の現状把握から、その第一歩を踏み出してはどうだろうか。
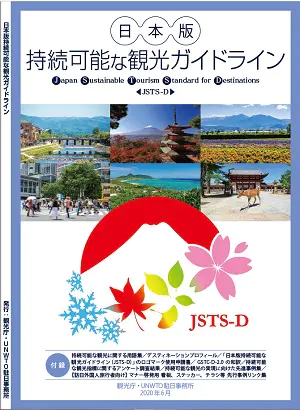
日本版 持続可能な観光ガイドライン( JSTS-D) は下記のリンクよりご覧いただけます。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810000951.pdf
寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-1024x576.png)



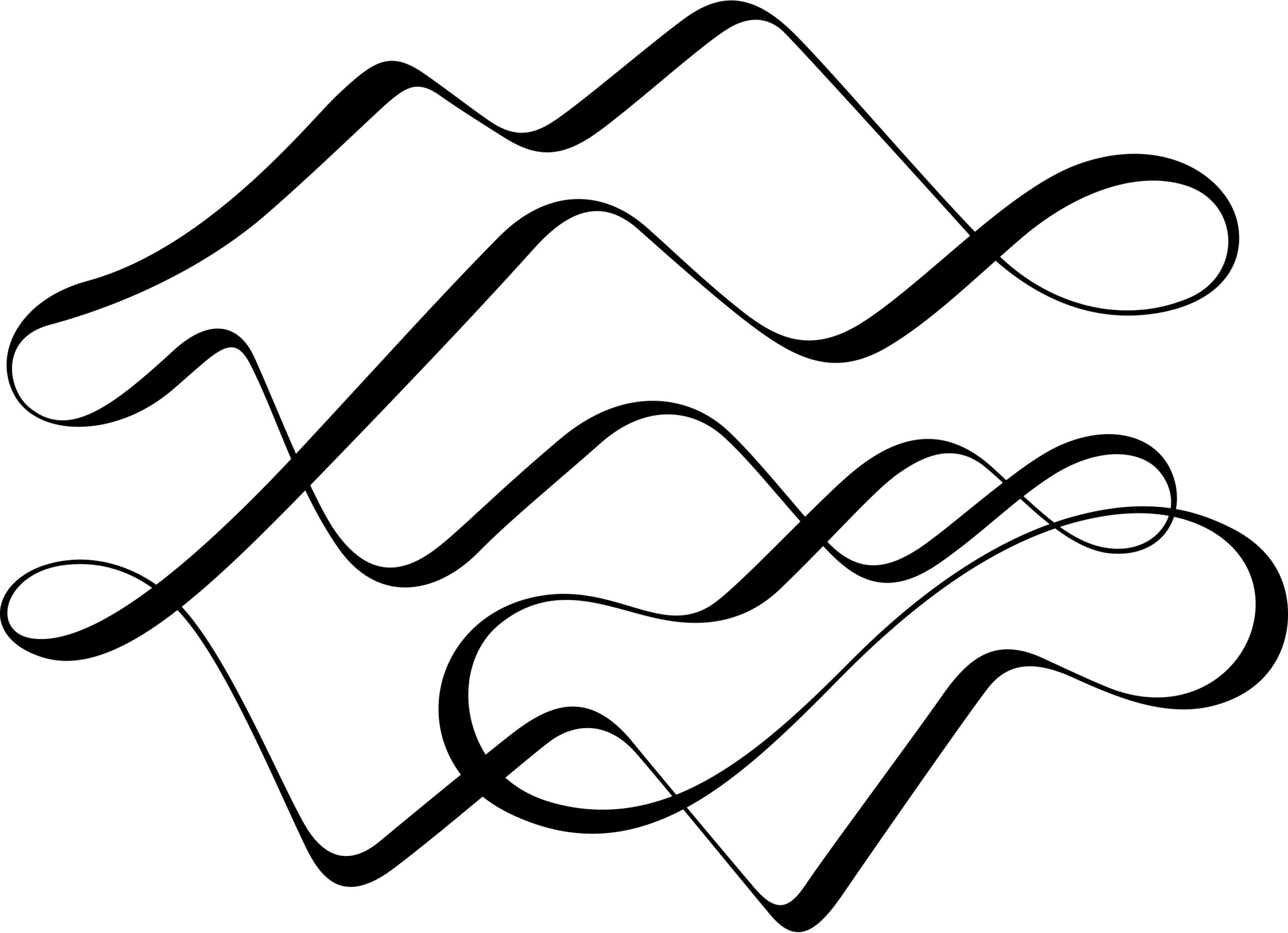



コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)


