【桑都・八王子市、浅川にて】 ただのゴミ拾いに終わらない。東京の自然と歴史を五感で感じ、地域への愛着を育む体験型イベント「桑都リバークリーンナップ」が、八王子市の浅川を舞台に開催された。観光・地方創生に携わるプロフェッショナルたちが、この活動から得た学びと示唆をレポートする。
イベントの幕開け:当日の空気感と期待

夏の強い日差しが照りつける早朝7時、JR八王子駅からほど近い浅川の河川敷に、イベントの参加者が集まり始めた。主催者に加え、地元の学生たちも参加し、会場は和やかながらも清々しい熱気に包まれていた。
「おはようございます!」、参加者同士が笑顔で挨拶を交わす。ゴミ袋が配られ、誰もが「ただのゴミ拾いではない、何か特別な体験が始まる」という期待に胸を膨らませている様子だった。義務やノルマは一切なく、誰もが自らのペースで活動に参加できる。この心地よい自由さが、参加者間のコミュニケーションを自然に促していく。
白熱のプログラム:具体的な内容とハイライト

桑都リバークリーンナップは、参加者が思い思いに川沿いを歩きながらゴミを拾うスタイルで進められた。しかし、この活動が一般的な清掃活動と一線を画すのは、「探究」という視点が深く組み込まれている点だ。
筆者は、裸足で川に入り、上総層群の地層を歩くというユニークな体験をした。約200万年前の地層に眠るメタセコイアの化石林を間近に観察。足の裏で大地の歴史を感じるという、まさに五感に訴えかける瞬間だった。太古の時代から、この場所に川が流れ、森があったという事実に触れることで、単なる景観としての川ではなく、壮大な地球の物語の一部として川を捉えることができる。
参加者の一人は「宮入さんのお話は、まさに目から鱗でした!」と、ゴミ拾い中に見つけたゴミから話が広がり、新たな学びにつながったという。また別の参加者は、「他の参加者との交流で、新たなビジネスのヒントが見つかりました。」と、活動そのものがネットワーキングの場になっていることに触れた。
参加者の声と広がる交流

イベントが後半に差し掛かる頃、参加者の間には心地よい疲労感と達成感が漂っていた。回収されたゴミ袋の山は、今日の活動の成果を物語っている。
- 「ただゴミを拾うだけでなく、地層や化石に触れる体験が新鮮でした。地域資源の新たな可能性を感じました。」(地方自治体観光担当)
- 「海のゴミの8割は川からやってくる、という話が心に刺さりました。この活動が、持続可能な社会づくりに繋がっていることを実感できて嬉しいです。」(旅行会社社員)
- 「普段なかなか接点のない人たちと、共通の目的を持って活動できたのが楽しかったです。新しい繋がりができました。」(ITベンダー担当者)
活動後も、参加者たちは発見したゴミや感じたことを共有し、会話が弾んでいた。ゴミ拾いという共通の目的が、普段交わらない異業種の人々を結びつけ、新たなアイデアやビジネスの種を育むきっかけとなっていた。
イベントが示す未来:地域創生への貢献と今後の展望

この桑都リバークリーンナップは、単なる環境保全活動ではない。地域固有の自然や歴史、文化を「探究」することで、参加者一人ひとりがその地域の物語を体験し、記憶に刻む「探究型ツーリズム」そのものである。
参加者はこの体験を通じて、自らの仕事に活かせるヒントを掴んだ。例えば、自治体職員は、地域資源を再発見し、新たな観光コンテンツを企画するきっかけを得た。旅行会社社員は、アドベンチャーツーリズムやヘルスツーリズムといった文脈で、この活動を商品化する可能性を探った。
「海のゴミの8割は川からやってくる」という事実が示すように、この活動は八王子というローカルな場所での小さな一歩が、やがて東京湾、ひいては地球全体の環境問題解決に繋がることを実感させる。この一連の体験は、参加者の地域への愛着を育み、観光やイベントがその地域の持続可能な将来のためのものであるという認識を深める。
このイベントは、観光と地域創生が不可分であることを証明している。当日の体験は、地方創生・観光産業に携わるプロフェッショナルたちに、地域の「過去、現在、未来」を探究することの重要性を改めて示唆した。
次回の開催情報
次回の「桑都リバークリーンナップ」は、2025年9月下旬の開催を予定している。詳細な日程や集合場所、申込方法については、SNSで告知される。観光・地方創生関係者だけでなく、地域を愛し、未来の景色を守りたいと願うすべての人が参加できる。
寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部





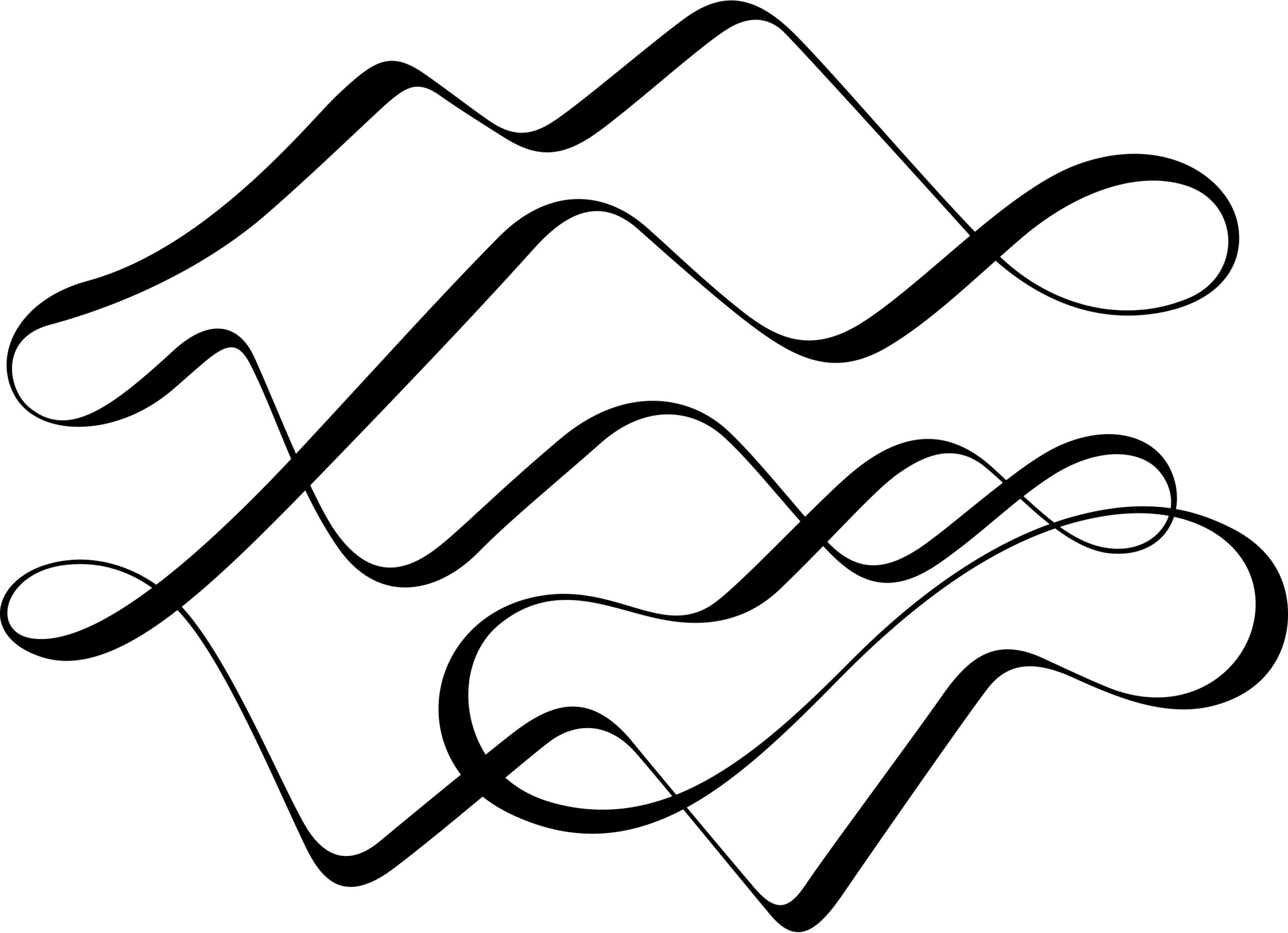



コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)


