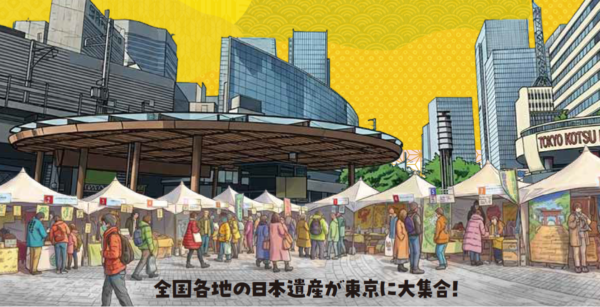京都中心街の南・伏見宿は、京都と大坂を結ぶ経済拠点、江戸時代に舟運によって発展した。
月桂冠をはじめとする酒や米を、ここ濠川から宇治川・淀川を経て、大坂に航行する輸送船が発着する。十石舟、三十石船と呼ばれ、明治時代末期まで存続していた。
その後、輸送手段は鉄道からトラックなどに変化する。また、淀川に大きな堰が造られたために、舟運は減退する。しかし、高度成長期の自動車による排気ガスや渋滞によって、舟運は再び見直される。観光用屋形船ではあるが、1998年に地元の自治体や企業など55法人によって運航を始める。現在では、伏見観光協会が運営している。
京都の町は、南北に長く高低差が激しい。そのため、人々は、長い間、桜の花々に触れる。昨今、桜の季節にSNSを開くと、京都市内の満開情報が目に入ってくる。この日は、2時間ほど予定の時刻より時間が空いた。どこかで桜をと、新幹線内で探していると、仕舞桜の花筏の写真が映し出される。
この橋の上からは、川沿いの土手に数多くのカメラマンが、各々のスタイルで撮影する姿を見る。特に、着物をレンタルしたコスプレ姿や「映え」写真を撮っている人々が少なくない。
一面に広がる桜花は、しばらくすると十石舟が桟橋に戻り、四方に散っていく。それも一興と、シャッター音が響く。散り際も見事だ。桜は日本を代表する季節限定の観光コンテンツ、なかなか時期の平準化の取り組みは難しい。
(2022.04.08.撮影)
(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8
取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長





.jpg)

1-600x400.jpeg)