地域創生と風土再生をテーマにした研修ツアー、2日目の朝。私たちは、穏やかな湾を望む「長洞(ながほら)元気村」の門をくぐりました。ここで待っていたのは、陸前高田の豊かな海の恵みを自らの手で触れ、学び、味わい尽くす特別な時間。漁師さんや地元のお母さんたちの温かい笑顔に迎えられ、私たちの五感を揺さぶる体験が始まります。

◼️漁師直伝!カサゴとメバルに挑む、ドキドキの魚さばき体験
「スーパーの切り身しか見たことないから、できるかな…」
そんな不安と期待が入り混じる中、始まったのは漁師さん直伝の魚さばき体験です。目の前に用意されたのは、カサゴやメバルといった、今朝獲れたばかりの新鮮な魚たち。命の力強さを感じるその姿に、参加者からはゴクリと息をのむ音が聞こえます。

まずは滑り止めの軍手を左手にはめ、いざ、鱗取りから。
「優しくやらなくていいよ、ガリガリッと思いっきりやっちゃって!」
お母さんの威勢のいい声に背中を押され、専用の道具を魚の尾から頭に向かって滑らせると、面白いように鱗が飛び散ります。この「ガリガリ」という感触と音こそ、命をいただく第一歩。
次はいよいよ、三枚おろしへの挑戦です。お腹を割いて内臓を丁寧に取り出し、きれいに洗う。そして、背骨に沿って慎重に包丁を入れていきます。骨に当たる「コツコツ」という感触に、魚の体の構造を実感。思うように進まないもどかしさと、地元の方々の無駄のない手際の良さとの対比に、日々の暮らしに根付いた知恵の深さを感じずにはいられません。時には珍しいカワハギが登場し、そのざらざらの皮を手で剥ぐという貴重な体験も。

慣れない手つきで格闘しながらも、ようやく自分の手で魚をさばききった時の達成感は格別です。「食べる」という行為の裏側にあるストーリーを知ることで、一切れの魚がこれまでとは全く違って見えてきました。これは単なる料理教室ではない、食と命の繋がりを再発見する、尊い学びの場でした。
◼️ぷりぷりの宝物!三陸わかめの甘さに驚く「芯抜き」体験

魚との格闘で高まった興奮も冷めやらぬまま、次は「三陸の宝」と称されるわかめと向き合います。津波の被害からいち早く養殖を再開したわかめは、陸前高田の復興を力強く牽引してきた大切な海の幸です。
体験するのは、塩蔵されたわかめの葉と茎を分ける「芯抜き」という作業。一見地味に見えますが、これが驚くほど奥深く、夢中になる楽しさがありました。
「太い方を持って、爪をうまく使って、両側にそーっと引っ張るんだよ」

教わった通りにやってみると、ぷりぷりとした弾力のあるわかめが、気持ちよく二つに分かれていきます。途中で切れてしまってもご愛嬌。地元の子供たちも大好きだというこの手作業は、不思議な集中力と癒やしをもたらしてくれます。
そして、この体験のハイライトは「味見」の時間。
芯抜きしたばかりのわかめの葉をひとかけら口に含むと、まず海の塩気がガツンと広がります。しかし、噛みしめるうちに、そのしょっぱさがすっと引き、わかめ本来の驚くほど豊かな甘みが口いっぱいに広がりました。
「美味しい!」「甘い!」
参加者のあちこちから、思わず感動の声が上がります。普段私たちが食べているわかめは、この甘みを味わうために塩抜きされているのだと、舌で理解した瞬間でした。
茎の部分も、漬物やスープにすれば絶品だと聞き、海の恵みを余すことなくいただく文化に触れました。持ち帰るお土産のわかめが、ずっしりと重く、そして愛おしく感じられます。
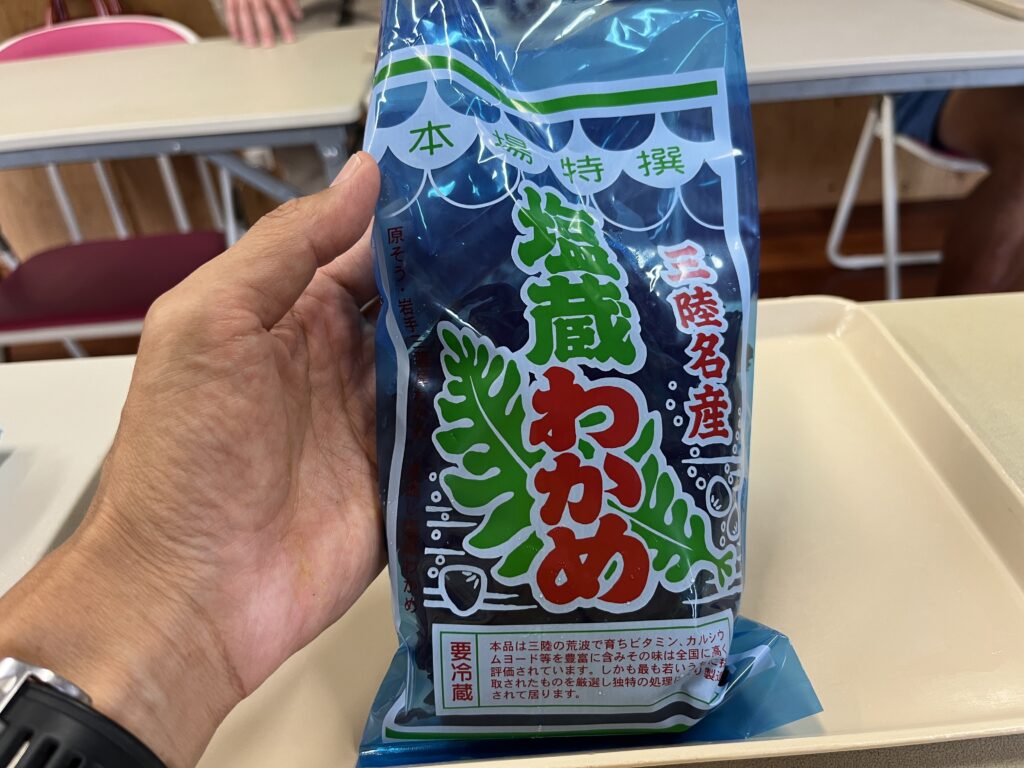
長洞元気村での体験は、結果だけでなく「過程」そのものを楽しむ豊かさを教えてくれました。地元の方々との何気ない会話、仲間との共同作業、そして自らの手で触れた命の温もり。すべてが忘れられない思い出となり、陸前高田の海と、そこで暮らす人々のことが、もっと好きになる。そんな心温まる体験となりました。
寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-3-2-1024x576.png)



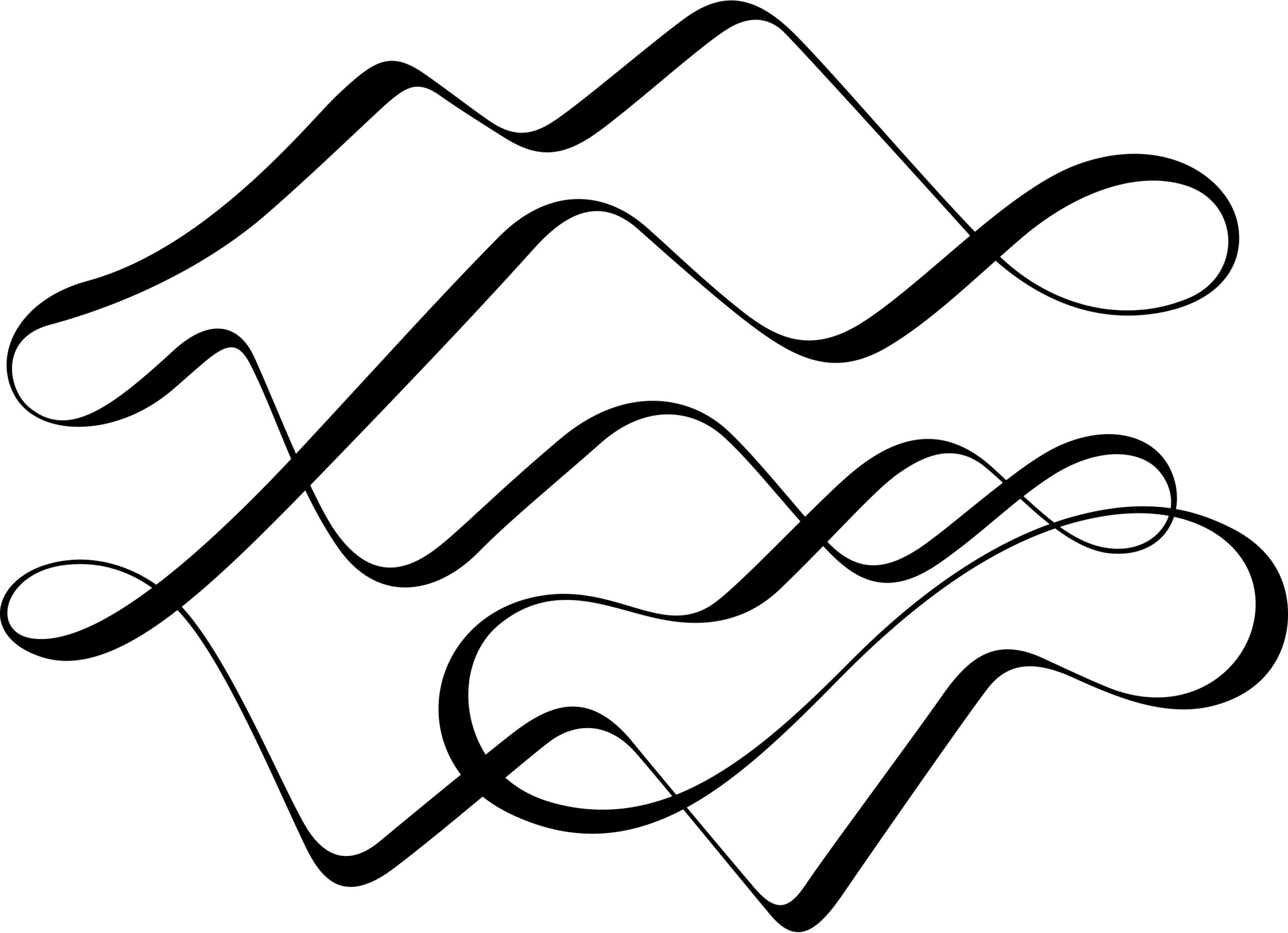



コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)


