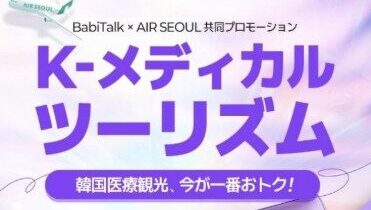浜名湖は、古く遠津淡海(とおつあわうみ、遠淡海)と呼ばれ、遠江の語源となったと言われる。かつては淡水湖だった。しかし、明応地震(1498年)に伴う津波によって、現在は遠州灘につながる汽水湖となっている。また、日本の湖の中でも複雑な形状であり、地上からもその姿は風光明媚な場所であり、浜松周辺の代表的な観光地である。
東海道新幹線に乗車すると、昨今はやりの「インフィニティ」という言葉がピッタリな場所を通過する。ここは、海と湖が一体化して、列車は水上を滑っているようだ。また、晴れた冬場には、地上から富士山が見える最西端とも言われている。
さて、航空機は西に向かう際、浜名湖の北側を通過する。一方、東に向かう時は、南側の太平洋上を航行する。しかし、時折、三河湾上空を抜け、浜名湖を眼下に見渡す時もある。その際、前方には、富士山の雄姿を俯瞰できる。

温暖・肥沃な土地を駆け抜けた人々
浜名湖周辺は、温暖かつ肥沃な土地である。それ故、戦国時代の三傑は、この場所を自らの領土として切り取ることに奔走し、天下統一を目指した。上空から見る直線状の遠州灘が、日本刀の反りのように見えることも、そう思わせる由縁である。
そして、遠州灘と浜名湖をつなぐ場所を「今切(いまきれ)」という。明応地震により出来上がった場所は、渡船によって行き来をしていた。そのため、徳川家康も三方ヶ原の戦いで撤退を余儀なくされた。また、今でも鉄道も道路も、この交通の難所を橋梁を掛けて通過している。
江戸時代には、「入鉄砲に出女」と言われ、関所が設置された。東海道の要衝である「今切」には新居関所。一方、「姫街道」と呼ばれた浜名湖の奥には気賀関所である。当時、全国には53箇所の関所が置かれていたという。中でも、浜名湖周辺は、徳川幕府にとっても監視の目を強化すべき場所であった。特に奥浜名湖は、大名の江戸詰めの女人たちが通り抜ける可能性があり、姫街道と呼ばれ、主要街道と同様の厳格さが敷かれていた。
江戸時代は、戦争のない平和の時代になったと言われる。しかし、幕府は、用心に用心を重ね、鉄砲による反乱や人質とされた女人たちが抜け出ることを、固く拒み続けた。簡単に行き来できないようにすることが、300年に渡る太平の世を作り上げたのであろう。
そう思うと、現在の浜名湖の景観は、平和の象徴なのかもしれない。

寄稿者 観光情報総合研究所 夢雨/代表
(これまでの寄稿は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=181





円形.jpg)

.png)