地域創生に取り組む東京山側DMCは、里山再生をテーマとした長岡フィールドワーク(風土再生の旅)を10月7日〜9日に実施した。この視察では、未来里山技術機構(NEST)の山本麻希(長岡技術科学大学 准教授)が提唱する、科学的エビデンスに基づく野生動物との「共存哲学」に最も注目が集まった。感情論を排し、野生動物の行動様式と生態系を深く理解した上で、人間と野生動物の生息域を明確に「切り分ける」というNESTの哲学は、地方創生における獣害問題を持続可能なビジネスへと転換させる可能性を示唆している。

「異分な根」による共存哲学:里山再生の重要性
NESTが提唱する人間と野生動物の「共存」は、動物を愛玩することとは一線を画す。それは、「山にクマは住む。人間は里外に住む。その間をしっかり切り分ける」という「異分な根を持って、お互いを見分ける」哲学に基づいている。
近年のクマの出没増加の背景には、カシノナガキクイムシによるナラ枯れとブナの凶作が重なったことが挙げられる。さらに、人間が里山の手入れを怠った結果、人里にいるのが当たり前の「新世代」のクマが生まれてしまったという事実も指摘されている。
クマの出没を止めるためには、里山に手を入れ、持続可能な森林経営(近自然林)を進める必要がある。これが、野生動物の生息環境を再構築し、人里との適切な距離を保つための本質的な対策とされる。
捕獲効率と倫理を両立させる専門技術(How)
山本氏の指導では、専門性の高さが随所に示された。野生動物対策を持続可能にするためには、捕獲技術の効率と倫理観の両立が不可欠である。
1. 電気柵の原則と運用:

電気柵は、濡れた動物の鼻がプラス線に触れ、マイナスの地面(アース)を踏むことでショックを与える仕組みで稼働する。人間はゴム靴を履いているため感電しないことが原理である。
しかし、柵がアスファルトやゴム製のシートに触れると効果を失ってしまう。また、イノシシの硬い皮膚ではなく、敏感な鼻に電気を流す高さの調整が重要である。
2. 高性能な罠の活用とプロのソフト:
NESTが推奨するくくり罠(三生社製)は、非常にすれたイノシシの捕獲に特化している。この罠は、罠の匂いをバクテリアが分解するまで1週間待ってから稼働させるという、プロの技術(ソフト)を要する。
のFAQを公開しましたのコピー-4-1024x576.png)
さらに、罠にかかった際にバネが分離し、動物に痛みを与え続けない設計になっている。これにより、足が痛まないため、食肉化できる部分(利用率)が高まるという倫理的・実利的な利点がある。
高利用率を実現する解体処理技術
捕獲された獣肉の品質維持には、解体後の処理が極めて重要である。師匠の技術では、内臓摘出後、肉の臭みの原因となる「肉を濡らすこと」を避ける。その上で、氷水(水冷)で一晩かけて深部体温を4℃まで下げる手法が採られている。
これは、従来の空冷よりも効率的で、獣肉の高い利用率(90%以上)を実現する。この解体処理技術は、捕獲した資源を無駄にしない持続可能なジビエ利用の基盤となる。
獣害対策は、単なる駆除問題ではなく、地域経済に貢献する資源循環のチャンスである。行政、学者、事業者が協力し、科学的知見を現場に落とし込んでいく取り組みこそが、真の「鳥獣共存」の里山再生をできることとなるだろう。
寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-3-1024x576.png)



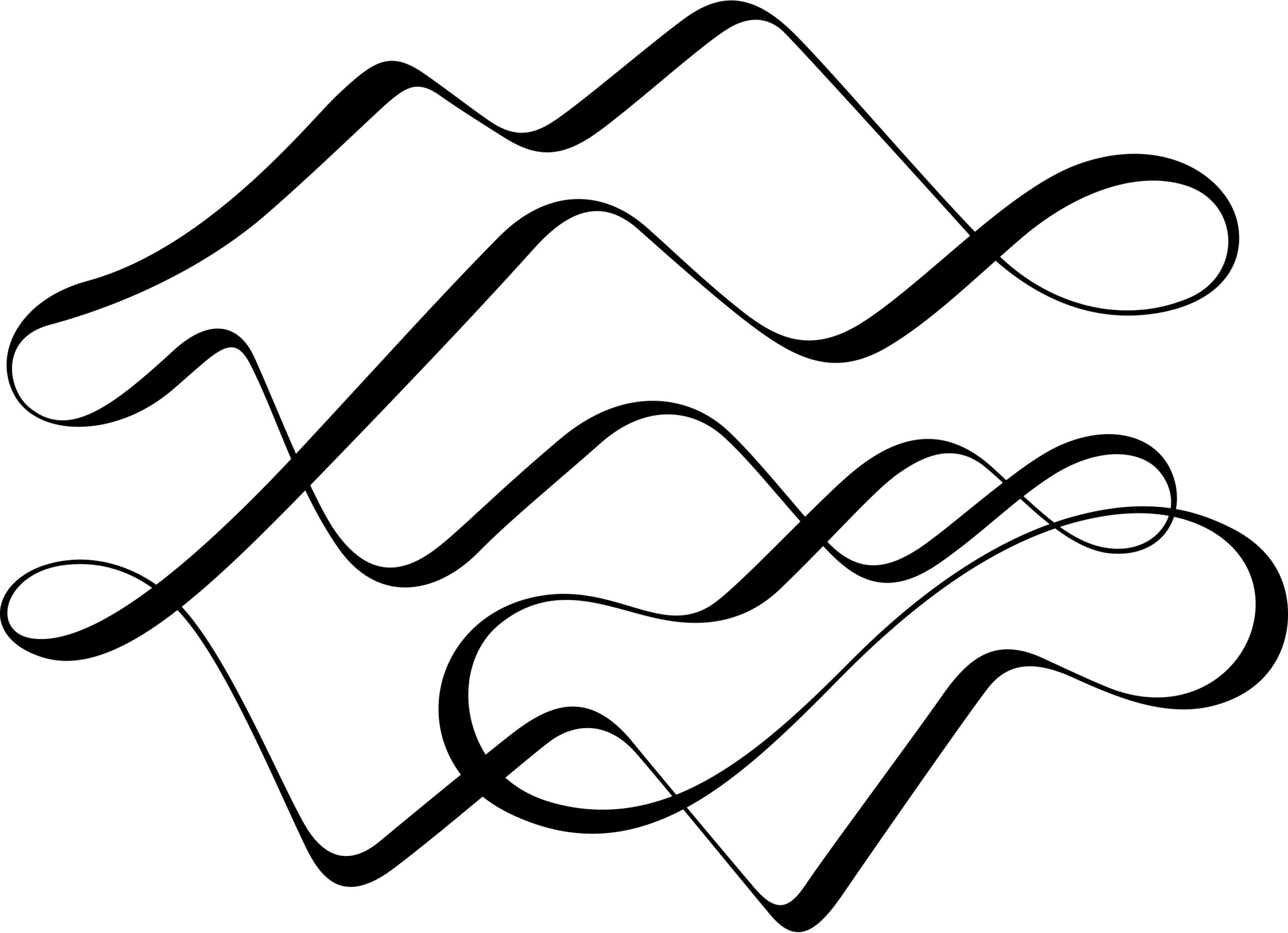



コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)


