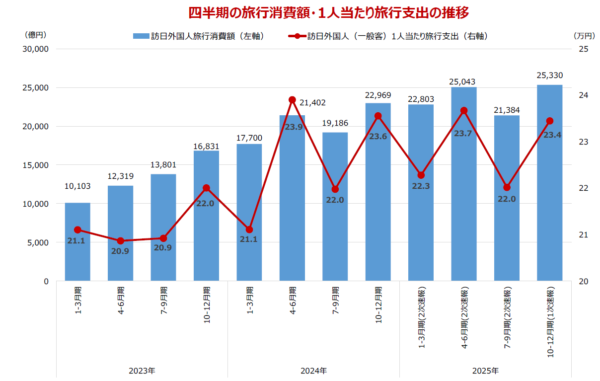北山駅から京都駅へ地下鉄に乗車する。逆方向は国際会議場だ。一駅乗車すると、次は北大路駅である。ここから数多くの人々が乗車してくる。買い物に出向く家族連れやバスから地下鉄に乗り換えた観光客など、ほぼ座席は埋まった。北大路駅は、京都市が推進する地下鉄と路線バスを活用するキーポイント、ターミナル機能を有している。また、ここは、前述の鉄道空白地域を補完するターミナルである。ここから金閣寺方面や洛北へのバスが出発する。
これまで、京都市は、市バス一日乗車券を販売していた。しかし、地下鉄とバスの乗り継ぎという方法を活用し、路線バスのマイナス面を払拭するように方向転換を行った。その代表的な施策が、バス一日乗車券を廃止し、地下鉄とバス双方に乗車できる一日乗車券に一本化したことである。
訪日外国人が好む観光先は

さて、日本を訪れる外国人は、「文化体験」「歴史的建造物」「伝統工芸」「食文化」に触れることを望む。なおかつ、「自らの手で体感」することが、彼らの行動様式である。そのために、貸切バスやタクシーなどの移動は好まれず、公共交通機関や徒歩移動が主流となる。
しかし、大きなスーツケースを持って移動するために、路線バスの混雑は解消されない。それ以上に遅延を生じさせている。また、京都に多い「路地」「辻子」にも徒歩移動の外国人が増えている。舞妓や芸妓を祇園界隈では追いかけ、迷惑行為も横行するようになっている。
公共交通機関を利用できる場所
このように、訪日外国人の目的地は限定され、交通至便な場所が好まれる傾向にある。
前回、京都市内は「鉄道空白地域」があり、それがデメリットであると述べた。しかし、偏りがあると言っても、京都市内には、大阪との結ぶJRや阪急、京阪という鉄道が走っている。また、奈良との間にJRや近鉄という鉄道も走る。そして、私鉄のターミナルのほとんどが、街の中心部に位置している。これは、京都に宿泊せずとも京都観光ができることにつながっている。
盆地の東と西に人気コンテンツが

彼らが好む観光地は、「東山界隈(清水寺や八坂神社、産寧坂など)」と「嵐山界隈(嵯峨野の竹林など)」が代表例となる。また、世界遺産である金閣寺や二条城も人気だ。そして、京都らしさを体感するために、錦市場や体験型観光施設(侍や忍者、清水焼や友禅体験など)も注目されている。
しかし、残念ながら錦市場は、人手の多さによって、市民の台所から観光客の食べ歩きテーマパークと化している。
この人気観光地である東山界隈と嵐山界隈は、ともに交通至便な場所である。そして、同時にさまざまな体験ができることも人気の的である。東山界隈は、特急バスが走り短時間で京都を堪能できる。清水寺や八坂神社、ねねの道と呼ばれる京都らしい町並みに触れ、二年坂から産寧坂にかけては、お土産の購入や日本食に触れることができる。
一方、嵐山界隈は、自然景観が今でも残り、大堰川にかかる渡月橋や嵯峨野の竹林が、SNS映えすることも人気である。京都駅からJR嵯峨野線に乗車すると、路線バスを利用せずとも短時間で嵐山に到着する。また、保津川沿いを走る嵯峨野観光鉄道に乗ることもできる。
SNSと現地体験

SNS映えという点から考えると祇園の舞妓や芸妓、伏見稲荷の千本鳥居なども外国に方々にとって、京都らしさに触れるものとなるのだろう。
また、欧米外国人を中心に神社仏閣に触れる旅は、全国各地で人気の的となっている。しかし、昨今は「見る旅」から「体験の旅」へと彼らの興味が、変化し深堀りさせている。
これまでも、東京赤坂に「忍者」の装束をつけたレストランが外国人だらけになったという。浅草には、瓦割り体験のコンテンツを売り物にしている施設もある。また、完成品が手元に残る体験も人気だ。その代表例が、自分だけの焼き物を作ることや西陣織のハンカチ絵付け、京扇子づくりなどである。これらは、かつて修学旅行の児童生徒が触れていた体験ものであり、京都市内には、数多くの体験施設が存在している。今では、外国人たちが好むモノ・コトとなっているのだ。
これまで、修学旅行を取り扱う旅行会社は、京都市内で、次の世代につなぐ体験学習を作り上げてきた。修学旅行生が減少傾向にある京都において、訪日外国人が、そのコンテンツに触れることは、今も昔も着地型観光が旅の原点だということを証明している。
第1回目の記事は、こちらから https://tms-media.jp/posts/70791/
(つづく)
(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8
取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長





.jpg)