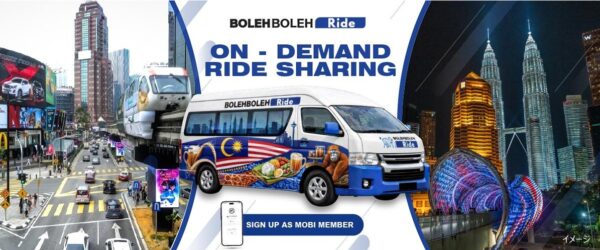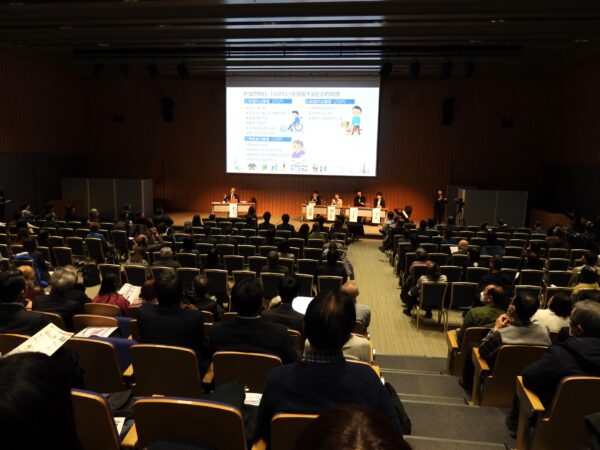日本旅行は、将来宇宙輸送システム(ISC)とともに、宇宙旅行サービスの商用化を見据えた新たな提携を発表した。2024年に両社が締結した「誰もが行ける宇宙旅行事業の実現を目指した業務提携」を発展させたもので、構想段階から実証・商用化段階へと移行する節目となる。
日本旅行は総代理店として顧客体験の設計、商品開発、販売を担い、ISCは宇宙輸送機の開発および安全監修を担当する。会見で日本旅行の吉田圭吾社長は「宇宙輸送を単なる技術ではなく、人の移動の新しい形として捉えている。宇宙への冒険を安全で安心のある旅へと変える」と語り、ツーリズムの視点から宇宙旅行を産業的な領域に拡張する意義を強調した。
両社が掲げる「SPACE Tour」構想は、宇宙旅行を段階的に発展させる3フェーズで構成されている。
「SPACE Tour 1.0」は2026年開始を予定し、宇宙を地上で体感するフェーズと位置づける。宇宙食や訓練体験、教育プログラム、宇宙関連施設見学などを通じ、誰もが参加できる地上型宇宙ツーリズムを展開する。
続く「2.0」では2030年代を目標に、再使用型ロケット「ASKA 2」により、例えば東京〜ロサンゼルスといった地上2地点間を約60分で結ぶ「宇宙経由の高速輸送」を実現する構想だ。価格は1億円程度を想定しているが、再使用回数の増加により将来的な低価格化を見込む。
最終段階の「3.0」は2040年代の実現を目指し、完全再使用型「ASKA 3」による軌道上滞在を想定。宇宙ホテルや研究、観光施設など、人々が暮らす宇宙空間の実現を目標に掲げる。

今回の提携により、構想段階から実証・商用化への移行体制が整い、2026年度中にはこれらのSPACE Tourの優先申込受付を開始する予定だ。
ISCの畑田康二郎社長は「日本の技術を結集すれば、人を安全に宇宙へ輸送することは必ず実現できる。宇宙旅行を一部の富裕層の体験から、誰もがアクセスできる旅へ変えていく」と述べ、再使用型ロケットの開発によるコスト削減と安全性向上の展望を示した。
日本旅行にとって宇宙との関わりは1992年、毛利衛氏の宇宙飛行を応援するツアー企画に始まる。以降、ロケット打上げ支援や宇宙教育事業など、宇宙関連の取り組みを着実に積み重ねてきた。今回の提携は、その延長線上にある「宇宙を旅の新領域とする」挑戦であり、ツーリズムが宇宙産業に接続する本格事例となる。
※メインビジュアルは、(左から)日本旅行の吉田圭吾社長、将来宇宙輸送システムの畑田康二郎社長。
情報提供 トラベルビジョン(https://www.travelvision.jp/news/detail/news-119354)