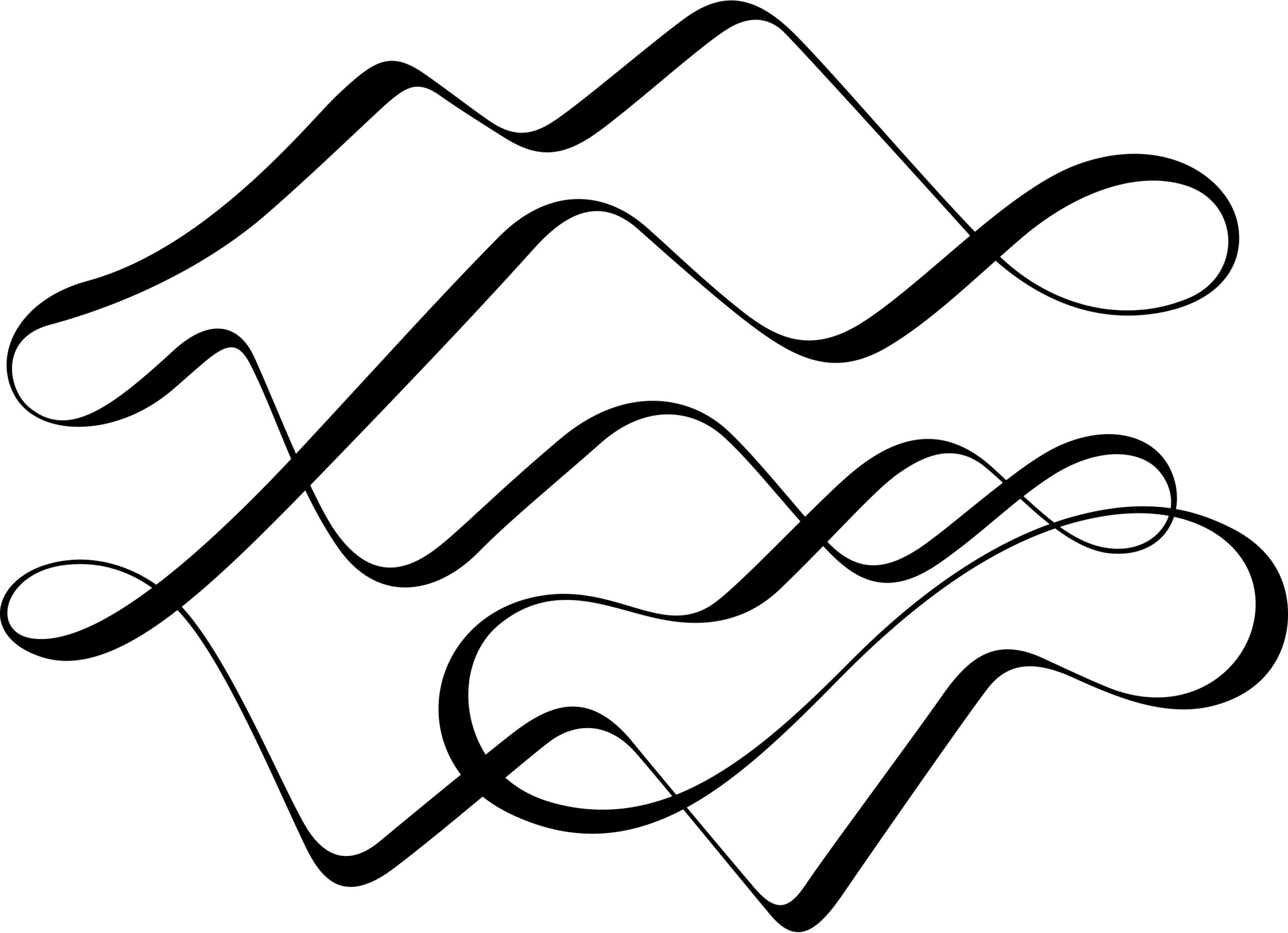URAHARA FES 2025 AUTUMN / TEAM「東京山側」ランウェイレポート
——————————————————————————————————————————
11月16日、原宿キャットストリートで開催された「URAHARA FES 2025 AUTUMN」に、東京山側DMCによるTEAM「東京山側」が参加した。
都市カルチャーの中心地・原宿に、山側の自然・文化・季節の営みが同じフィールドとして立ち上がった稀有な試みであり、東京全体を一つの地層として捉えるDMC的アプローチを可視化する実践となった。
“まちと自然の往復”をどのように体験として編んだのか。本稿では、その具体的な姿をレポートする。
——————————————————————————————————————————
原宿のまちに山側が現れる
11月の日曜日、原宿キャットストリートは朝からにぎわっていた。
古着店のラックが歩道に張り出し、色とりどりのファッションに身を包んだ若者、買い物袋を手に歩く家族、写真を撮る観光客が交差する。
街は常に変化し続ける“生き物”であり、渋谷区が掲げる「シティプライド」は、この更新をどう次世代へつないでいくかという問いと密接に結びついている。
URAHARA PROJECTは、この原宿の日常に新しい表現を折り重ねる“実験の場”として継続的に企画されてきた。
今回、そのフィールドに加わったのがTEAM「東京山側」である。
山側と街側を対立軸ではなく「東京という一つの流域・地層」に位置づける東京山側DMCの視点が、URAHARA PROJECTの思想と重なり、ランウェイという形で表現された。
——————————————————————————————————————————
“いつもの姿”でランウェイを歩く
今回のランウェイは、煌びやかな衣装ではなく、山側で暮らす人の“日常”が主役だった_
子どもたちの手には、秋川で使う釣竿、正月の餅つきに使う杵、自分たちで植えて刈り取った稲。そして あきる野市の竹クラブで作られた竹細工や竹コップ。
ガイドは、山歩きで使い込んだいつもの装備でランウェイを歩いた。
高尾山や御岳山で行者が持つ「金剛杖」も登場した。
金剛杖は、古くから行者が身を守る“大切な 相棒”として携え、山を登るときは道しるべとなり、祈りを込めるときは支えにもなる。 金剛杖が登場したレッドカーペットは、山側で積み重ねられてきた営みの歴史が、ふっと街の中へ流れ 込んだような重みがあった。
街側のカルチャーを尊重しながら外からの表現を迎え入れる——URAHARA PROJECTの姿勢は、東京山側DMCの“風土を読み解き、日常をフィールドとして扱う”態度と自然に重なっていた。
原宿の町並みのすぐ横で、山側の季節の営みがそのまま現れ、両方のフィールドが等しく立ち並ぶ光景が生まれていた。






——————————————————————————————————————————
山側の営みが都市で“可視化”される意味
東京山側DMCの活動の核には、「東京は日本の縮図である」という視点がある。
奥多摩・秋川・御岳を含む中山間地域は、多摩川流域や地層レベルで渋谷・原宿とつながっており、歴史的にも人や物が往来してきた。
DMC(デスティネーション・マネジメント・カンパニー)として同社が行っているのは、
この地理的・文化的関係性を現代の観光・教育プログラムへと再
編集することだ。
今回のランウェイは、その再編集の“都市版実験”でもある。
山側の暮らしの道具や子どもたちの探究の成果が都市の中で可視化されたことで、山側の資源が「自然体験」ではなく、「都市の生活とも関係しうる価値」として立ち上がった。
山側の視点が都市に触れ、都市の視点が山側に触れる——
原宿の中心で、それが具体的な手触りを持って示されていた。

——————————————————————————————————————————
参加者の声
ランウェイを見て足を止めた来街者は多く、素朴な道具や子どもたちの姿に関心を向けていた。
子どもを連れて参加した保護者からは次の声も聞かれた。
- 「参加した子どもたちはすごく楽しかったと言っていた」
- 「東京山側が、もっと多くの人に知られてほしいと思った」
- 「東京山側DMCにしかできないランウェイで、道行く方も立ち止まって見ていた」
こうした“都市での反応”そのものが、今回の取り組みの成果といえる。
——————————————————————————————————————————
観光と地域創生が交差する地点としてのランウェイ
今回の試みは、観光・地域創生の専門家にとっても多くの示唆をもつ。
●地域の日常は都市でこそ輪郭をもつ
山側の営みを町中に置くことで、第三者が理解しやすくなる。
●子どもの探究は最も説得力のある表現となる
身体を通した学びは、都市でも強い存在感を発揮する。
●原宿の多様性は山側の“素の姿”と相性が良い
多様な文化を受け入れる土壌が、山側の価値を受容しやすくする。
●街側と山側が両立する“余白”が新しい観光を生む
どちらかを主役にせず並べることで、新しい循環型ツーリズムへのヒントが得られる。
●東京全体を一つのフィールドとして捉えるDMC的視点
行政区でなく流域・地層・生活圏で構造化することで、都市と山側の往還が描きやすくなる。
TEAM「東京山側」のランウェイは、原宿の中心に山側の日常をそっと置く試みだった。
都市に自然の営みが入り込むことで、街はより厚みを帯び、人の往来が新しい関係性を生み出す。
まちと自然が同じ場所に立つとき、東京の観光と地域創生には新しい地平が開ける。
今回のランウェイは、その未来を具体的なかたちで示していた。
寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部