東京都は7月10~11日、「令和7年度 誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業」を推進する一環として、八丈島(東京都八丈町)で「バリアフリービーチ体験モニターツアー」を実施した。バリアフリービーチの設営と運営に取り組むNPO法人湘南バリアフリーツアーセンターの榊原正博理事長や、八丈島自然ガイドサービスしいのきの大類 由里子代表を講師に迎え、1泊2日で海水浴やスノーケリングなど、海辺のレジャー体験の設営や運営について研修を行った。

モニターツアーに障害者3人など総勢25人が参加
東京都では、障害者や高齢者等が、東京の自然を安心して楽しめる観光を推進するため、旅行業者、体験型観光提供事業者等を対象として、障害者等向けの自然体験型観光プログラムの運営ノウハウを提供する取り組みを開始している。
モニターツアーには、応募した障害者3人とその介助者、旅行会社、都内で自然体験型学習を提供する事業者など、総勢25人が参加した。以下、ワークショップの様子を紹介する。

会場となる八丈島のビーチは、東京・羽田空港から全日本空輸(ANA)の航空機で約1時間、空港から車に乗り換えて約5分の底土海水浴場。初日は、八丈富士中腹に位置する牧場で八丈島の自然や眺望を満喫する「八丈ふれあい牧場」、幅100mで長さ500mの大規模な溶岩台地の自然景観を望める「南原千畳岩海岸」を訪れた後、宿泊地となる八丈ビューホテルでワークショップとして座学に加え、ホテル内の砂利道で車椅子体験を行った。2日目は、底土海水浴場でバリアフリービーチの設営と体験会のほか、東京都指定無形文化財「黄八丈」織元工房である「黄八丈めゆ工房」やあしたば加工工場、熱帯・亜熱帯性植物豊富な公園など「八丈植物公園・八丈ビジターセンター」を見学した。

障害者が安心できる雰囲気がある場所を作る
初日の座学では冒頭、東京都産業労働局観光部の西島裕樹課長が、東京都が推進するアクセシブルツーリズムやワークショップの趣旨を説明。また、観光庁が2023年に試算したユニバーサルツーリズムの市場規模として、外出に不自由がある高齢者を含めて年間3,000万人、潜在的な市場規模は同4,000万人となっていることを紹介し、「市場規模はインバウンドと同規模、もしくは上回る大きさがある。高齢者や障害のある方をはじめ、誰もが東京の観光、魅力を安心して楽しめるように配慮されたアクセシブルな観光を目指し、さまざまな整備を進めていきたい」と話した。

東京都では、障害者や高齢者等が、東京の自然を安心して楽しめる観光プログラムを提供する事業者等に対して、プログラムの実施に必要となる備品等の導入経費の一部を補助する「誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金」を募集している。自然体験型観光を提供する事業者や観光協会などを対象に、障害者向け備品の購入費や既存備品の改造費用を補助率5分の4以内で最大200万円まで補助する。このほか、バリアフリー情報ガイドの作成やシンポジウム・セミナーを開催するなど、さまざまな取り組みを行っている。

「誰もが楽しめる自然体験型観光」ワークショップでは、榊原理事長が障害についてやビーチのアクセシビリティについて講義。障害や車いすの種類について解説するほか、高齢者や障害者が生活する上の「バリア」として①物理的バリア②制度のバリア③文化・情報のバリア④意識(心)のバリアーの4つを挙げた。障害者接遇のポイントについては、榊原理事長が「余暇を楽しむことが第一で、行った先で楽しい体験をし、おいしいものを食べるなど、充実した1日が過ごしたと思ってもらうことが重要となる」と説明した。また、障害のある人へ声掛けするときの魔法の言葉として「何かお手伝いしましょうか」「何かお困りですか」「何をすれば良いですか」といった対話手法を伝授した。
バリアフリービーチを運営する際の注意点としては、全ての人の安全確保、心の中の段差を取り払うこと、合理的な配慮の必要性などを紹介した。ビーチで必要な介助の場所については、①駐車場から海水浴場への移動②シャワー③更衣④トイレーを挙げた。
医療機器のエンジニアだった榊原理事長は研修で訪れたスウェーデンで、障害者がビーチでリラックスして過ごす姿を目にし、バリアフリービーチを日本でも実現しようと決意。モビマットという不整地対応のマットを導入し、神奈川県鎌倉市材木座での活動を皮切りに、全国50カ所以上でバリアフリービーチを運営している。

大類氏は、「スノーケリング体験での注意点とバリアフリーに対する想い」をテーマに、これまでの知的障害者の海水浴サポートや、車いす・聴覚・視覚障害者のスノーケリングサポート、運動機能障害・聴覚障害者の登山サポートの経験などを伝えながら、自然に親しみながら手伝うことの大切さを説いた。自然体験ツアーの受け入れを行っている理由については、「多くの人に自然を楽しんでもらいたい」と答えた。
「およげない」と「しょうがい」への対応についても説明。大類氏はできないことをサポートすることを第一に掲げながら、「呼吸の確保やバランス・浮力の確保をすることで、条件問わず安定と安心が確保できる」と述べた。
大類氏は神奈川県横浜市出身で、八丈島自然ガイドサービスしいのきを2009年に設立した。島在住は26年、ガイド歴は20年。現在は、森林インストラクターやPADIダイブマスターの資格を取得し、トレッキングガイドやスノーケンリングガイドを行っている。ガイド以外にも八丈島でビーズアクセサリー講師を務めている。

講義後はホテルの駐車場に場所を移して、水陸両用車いす「モビチェアー」と車いすけん引装置「JINRIKI」の使用方法をプランニングネットワークの渕山知弘氏(オフィス・フチ)が指導。翌日のバリアフリービーチ運営のために車いすの機能や基本操作を学ぶ体験が行われた。初めて車いすを操作する参加者がいる中、渕山氏は「なぜ旅行業者や観光関係者が車いすのことを知らなくてはいけないか」など解説し、観光地や悪路でのサポートの仕方などを伝えた。参加者からは、「車いすのたたみ方や、ブレーキの使い方など、知っていそうで知らないことが多かった。知ると知らないでは大きな違いで、帰社後には同僚に伝えていきたい」といった声が上がった。

バリアフリービーチの運営を体験
2日目は、底土海水浴場に集合しブリーフィングの後、バリアフリービーチの設営から参加者が行った。設営では、車椅子利用者の移動を支援するロール状の「モビマット」が護岸から波打ち際まで敷き、スムーズなアクセスルートを整備した。その後、障害者はインストラクターの大類氏の指導のもと、ウェットスーツを着用。介助者やその他の参加者は、砂浜までの急なスロープでのサポート方法を見学するほか、実際にモビマットから海へ入る際の補助を行った。

海上では、潮流や波の状況を確認しながら、モビチェアーやシュノーケリング用具を用いて活動を実施。障害者1人に対し3人以上のサポート体制が組まれ、安全面に最大限配慮しながらビーチ体験が行われた。体験会はおよそ2時間にわたり行われた。

参加者からは「海でおぼれたらどうしようなど不安な点もあったが、障害者向けの備品の用意があること、適切な介助方法をしることでスムーズに運営ができることが知れた」、介助者からは「普段は一人で全てを行わなければならないと思い、旅に躊躇していたが、サポートがあるツアーであれば、全員が楽しめる」といった声が上がった。適切な指導、運営が行われたことから、サポートに当たった介助者の笑顔が印象的で、和やかな雰囲気が広がっていた。
底土海水浴場は、八丈島では唯一の人工砂浜でありながら高透明度を誇る海水質が評判。環境省の水質判定では、最上位の「AA」評価を連続して受けており、水質の清潔さ、安全性が全国的にも非常に高く評価されている。

補助金を活用した備品購入、旅行商品の開発につなげたい
ワークショップ後には、意見交換会を開催。旅行会社10社、特に都内に拠点を持つ全国旅行業協会(ANTA)加盟、東京都旅行業第2種登録の事業者が多く、体験を振り返った参加者からは東京都アクセシブルツーリズムの可能性、車いすやけん引装置などの補助金を活用した備品購入の検討、旅行商品の開発に向けた展望などが語られた。また、事業や取り組みの継続性、地域間連携による取り組みの推進を求める意見も上がった。


【参考】
東京都「誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金」の詳細は、以下URLから。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/nature
東京都「誰もが楽しめる自然体験型観光」特設サイトは、以下URLから。
https://www.sangyo-rodo1.metro.tokyo.lg.jp/tourism/accessible/nature/
取材 ツーリズムメディアサービス編集部






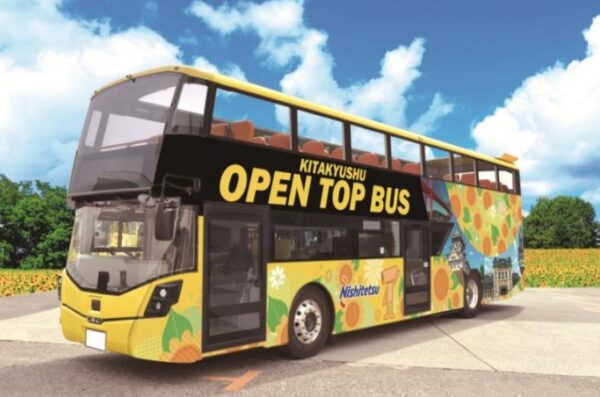





八丈島でのバリアフリービーチ体験素晴らしい取り組みですね。配慮が必要な家族がおりますので、誰もが安心して楽しめる旅行が増えるのは本当に嬉く思います。こうした情報がもっと広がると良いなと心から思います。貴重な情報ありがとうございます✨️